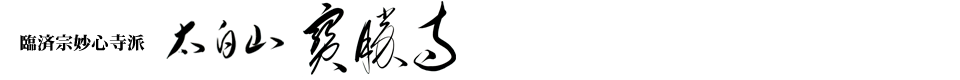和尚のちょっといい話
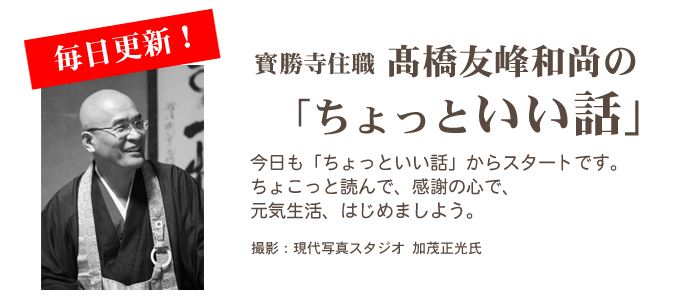 |
花菖蒲園の草引きがシルバー人材センターのスタッフの皆さんによって今日から始まりました。六月に開催される「さん華まつり」に向けての準備がこれから進められて行きますが、今年は温暖化現象の影響からか苗の生育が例年より早く感じられます。
このお祭りももう三十年以上続けられており、近年は新しく薔薇園も加わって紫陽花とともに三つの花が咲き競うのも間近に迫っています。和尚も今後は時間を見つけて園内の整備に入りますが、いつも子供の成長を見守るような心境でいます。
寺内では昨日より引き続き新入社員の坐禅研修が行われており、こちらもまた日本の未来を担う大切な金の卵の皆さんですので、副住職による懇切丁寧な気合の入った指導が行われていました。今日で研修は終了しますが、「朝打三千 暮打八百!」 若者達には大いに頑張って頂きたいと念じています。
境内には燦燦と太陽の光が降り注ぎ、苔むした庭がいっそう緑色を増してきました。極楽浄土とはまさしくこのような光景に違いないと感じ取ったものです。この時期は何もかもが一気に成長して行きますが、身も心も全くに爽快そのもので和尚も久しぶりに故郷の春を満喫しています。勿論のこと春風を受け桜花乱舞状態、言葉を失います。まもなくこの八日に降誕会(御釈迦様の生誕日)を迎えますが、大自然の営みが祝福の意を表しているかの如き感です。人生には皆、色々な節目が有るように和尚にとっても今年は大きな節目の年。「向上心」を失速させないようにしながら「頑張るねん(年)」にしたいと研修会に臨みつつ新たなファイトの念を抱いています。友峰和尚より
今日から大安禅寺では企業の新入職員坐禅研修会が始まっています。この後も数社の研修会が予定されていますが、新入社員にとっては緊張感の中での修練となっています。参加される皆さんは既に入社が決まっているわけですが、入社直後の禅寺に於ける宿泊坐禅研修だけに尚更のこと気持ちも張りつめた状況となっているようです。
大安禅寺 樹齢三五〇年のしだれ桜
そもそも卑山のような悠久の歴史を有した環境下での研修の意義ですが、やはり一番のメリットは普段の社会的喧騒から離れ、静かに坐って自分の姿や心と対面できるところに有るかと思います。また、規則正しい生活リズムに自分を置くことで心のリラックスを得ることでしょうか。現代はストレス社会と言われ続けている中に有って、自己コントロールの難しさを多くの方が感じ取っている事と思います。社会人としての第一歩は「立志」に有ると思いますが、今の時代はそれ以前に、「自分とは一体何者なのか?」という、己を見極める時間が求められているように思います。早朝の読経や坐禅は値千金です!「人間は何が故に働くのか?」などという質問は消え失せてしまいます。坐禅研修の目的を問われるなら、その答えは「有り難し」「おかげさまです」、この二つの心をしっかり体得する事に尽きるかと思います。さて和尚も老骨に鞭打って若者と共に参加したいと思います。桜満開の大安禅寺! 鶯の鳴き声に祝福を受けながら頑張って参りましょう。友峰和尚より
明日から企業の新入社員坐禅研修会が始まる為、特別法話の原稿書きなどをしましたが、毎年この時期になると自然と気持ちも引き締まる思いです。近年では新入社員の研修カリキュラムなどもずいぶんと様変わりしていますが、基本的には礼儀作法の修練を中心に、新社会人としての心構えや忍耐力の修行が組み込まれています。20年ほど前までは多くの企業がこぞって禅寺での宿泊坐禅研修を取り入れていましたが、最近では「社会人とは、会社人とは」といった内容の講義型研修が主力となっているそうです。そもそも「働く」という概念に於いて昔とは意見を異としている今の新社会人に、「働く事の意義」から教えていくことは各企業にとって真剣な課題となっているようです。そう言えば昔にこんな言葉が有りました、「働かざる者食うべからず」とか「食えなんだら食うな」とか少々過激な言葉だと思いますが、我々の宗旨には「一日為さざれば 一日食らわず」という中国の高僧・百丈懐海禅師の遺した有名な言葉が有ります。日本的言葉で言えば「もったいない」ということでしょうか。禅宗では、働くことの概念を「作務(さむ)」という言葉で位置づけています。「心をどのように働かせ、一日を通して身体をどのように使いこなしたか」を言います。「働く」は労働ではなく「どう心を働かせたか」と問うているのです。本当に和尚も納得ですね。人生は二度無い、今をどう生きるか! その事が働く意義につながっていく事と思います。
「春風 福寿を生ず」 渓仙 書
「今という 今こそ今が 大事なり 大事の今が生涯の今」の禅語の如く、新社会人となられる皆様、いま自分が無事で有る事に深く感謝しながら、大いに自分を生かして社会の幸せに貢献して頂きたいと念じます。それと同時に、皆様のご健康とご活躍を願い心から祝意を表したいと思います。友峰和尚より
犀川の風景
ぽかぽか天気のお花見日和となった爽やかな土曜日の朝を迎えました。NHK人気朝ドラ「あさが来た」も今日が最終回という事で是非是非見ましたが、最初から最後まで本当に心から楽しませてくれた、実に毎回が充実した連続テレビドラマでした。和尚が評価するまでも無く、今日までずっと高視聴率をキープしてきたことがその人気度を示しています。主役の波瑠さんを先頭に次々登場する全ての俳優さんの演技が見事で、ドラマが進むにつれ演技力もアップしていくというドラマはそんなに見たことがありません。ストーリーも明快で、明治期の実在した人物の自叙伝という事で信憑性が有り、また一家族の生涯を描いた作品としてとても親近感を覚えました。和尚はこれまで一度も朝ドラを見たことがありませんでしたが、今回は本当に毎朝熱心に鑑賞し、色々な意味で勉強になりました。明日からは夢が覚めたような超現実的な朝を迎える事になると思いますが、この6カ月間、楽しませてもらったことに感謝したいと思います。さて、4月に入って周りの雰囲気ががらりと変わってきました。やはり新年度を迎えて人々の心も新たな人生を歩み始めているように感じます。
 犀川沿いの桜の花が満開となりました。道行く人々も、歩行速度を速めながら桜並木の方角に引き寄せられて行く姿が印象的な一日となりました。流石にここ数日間は家の中に居るより満開の桜と心を共にしたいものですね。「人生心の花を咲かせましょう!」お元気にお過ごしください。友峰和尚より
犀川沿いの桜の花が満開となりました。道行く人々も、歩行速度を速めながら桜並木の方角に引き寄せられて行く姿が印象的な一日となりました。流石にここ数日間は家の中に居るより満開の桜と心を共にしたいものですね。「人生心の花を咲かせましょう!」お元気にお過ごしください。友峰和尚より
寳勝寺に「アラン・ドロン」がやって来た!って。ホッカホカの快晴の天気に恵まれた今日、早朝より「ドロン」を飛ばしての空撮が行われました。いよいよ始まる霊苑改葬工事の準備の為、施工業者によるドロンでの空からの調査でしたが、実に空高く舞い上がった遥か上空からの寳勝寺一帯の風景を見るのは初めてで、思わず文明の力を感じた瞬間でも有りました。此れまではヘリコプターでの空撮が主でしたが最近はすっかり「ドロン」が主役となっているようです。
ウォーミングアップ中・・・
モニターに映し出された寳勝寺上空の画像
月替わりの4月初日を迎え朝一番に檀家様のお参りに行きましたが、金沢城周辺は桜の御花見客で賑わいを見せていました。金沢の桜の満開情報は4日頃となっていますが急激な気温の上昇で一気に花が開いていくようです。皆様も是非お花見見物にお出かけください。今日はエイプリルフールだそうですが、騙す事も騙される事も無く穏やかな1日を過ごしました。午前中には以前しいのき迎賓館での個展開催で大変お世話になった才田様と「あとりいえ」主催の山田様が来られ、久しく歓談しました。
本格的な春のシーズンを迎え金沢でも色々なイベントが企画されていますが、特にしいのき迎賓館でのイベントには和尚も注目しています。金沢を代表するパワフル女子!お二人の活躍を今後も期待したいものですね。和尚も心から応援したいと思います。金沢女子万歳! 和尚はドロン? 友峰和尚より
寳勝寺檀信徒の北條淳子様から、たくさんの珍しくまた素晴らしい切手をご寄贈頂きました。淳子様が切手コレクターとして長年収集して来られたものだそうで、この度その貴重な数々の切手を卑山の寺務用に使ってくださいとの事でした。されどとてもとても貴重な物ばかりで使用する気になれず、さっそく淳子様に利用方法等をお電話したところ、やはり通信用に使って欲しいとの要望でしたのでこれから使っていきたいと思います。お寺の各所には多くの方々から寄進を受けた品物が使われています。その一つ一つを寄進者に思いを馳せながら大切に使っています。皆様が寺カフェに来られました折には、ランチョンマットやコーヒーカップ、急須、椅子に机そして花器や屏風等々に注目して頂ければと思います。本当に有り難い事ですね、皆様の心を頂きながらの寺カフェです。大いに利用して頂きたいと思います。
 ㈱キタジマ(福井市高木中央)代表取締役会長・北嶋様ご夫妻が来山下さいました。
㈱キタジマ(福井市高木中央)代表取締役会長・北嶋様ご夫妻が来山下さいました。
このところ穏やかで暖かい日が続いていますが、次第にお花見気分が高まってきました。犀川沿いの桜並木の蕾も大きく膨らみ中にはすでに咲き始めているものも有ります。
本日午後の犀川沿いの風景 (住職撮影)
愈々明日から4月を迎えますが、満開の桜の花と共に新入社員や新入生の初々しい姿が見られるのもこの時期です。大安禅寺ではまもなく企業新入社員の宿泊研修会が始まろうとしていますが、社会人として、第一歩を踏み出す為の心構えを修得する研修でも有ります。和尚も初心に戻って参加したいと思います。「鉄は熱いうちに打て」との格言が有りますが、和尚のように冷え切った鉄も熱い思いで、いま一度融かしてみたい思う今日この頃です。友峰和尚より
御祈願のお経を上げました。
3月も残すところ、あと2日となりました。4月は、昔の暦で「卯月(うづき)」といいます。そのいわれは「卯の花の月」または稲を植える為の「植月」から来たと言われていますが、干支でいけば1月の「子」から始まり4月は4番目の「卯」の月という事になります。いずれにしても「心のうずく月」で待ち遠しかった本格的な春を迎え、心うきうきする月には違いないようです。

桜前線も一気に北上してあちこちの開花状況が伝えられていますが、金沢市内の桜の名所・兼六園では4月8日頃が満開の予報となっています。桜開花のニュースは否が応でも心を外へ外へと誘ってくれます。寳勝寺玄関先の早咲きの桜はもう既に満開となっていて、寺カフェ利用の観光客の方が記念写真を撮って行かれる姿が見られます。また爽やかな春風の中にも桜のほのかな匂いが感じられますが、一斉に吹き出る新芽からの匂いも混ざって甘い香りが漂ってきます。
やはり春の到来は日本の人々にとって格別な季節のようで、道行く人々の笑顔がとても素敵ですね。金沢を訪れる外国人観光客の方々もお花見を楽しみにしているという事で、今や日本全国でのお花見は日本観光の目玉の一つとなっているそうです。
さて、和尚は「ちょっと一服」で、4月を目前にして鋭気を養うために今日は休息をとりました。日々の仕事リズムから解放されると周りの事がよく見えてくるものです。休息は、日々の人との大切なご縁を振り返って感じ取る時間でも有ります。多くの人のご縁によって今が有ることを感謝した一日ともなりました。大いに休息して、明日から再び全力投球で参りましょう!「俺がやらねば誰がやる 今やらねばいつ出来る」時間との戦いが続いていきます。友峰和尚より
皆様にはその後お変わりなく、お元気にお過ごしでしょうか? 今日のように気温が上昇してくると、それに呼応するかのように人の出入りも急に激しくなっていくようです。
朝一番のお客様はグリーン産商(お守り販売の会社)の営業の方でしたが、先日のブログでも書きましたように近年は寺社の御守りにも変化が現れ、これまでのようなシンプルな物とは違って若者向きのおしゃれな色柄に変わりつつあります。寳勝寺の御守りはオリジナルのものが多く、特に「美し御守り」は人気があります。また、絵馬風の祈願式御守りも人気があるとの事で、やはり願い事が叶うようにと祈願した後の御守りは、御利益効果が一層高まると言うものです。
山門かさ上げ工事の打ち合わせ中
午後には「寶勝寺霊苑改葬工事」に際しての山門かさ上げ工事関係者が来られ、現場立ち合いとなりました。春の暖かさに連れられての打ち合わせはとても気持ちの良いものでした。夕方には、先日試飲した新しいコーヒーメーカーの納品に立ち合いましたが、午前午後それぞれに、皆プロフェッショナルとしての意気込みを感じさせてくれました。「世のなかそんな甘いもんやあらへんで」っていう感じが直に伝わって来た一日となりました。
いいですね。人生は本当に、「今を生きる」ことに尽きますね。「頼もしい」という言葉が風化しつつある世の中に有って、今日は真に天晴れあっぱれ!と言いたくなるような人との出会いの一日となったようです。好天気に恵まれた早春の寺カフェ、お客様も何処となしか、ほっかほかを楽しんでいるように思えました。友峰和尚より
地元HAB北陸朝日放送5チャンネルの4月4日から始まる新番組「2時はドキドキ」にコメンテーターの一人としての出演依頼要請を受け、番組のメインキャスター・牧野慎二様が本日ご挨拶に来られました。この4月からは各局一斉に新しい番組が登場しますが、この「2時はドキドキ」の番組は地元の話題を中心にした食・レジャー・医療・子育て・老後など実生活に役立つ「本物志向の情報(くらしズム)」の探求を目的とした視聴者目線の番組で生放送されるとの事。北陸三県で放送され、和尚は4月12日より出演予定となっています。
久しくテレビ出演から遠ざかっていましたが、今から出番を楽しみにしています。70歳近くになりますと衣食住全てに対して気を遣うようになる中で、色々と学習できることを期待しています。最近、テレビ番組の編成では地域密着型のものが多く見受けられます。これからの番組作りは身近なテーマが中心となって行くようです。「2時はドキドキ」、お時間が有りましたら是非ご覧ください。さて皆様はどんな時にドキドキしますか? ハ~イ!「早く走るとドキドキします!」そんなドキドキではないのです。希望に満ち溢れた青春時代! あの頃を思い出し、いま一度ドキドキしてみたいものですね。間もなく桜も満開となりますが、その時こそ思い切ってドキドキしながら眺めてみたいものです。「和尚さん~お酒の飲みすぎは慎みましょう」ドキドキ?? 友峰和尚より

北海道新幹線が開業して日本全土がどんどん狭くなっていくような感じですが、同じく金沢ー東京間が新幹線で2時間20分で結ばれたのも凄い事です。和尚の中学生時代は修学旅行先が東京でしたが、当時は蒸気機関車内で一泊しての上野駅到着でしたから実に東京が遠く感じたものでした。今日は日曜日という事もあって、新幹線を利用しての観光客の方が寺カフェを利用されていたように思います。また金沢ー長野間も約1時間ということで、こちらも魅力的な観光ルートとなっています。現在は、新幹線開通の威力を見せつけられた感のある観光都市・金沢のようです。今後は北海道新幹線も札幌まで整備されるとか。北陸新幹線の福井駅延長工事も加わって開通を今から楽しみにしています。ところで皆様はもう北陸新幹線に乗車されましたか?「和の未来」をテーマにしたアイボリーのおしゃれな車体に、北陸の空と海を表すブルーと伝統的工芸を表す銅の色が見事な線で描かれています。乗る者の旅の心を高揚させるにふさわしい北陸新幹線の車体を見るのも楽しみの一つですね。さて、和尚は寺カフェサポート役の一日でしたが、午後からはお客様の合間を見て色紙書きをしました。旅行を楽しんでいる皆様の姿を拝見しながら和尚の心は、いつしか孫たちと共に新幹線でディズニーランドに行くことを想像していました。
穏やかな時間が過ぎて行く日曜日の寳勝寺に有って、現実と非現実との世界の中に心を馳せた早春の休日でした。観光客の足音と共にまた一歩、心も弾む卯月の季節を迎えようとしています。友峰和尚より