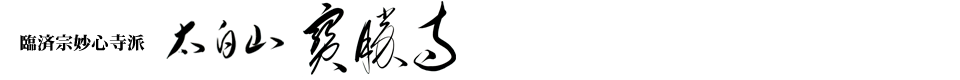和尚のちょっといい話
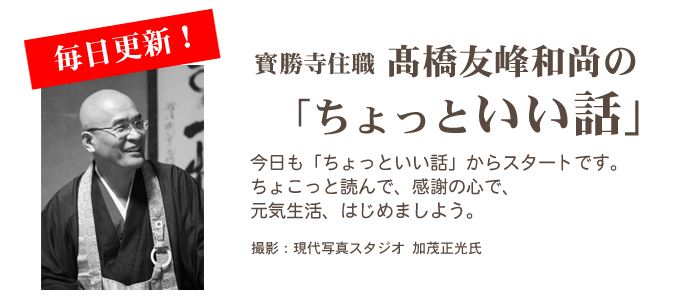 |
個展2日目はカリキュラムが目白押しで、午前10時から始まった学生との懇談会を皮切りに、御茶会、書道教室、そして午後4時より今回最初の坐禅会が「メディテーションルーム」で行われました。参加者は大学教授や学生さんなどで、少人数ではありましたがサラ・ローレンス大学で開催される初めての坐禅会でもあり、真剣な面持ちで約一時間の坐禅にトライされました。千里の道も一歩からですね。そもそも坐禅をした部屋は学生達のメディテーションルーム(瞑想室)として普段から活用されている場所でもあり、坐禅の布団や坐禅台もあり、あらゆるものに対応されている大学側の姿勢が伺えました。現在ではアメリカ全土に禅センターがあり、ニューヨークにも沢山あるとの事でした。爽やかな気分になったところで、今回初めての夜のニューヨーク市内観光とブロードウェイ「オペラ座の怪人」鑑賞に出かけました。
ホテルから車で10分足らずのところにある、ブロンクスビル駅 ( 撮影:斉藤公一氏 )
電車を待つ一行 ( 撮影:住職 )
( 撮影:斉藤公一氏 )
グランドセントラル駅にて
ニューヨークの中心部 タイムズスクエア
和尚にとっては40年ぶりのニューヨーク市内。タイムズスクエアの電飾にはさすがに圧倒されました。半端じゃないですね! 思わず新宿歌舞伎町を思い出していました。大がかりな電飾は日本の企業が担当しているとか、世界の観光都市パリで見たシャンゼリゼとはずいぶん趣が違った大都市の風景でした。開演時間までには夕食が間に合わないと言うので、仁さんがグランドセントラル駅の構内で沢山のサンドイッチを購入して下さったのですが、皆さん劇場前で並びながらの立ち食い状態となり、おまけに時間も迫り大急ぎで口に詰め込む羽目となりました。ブロードウェイでの観劇、これがホントの大感激! すばらしい歌劇に酔いしれた数時間でした。場内は世界各国からの観光客でぎっしり満員。座席も狭く和尚にはちょっと窮屈でしたが、ここは世界のニューヨーク、仕方のないことです。ガマンガマン。
マジェスティック劇場前にて、長蛇の列に並んでいます ( 撮影:斉藤公一氏 )
大混雑の中、皆でサンドイッチを食べました
満席の会場内、開演を待っています ( 撮影:住職 )
舞台の美しい装飾
終演後、大混雑の劇場ロビーで感激を語り合っています ( 撮影:住職 )
帰路、ネオン輝く大都会を馬に乗ってパトロールする警察官を見ました ( 撮影:住職 )

カッコいいので、何枚も写真を撮りました ( 撮影:住職 )
ワイワイガヤガヤ、地下鉄と在来線に乗り換えての帰路はニューヨークの夜を堪能しながらの休息日となったようです。つづく
晩秋の空 / 寳勝寺山門にて
晩秋の澄み切った青空が金沢の空に広がっています。この時期、北陸特有の筋状の雲が白山山系にもかかり、なんとも言葉では言い尽くしがたい風情を見せています。国外に出ますと一番に感じるのは空の色と雲の出具合で、アメリカなどはさすがに大陸を感じさせるに相応しい、際立った大雲が延々と高く広く連なっていますし、パリで見た雲はどことなく転々として、同じ大陸ながらその形は随分と違うものですね。またそれぞれに国の匂いも異なり、今回のアメリカ訪問では特にスーパーマーケットなどに行きますとその違いは歴然です。物の大きさもまた異なり、ジュースや牛乳などの入れ物に到っては驚くほどビックで、そこにも国の大きさの違いを感じ取ったものです。大体、町から一歩外に出ればハイウェイが連なり、日本での日々の生活がいかにスローライフであるかしみじみ感じ取った毎日でした。さて話しの続きですが、グリフィス教授がサプライズを用意していてくれたのが、サラ・ローレンス大学学長招待の夕食会でした。
夕食会にて、大学長様とともに ( 撮影:斉藤公一氏 )
会場エントランスにある一室
今回の「禅文化墨蹟禅画展と茶華道展」の開催は大学とグリフィス教授からのオファーで実現したものですが、夕食会場となった建物は大学内にある学長様の住居で、1921年に建造されたヨーロッパ中世頃の様式を思わせる実にクラシックな建物。写真にある通りの室内もおしゃれなインテリアで素晴らしい雰囲気でした。夕食会開催に当たり、和尚も事前にメアリーさんから教わった英語でのスピーチで感謝の意を伝え、その後は和やかな交流のひと時を過ごしました。野口社中の皆様は全員で童謡の合唱と民謡「丸岡音頭」の踊りを披露され、大学側の招待客を巻き込んでの大変な盛り上がりを見せたものでした。
スピーチのようす ( 撮影:斉藤公一氏 )

さきほどの緊張した御茶会とは打って変わってのはしゃぎぶりでしたよ! このような体験ができたことは参加者にとって生涯忘れる事の出来ない思い出となったようです。一歩一歩また一歩、順調に滑り出していく感じが伝わった楽しい夕食会でした。つづく
( 撮影:斉藤公一氏 )
開催初日、午前11時半から、野口美智子先生の真骨頂でもある「生け花デモンストレーション」が大学関係者向けに行われました。これまでにも何度も何度も、野口先生が花を生け込む姿を拝見させてもらって来ましたが、今回はまた格別に違っていました。実に丁寧でわかり易く、しかもゆっくりと説明しながら、一枝一枝を花瓶に差し込む姿には美しさを感じたものです。補佐をされた酒井む津子さんも、陰に日向に黒子としての役割を笑顔を以て対応されていた姿にも感心させられたものでした。師匠と弟子との阿吽の呼吸とでも申しましょうか。和尚などはどうしても花より人の方に目が行ってしまうわけですが、一つ一つの立ち居振る舞いこそが見事な生け花を作り上げていきます。静まり返った中での花切りばさみの音や息遣いが、見つめる人の心を打ちます。
興味深く見つめる学生さんや教授、大学関係者の方々 ( 撮影:斉藤公一氏 )
おひとりおひとりに、丁寧に説明される野口先生 ( 撮影:Gene Foulk 氏 )
( 撮影:斉藤公一氏 )
ワークショップのようす ( 撮影:斉藤公一氏 )
( 撮影:斉藤公一氏 )

サラ・ローレンス大学の学生さん、通訳をして下さった舟山先生とともに ( 撮影:斉藤公一氏 )
デモンストレーションの後、12時半から開催された生け花ワークショップでも多くの参加者が進んで生け花にトライしていました。国外での2度目の開催となった生け花ワークショップ。野口社中の皆様が堂々と日頃の腕前を参加者方々に教えている姿には、日本文化を身を以て伝えようとする意気込みを感じとった楽しい時間となりました。その日の午後4時からは、個展会場で大学長様はじめ大学関係者、VIPを招待しての野口社中の御茶席が開かれました。
静粛な雰囲気のなかでの、姉崎志乃様によるお点前
説明に聞き入るご列席の方々
姉崎志乃さんのお煎茶お点前披露は、和尚もこれまでに経験したことがないほど静粛で緊迫感漂うものでしたが、それはそれでまた風流な趣でした。何もかもが皆にとって初体験のアメリカ、ニューヨーク。サラ・ローレンス大学での一幕でした。つづく
先日、今回のニューヨーク個展に最年少で参加された小学6年生の加賀好さんからお礼の葉書が届きました。とても可愛い素敵な葉書に、綺麗な字で、感動した沢山の気持ちが綴られていました。すべての催事を無事終了した今、色々な思い出が蘇えってきますが、なかでも、好さんの参加は常に緊張感を緩和させてくれるマスコットのような存在でした。いつもぴょんぴょん跳ねている小リスのような感じで、周りの人たちへの気配りやお手伝いなどには感心したものです。彼女はクラシックバレーと書道を日々修業されているとか。個展初日の午前10時から行われた「第1回 書道教室」の時には生徒として参加し、学生さんの模範としての成るほど!見事な字を披露してくれました。
野口社中の丸子さん、北島さんとともに ( 撮影:斉藤公一 氏 )
書道教室のセッティングをお手伝いしてくれています
8名の学生さんとともに、好さんも書道教室に参加
好さんの字を見本に「楷書・行書・草書」の説明をされる 中 智恵子 先生
これまでにも色々な場所で個展を開催してきましたが、その都度思いますのはやはり、人との御縁を結ぶなかで自分を含めて誰かしらの成長を願うわけですが、今回は会期中に日々成長を見せる好さんに何より目を見張るものを感じたものです。勿論、参加されている方々も目に見えぬ成長と自信を獲得されていったことと思いますが、人生、若い時の経験ほど大切なものは有りませんね。アメリカのグローバル社会、しかもサラ・ローレンス大学の学生との学習となりますと相当なプレッシャーがあったと思いますが、堂々としかも丁寧に書き上げた彼女の心持は今後の修学にも大きな自信になる事と思います。書道教室が終了するや否や、そこはそれ、すぐに学童に戻って童心そのままに愛嬌をふるまう姿もまた可愛いものでした。
初めて書道を体験された学生さん!また得意げに書かれた学生さん!学生っていいですね!! 担当の中 智恵子先生もとっても素敵な方でした。和尚も久しぶりに教壇に立った面持でした。思えば大学時代に習得した教員免許、どうやらここにきて、アメリカでやっと役に立ったような気がしましたよ。つづく
話を進めましょう。今回も越前和紙作家・長田和也氏に無理をお願いして個展会場と御茶席の間仕切用にタペストリーをお願いしたところ、初めて見る実に見事な和紙作品が届いていました。個展会場を設営するときはいつも思うことですが、会場に立体感を持たせるためには何か仕切りが必要で、予め寸法など知らせてはいたものの高さもぴったりで場内がいっぺんに引き締まりました。越前和紙の香りとデザインの美しさにしばしうっとりしたものです。
野口先生が、タペストリーのポールをセッティングされています
丁寧に包まれたロールを開いてみると、美しい和紙作品が登場しました
テグスを通しています
大学専属の大工さんにお願いし、天井から吊るしているところ

位置や 傾きを、慎重に調整中…
「オッケー! 素晴らしい!」
長田氏は以前、ニューヨークで越前和紙の展示会をされたと聞いていました。今回は仕事の関係で参加できませんでしたが、新しい作品を提供して下さり本当に有り難く感謝いたしました。越前和紙のタペストリーのおかげで立体感のある作品展示が出来たことは言うまでもありません。真っ白な網目模様の越前和紙の隙間から眺める会場の風景も格別なものでした。サラ・ローレンス大学長様はじめ副学長様からも賛辞を頂きました。野口先生はじめ社中の皆さんも次々と手際よくお花を活け、より一層華やいだ雰囲気を醸し出していきました。ここが日本から遠い遠い国アメリカ合衆国ニューヨークの一角での生け花であることを一瞬忘れてしまうほど、皆さん真剣な面持ちで丁寧に生け込みをされていました。以前パリ個展開催に同行された社中の方々は流石になれたものでした。
二日間に渡って会場の設営がなされたわけですが、全てが終了したのは二日目の夕刻すぎで、愈々明日開催を前にして誰もが成功を念じたものでした。つづく
雨上がりの後の冷え込んだ大安禅寺の朝を迎えました。8時から庫裡玄関前の松の木の選定が今後新しくお世話になる庭師の斎藤 満さんとお連れの方とで始まりました。今年は北陸地方は大雪の予報が出ているので、雪吊りなども急がねばなりません。境内建物周辺の雪囲いは世話方さんによって早々と済んでおり、融雪装置の設え等を若干残すのみとなっています。長い長い厳しい冬を越すには十分な準備が必要ですね。
本当にのんびりムードの時間を過ごしています。漸く時差ボケからも解放されつつあり、体も楽になってきました。昨日の続きですが、個展会場となった大学図書館の二階の部屋は、今回の個展開催のために改装して下さったとか、なるほどまだペンキの後の残る綺麗な空間でとても気に入りました。昼食を終え腹ごしらえもしっかりして会場設営に入りました。
会場に入ってまず驚いたのは大安禅寺で制作した掛軸台と全く同じものが4台置いてあったことです。大変ビックリしましたよ!日本から送るには送料が相当かかるというので断念した製品と同じものが其処に有ったわけですから、無理からぬ話です。これは仁さんが、自分の工房で日本で見た製品と同じものを作成しておいたとの事で、もう感激でした。それだけではなく14個もの花置台も自ら手作りで作成したものでした。馬子にも衣裳という言葉が有りますが、やはり掛け軸やお花を展示するにもそれを飾る為の道具が必要というものです。そのほか展示用のパネルもあり完璧でした。
全員で手分けして、仁さんの作ってくれた花置台を運びました。
仁さんに続いて、斉藤さん。
斉藤さんに続いて、野口先生。
グリフィス教授の友人の庭師さんから提供された、花材の一部
沢山の枝の中から、野口先生と社中の皆様が選別され枝葉を処理されました。
もう何も言う事はありませんひたすら展示の準備に入りました。野口社中の皆様が使用される花材も山ほど用意されていました。写真の如くです。グリフィス教授と仁さんの今回の個展開催への強い気持ちが伝わってきた瞬間でもありました。
日本から送った掛軸や額、備品など。毛氈に包み送った作品も
休憩中のようす
右へ、左へ、相談しながら机を移動中
日本から丁寧に送られた作品を開封しながら、個展開催成功を祈りながらの展示設えが始まりました。三月に開催された、金沢しいのき迎賓館での墨蹟禅画展を思い浮かべながらの作業となりました。ワイワイガヤガヤもう野口先生も社中の皆さんも我々スタッフもわき目も振らずぶつぶつ言いながらの集中した時間となりました。つづく
10月20日(月)、ニューヨークでの最初の朝を迎え、早速にサラ・ローレンス大学へ個展会場の視察と設営に行きました。昨晩はぐっすりと休めたおかげで長旅の疲れも出ず、元気にホテルを出発できました。サラ・ローレンス大学から専用車が迎えに来ており、曇り空ながら空気の引き締まるような冷気のなか一路大学へとハイウェイを突っ走り約20分足らずで大学に到着。学内の風景の素晴らしさは息をのむほどでした。前もってビデオや写真で見ておいた感覚とは全くに違って、スケールの壮大さや学舎の美しさに圧倒されたものです。
大学の事務室が置かれている、1921年頃の建築物 (撮影:斎藤公一氏)
初代大学長の肖像画の御前にて (撮影:斎藤公一氏)

個展会場となった大学図書館の入り口 ( 撮影:住職 )
あとで聞いた話ですが、大学の建物の立ち並ぶ地域はニューヨークでも屈指の高級別荘地だそうです。なるほど、どの建物も個性豊かなものばかりでした。グリフィス教授の案内で多くの建物の見学に向かいましたが、今回の個展会場となった大学図書館の2階は、完成したばかりの実に素晴らしい空間でした。個展会場の両側が図書室という一風変わった場所にも思えましたが、とても静かで大変趣のあるお部屋で、いっぺんに気に入ったものです。大学の図書館というとどこか硬いイメージがあると思いきや、たくさんの小部屋や閲覧室、視聴覚室、勉学室等があり多くの学生が集う、いわば学生さんの溜まり場のような存在でも有るようでした。あっという間にお昼時間となり楽しみにしていた学食体験ということで、グリフィス教授の案内でサラ・ローレンス大学の学生食堂初体験となりました。
いやはやものすごい量で品数も多く、極めて贅沢な昼食でしたよ。個展開催中は毎日、大学教授や学生さん達と一緒に昼食を頂くこととなりました。このこともグリフィス教授の粋な計らいでした。学食を経験できるなど思ってもみなかったですからね。最初から驚くことばかりでした。勿論デザートには和尚の大好きなアイスクリームをてんこ盛り食べましたよ!大食のアメリカ合衆国、食べ物の量も半端じゃなかったね。つづく
静かで穏やかな時間が流れていきます。本当にまるで時間が止まっているような感覚が続いています。ニューヨーク滞在中のスピード感あふれる日々の生活とは全くに対照的ですね。先に帰国された皆様は、その後いかがお過ごしになられているのでしょうか?大変気になるところです。和尚的には時間が経過すればするほど個展開催中の色々な感動が思い出されてきます。忘れないうちに書き留めておきましょう。ブログを読んでくださっている多くの皆様にとってはちょっとつまらないかも知れませんが、暫らくお付き合いくださいね。
10月19日、日曜日。時差が日本より13時間遅れていますので、成田空港出発と同じ日の同時刻にニューヨークに着いたわけですが、この日程を組んでくださったグリフィス教授に感謝したいと思います。と言いますのは、日曜日は空港もハイウェイも空いていて実にスムーズにホテルへと向かう事が出来たことです。グリフィス教授の話によりますと、平日は空港もハイウェイも混雑して時間のロスが大きいとか。また時差ボケを出来る限り防ぐためにフライトの時間を工夫したとか。なるほどホテルに着いたのが夕刻の6時頃でしたからすぐに食事をして床に就くことが出来ました。ホテルも長期滞在型の、写真の如くとてもおしゃれな雰囲気のお部屋でした。
このホテルもグリフィス教授がいろいろ探して実際に視察してから予約して下さったわけで、サラ・ローレンス大学にも近く本当に便利な場所に有りました。そうそう言い忘れましたが、ホテルに着いた時もさることながら空港からホテルまでの間の車中はロングフライトにもめげず大変賑やかだったとか。お写真の如くで納得!でした。
撮影:斎藤公一氏
ホテルの近くのファミリーレストランでまずは全員揃っての夕食会、まずはガンバローの乾杯でした。誰もが笑顔でまずは無事に到着。めでたしめでたし!きっとその後は爆睡だったと想像します。つづく
気温も少し上がり、凌ぎ易い朝を迎えました。今日は11時より野町・少林寺で小原家の満中陰忌の法要を修業し、午後からは伊藤家の祥月命日のお参りに行きましたが、相変わらず時差ボケ症候群が続き体調も不十分といった感じの日曜日となりました。無理もないことで、帰国してすぐの日々法務に追われての毎日ですから、明日からは少しずつですが体調復帰を心がけたいと思っています。まだ周りの方々とは帰国の挨拶もままならず申し訳なく感じています。取り急ぎブログでご報告かたがた帰国のご挨拶と致します。
昨日に引き続き、小松空港にて 手荷物検査を通過後も見送って下さった皆様
笑顔で手を振る野口先生
小松空港を出発。羽田空港着、成田空港からジョン・エフ・ケネディ空港へ
行きは良い良い帰りは怖いではありませんが、出国の際の飛行機内は比較的空いていて、きわめてラッキーだったのは和尚の席は4人席のところ家内と二人きりだったため、座席のひじ掛けをたたんで真っ直ぐ仰向けになれるという按配で、いわばファーストクラス的といったところでしょうか。約13時間のフライトですから本当に助かりました。準備の疲れもあって4時間ばかりは眠りの中にあったせいか、午後の4時25分にニューヨーク・ケネディ空港に着いた時は比較的に体も楽で疲れずに済みました。和尚は身体が大きいし、体重もあるので、エコノミークラスはさすがにきつく途中何度も体操をして体のこわばりを防ぎながらのフライトとなりました。空港到着後、ようやく皆さんと顔を合わすことが出来ましたが、誰もが笑顔で元気に入国できたことをまずは感謝しました。空港にはグリフィス教授と仁さんが迎えに来てくれており、サラ・ローレンス大学の大型専用車2台と仁さんの自家用車で一路ホテルへと向かいました。和尚にとっては40年ぶりのアメリカ・ニューヨーク訪問となりました。何もかもが新鮮でした。

車窓からの景色、ハイウェイ走行、そして何よりも迎えに来た車のでかいのにまずは驚いたものです。アメリカはやはりでかかった!久しぶりに思い出した第一番目の入国後の感想でした。つづく
ニューヨーク、サラ・ローレンス大学での個展を終了し、2週間余りを経過しました。ここにきて漸く、当時の色々な出来事を思い出しながら振り返っています。まず出発時の小松空港でのサプライズが待っていました。野口社中の留守番組の皆様が大勢来ておられ、しかも御手製プラカードを持参しての見送りには全くに予期しない出来事で大変感動したものです。
小松空港にはタクシーで到着したため皆様が待ち構えていたところとは別な場所に降り、全く気付かずに空港ロビーに入ったところ、野口社中の参加者の方から正面玄関に行くよう促され、妻とのんびりと向かったところいきなりの社中皆さまの送迎ムードに驚きました。ひっそりとした出発を思っていただけに、感激もひとしおでした。今から振り返っても本当に嬉しい出発時の出来事でした。あらためて皆さんに感謝申し上げます。
社中の皆様とは帰国後まだお会いしていませんが、きっと皆様も一緒に参加したかったであろうと思いますと一層その有難みが伝わってきます。何事も初めと終わりが肝心と言います。何とも素晴らしい旅立ちを演出して下さった野口社中の皆様の声援に応えて、何としても成功させたいと願ったものです。ところで新命和尚も毎月の家族動物供養の席で参列の皆様に挨拶をして、「住職は今日、無事に旅立たれました。」と言ったところ、妙な歓声が上がり「和尚さんがお亡くなりになったんですか?」と聞かれたとか。なるほど、日本語の使い方は難しいですね。色々なところでハプニングが起こりますね。飛行機の中からも見送り下さった皆様の黄色い歓声が届いてくるような錯覚さえ起こすほど、手を大きく振って下さってのお見送り、和尚も参加した者も生涯忘れる事の出来ない感動の風景となりました。これできっと全ての催事も必ず成功すると大きな自信となりました。つづく