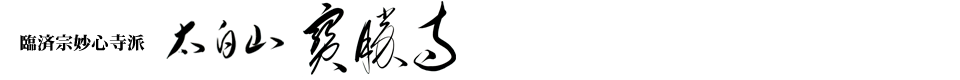和尚のちょっといい話
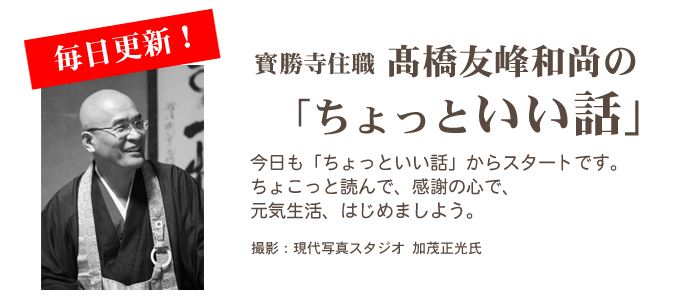 |
まさにお手上げ状態の豪雪となっています。ニュースでは福井・金沢の大雪状況が全国に伝えられるほど、昭和56年以来の久しぶりの降雪で、法務は一旦中止して早朝より除雪に追われました。金沢兼務4ヶ寺院での屋根雪が軒につかえるほどの状態で、このままでは建物に被害が生じる恐れが出て来ました。
 寳勝寺 中庭の雪
寳勝寺 中庭の雪

屋根雪が落ち 小高い山になっています
天気予報では明後日頃まで大雪が続くとかで、本当に心配されます。立春到来を喜んだ矢先の「立春寒波」襲来で、「平昌オリンピック開幕」もソッチのけで除雪に日夜奮闘しています。午前中には少林寺お檀家様の月参りがあり寺を出発したものの、何処も彼処も雪の山で交通事故も多発しており車の運転には十分気を付けて頂きたいものですね。
㈱ココ・プランニング川面専務との打ち合わせ

さて、夕刻からは節分会で鬼やらいに用いた「福豆」を頂きながら寺務の整理をしました。これまでに頂いたお手紙や御葉書をじっくりと読み返しながら少しずつお返事しようと思っていますが、どの文章も心のこもったものばかりで有り難く思います。電子機器の発達で意思の疎通も短い文章や絵文字で済ませる事が多くなりつつある今日、お手紙や御葉書の文章には一味も二味も違った相手様の思いを感じるものです。大雪が図らずも時間と心の余裕を与えてくれた一日となったようです。友峰和尚より


朝日が雪面を照らし、春の到来を告げるかのように立春を迎えました! 昨晩は約400名近い地元の方々で堂内が埋め尽くされ、節分会と鬼やらいに引き続き福引大会が盛大に行われ、子供達の元気にはしゃぐ姿を嬉しく見守ったものでした。

平成三十年度 「節分会」 御祈祷のようす / 大安禅寺 本堂にて

北陸地方の長い長い雪の季節から心を解放するため始めた「節分会大祭」も今年で40年になろうとしています。最初は100人足らずの参加者でしたが、今では多くの善男善女方々が御来寺下さって福引大会も盛大なものと成っています。お寺との御縁のある多くの企業の方々からも福引景品を贈呈下さり本当に感謝の言葉も有りません。心から厚く御礼申し上げます。少子化の進む地元各町内に有って、少しでもお寺と子供達との法縁を結んで頂く為の行事でも有り、今後も継続できればと願っています。鬼やらいの前には地元劇団の「紙芝居」が上演され、「お互いの和合の大切さ」を子供達に諭していました。

紙芝居の上映

鬼やらいにて

福豆まき と 大福引退会 / 枯木堂にて



昔のお寺では日曜学校行われ子供達が大勢参加していましたが、近年の少子化に伴い、お寺と子供達の繋がりも少なくなって来ています。仏教がクローズアップされる今の社会の中で、子供がお寺に自由に出入りできる環境を提供する事も、布教活動の重要な課題となって来ているようです。さて立春を無事に迎える事が出来、和尚も気分一新!大いに若返りを図りながら新芽を吹いていきたいと念じております。友峰和尚より

今朝のようす 茶礼での孫たちとのひととき


 瑞源寺様とともに 当日お申込みの方の御祈願札を書いているところ
瑞源寺様とともに 当日お申込みの方の御祈願札を書いているところ
明日の立春を前に夕方六時より「節分会祈祷祭」が行われますが、今日は午前中から職員始め多くの世話役御婦人方々がその準備に余念が有りませんでした。一つの行事を無事円成するためには裏方さんの働きが欠かせません。裏方こそ本当の意味での主役なのかも知れませんね。どうやら心配された降雪と道路の凍結は免れたようで、無事に御祈祷祭を開催出来そうです。節分会の様子は明日のブログでお知らせする事とします。

荒木芳栄さんとともに
 2019年4月に予定されているサンリスの作品展に向けて パンフレット用の写真を撮影
2019年4月に予定されているサンリスの作品展に向けて パンフレット用の写真を撮影
本日はフランス・パリから一時帰国した画伯の荒木芳栄さんが挨拶に来寺されたのに引き続き、㈱エフワイ運輸・岡島和憲会長様、松浦建設㈱・吉田専務様が節分会祈祷札を受け取りに来られ、しばしのよもやま談議となりました。

㈱エフワイ運輸・岡島和憲会長様とともに

松浦建設㈱・吉田専務様と 社員の方とともに
昔の暦では今日が大晦日、除夜の鐘ならぬ鬼やらいの行事が午後七時より開催されますが、今年は土曜日ということも有って多くの参拝者で賑わう事と思います。除夜の鐘が「自己の108の煩悩消除」ならば、鬼やらいは「悪霊払い」となりましょうか? 「鬼は外! 福は内!」とは古来よりの豆まきの掛け声乍ら、外に追い出された鬼だらけの社会も困ったものです。大安禅寺では、「福は内! 福は内!」と福豆を撒きますからご安心下さい。御参拝頂いた皆様の身体健全とご多幸を心よりご祈祷申し上げたく思います。友峰和尚より

 大安禅寺 旧参道から鐘楼を臨む
大安禅寺 旧参道から鐘楼を臨む
臨済宗の祖・臨済義玄禅師は中国唐代末期(9世紀)の人です。弟子の三聖慧然(さんしょうえねん)が師匠の行状を語録にまとめた「臨済録(りんざいろく)」を常々読んでいますが、その中の禅問答の一つに、「大悲千手眼 那箇(なこ)か是れ正眼 速やかに道(い)え、速やかに道(い)え」と有ります。
雪深い渓谷の中に 延々と続く けものみち
京都東山の三十三間堂を参拝しますと、千の手・千の眼を持った観世音菩薩がずらりと並んで安置されています。「お前さん、その千手千眼観世音菩薩の、どの手が本物だ! どの眼が本物だ! 速やかに答えてみろ!」というわけです。さて皆さんはどのように答えますか?

イノシシの足跡

種田山頭火の句に「指五本ある 嬉しいな」と有りますように、一生涯の内にどれだけ自分の「手」を活かし「眼」を活かして来たかと問われれば自省の念でいっぱいになり、加齢と共におぼつかなくなる身体にジレンマさえ覚える今日この頃です。明日は節分会、夕刻より鬼やらい行事が開催されますが、「懈怠心(なまけごころ)」をことごとく粉砕して千手千眼観世音菩薩の神髄に迫ってみたいと思っています。


さて、今日も終日融雪作業に時間を労しましたが、境内を見渡せば春到来の足音があちこちから聞こえて来るようです。春よ来い~早く来い~友峰和尚より



大安禅寺にて 境内の融雪作業

2月3日の節分会を前にして参道と庫裡前庭の融雪作業をし、午後からはご祈祷御札書きに引き続き福引大会スポンサー名札書きなどをしました。節分明けの北陸地方は再び大雪になるとのこと、まだまだ油断は禁物です。しかも氷点下の日々が続く予報で、水道凍結などを防ぐ工夫も強いられています。

アトリエにて 節分会の掲示物を準備
大安禅寺に戻ると山中のアトリエで過ごす時間が多くなりますが、木々はすっかり春めいて来たようです。今日は職員が、日頃御法縁を頂いている関係各社の皆様に立春大吉の御祈祷札と福豆をお届けしています。夕刻になって藤田通麿総代様が来寺され、思いもかけぬ和尚の古稀祝いの言葉と共に記念品を頂きました。心のこもったお手紙が一番のサプライズでした。






皆様から頂いた温かい励ましの言葉を心に留め、頑張っていこうと気持ちを奮い立たせています。本日は藤田総代様の兄弟子を思わせるような真心に接し、心より感謝と御礼を申し上げます。有り難うございました。友峰和尚より

大安禅寺 中庭の風景 / 平成30年1月30日撮影
この時期、毎日のニュースが雪の話題になるのも北陸特有の現象で無理からぬことです。降雪の大小が日常生活に大きく影響するだけに、天気予報とのにらめっこが続いていきます。今日は気温も緩み朝から雨混じりの雪模様となりましたが、どうやら少しずつ春が近づいている気配を感じます。1月も今日が最終日で愈々明日から2月「如月(きさらぎ)」を迎え、3日の節分会には盛大に鬼やらいの行事が挙行されます。

新命副住職による スポンサー各企業様の商売繁盛ご祈祷 が修行されました
古来よりこの時期、何が故に「鬼やらい」の儀式を行うのか調べてみましたところ、諸説ありますが旧暦では2月3日が大晦日で、除夜の鐘を撞くのと同じく邪気を払う行事として追儺の「豆まき」が始まったと有ります。翌日の4日が立春で、本来の新年を迎える事となります。卑山でも昔は2月に新年の行事を遂行していたように思います。

祈祷太鼓を打ち鳴らし 商売繁盛招福除災の御祈願をします
さて寺では3日の夕刻より修行される節分大祈祷祭、鬼やらい、福引大会の準備が副住職と職員によって行われていました。年々福引景品をご提供下さるスポンサーの方が増え、豪華な景品が盛りだくさんに用意されていますので、是非ご参加下さいますようお待ち申し上げております。「当たるも八卦、当たらぬも八卦」と意味は異なれど、一喜一憂せず「悪鬼を払う」ことを目的とした福引大会に大いに挑戦してみて下さい。
 一昨年の 節分会福引大会のようす
一昨年の 節分会福引大会のようす

福引大賞を得る為に無欲で臨むか、それとも集中力で臨むかはあなた次第です! 和尚は明日から個別厄除け御祈祷を実施しますが、本年が前厄、本厄、後厄に該当する方は是非お申し込みください。渾身の法力で除災祈祷に臨みたいと念じています。友峰和尚より



易経に「幾を見るは其れ神」(きをみるはそれしん)と有り、その意味は「物事には予兆があり、身の回りに起きる出来事を見て未来を予知する」事で、多くの方々がこれまでになんらかの経験をされていることと思います。俗に言う「虫の知らせ」等もそれを表す言葉だと思うのですが、如何に「機を見るに敏なり」と今起きている出来事を注意深くつぶさに鑑みて、それに対応する策を講じなければなりません。

大安禅寺 本堂前の老松倒木 平成30年 1月中旬
昨年、重要文化財の大安禅寺山門横塀が突然倒壊したことに端を発し、今年に入ってからは本堂前の樹齢約二百年の松の大木が雪の重みで倒木、また宝蔵館の展示室では大ガラスに大きなひびが入るという立て続けの出来事に、流石の和尚もこれら一連の出来事が偶然とは思えず未来の予兆を探る思案の日々を過ごしています。そうこうする内にも今度は給水用のポンプが凍結して断水状態となる始末。これらの共通点はと言えばいづれも「老朽化」が考えられ、宝蔵館の展示用ガラスのひび割れも築後約三百年の宝蔵館の老朽化が原因で、今回の大雪の重みに耐えられず起きたものと結論づけました。

松井建設㈱ 田中営業部長 と 営業部 吉川氏とともに
来年度より大安禅寺重要文化財建造物の本格的な全面修復工事が文化庁指導のもと始められようとしていますが、これまで耐えに耐えながら四百年に渡って大安禅寺を支えて来た全てのもの達が一気に「タガを緩めた」と言うのでしょうか? それとも「一刻も早く修復して欲しい」という叫びなのでしょうか? 和尚も既に70歳の古稀を迎え、もはや日々のメンテナンスは欠かせない状態です。卑山の全ての建物が悲鳴を上げている状況下の中で、只管自問自答の毎日が続いています。今日は火曜日で休寺日でしたが、松井建設㈱の田中営業部長が部下の方と来寺くださいました。これ幸いと和尚の深い悩みをしっかり聞いてもらいました。どうか神様!和尚自身の補修も宜しくお願い申し上げます。友峰和尚より

寳勝寺 境内のようす
今日はようやく気温も緩み日々融雪に時間を労した甲斐有って、積もりに積もった屋根雪もすっかり無くなり次の降雪に備えています。なにしろここ数日はマイナス気温が続いて除雪をするにもスコップの歯が立たずあきらめ状態、しかしながら昨晩から雨模様となった為、今がチャンスと雪割りをしました。

ふれあいパーク霊苑にて
午後からは兼務寺院・瑞光寺の視察に行きましたが、金沢市内の路地裏は今でも除雪がなされておらず圧雪された雪がそのままでした。今日から通称忍者寺(妙立寺)が休寺となったため人通りも無く、卑山も臨時休寺日としました。大安禅寺では2月3日夜7時より節分会が修行される予定で、和尚もそれに合わせて帰山しますが、皆様の御参加を是非お待ち申し上げております。


夕刻から厄除祈祷が行われますので、本年が前厄・本厄・後厄を迎えられる御方はご祈祷会の参加を臨むものです。道語に「心こそ 心迷わす心なれ 心に心 心許すな」と有りますが、言い換えれば「心こそ 心悟れる心なり 心に心 こころ悟れよ」とも言えます。ご祈祷の神髄は「無心の心を悟る」ところに有り、仏法の教義に於ける「中道」を悟る事でも有ります。僧侶が読誦する真言陀羅尼の法力を以って厄払いと成ります。2月1日より2日間に渡り個別の厄除祈祷が行われる予定となっています。さてさて「福は内!鬼は外!」いったい福とは何ぞや? 鬼とは何ぞや? 皆さん、お分かりでしょうか?「恐ろしき 地獄の底の 鬼とても おのが吹き出す ものと知らずや!」クワバラ、クワバラ。友峰和尚より


大相撲初場所は千秋楽を待たずに栃ノ心の優勝が決まり、和尚も思わず心から「おめでとう」の言葉を発しました。有終の美とは全くに彼のことであろうと思いました。どのような世界にでも言えるのは、「決してあきらめない」という事だと思います。あきらめずに努力を続けていると必ず幸運の機が訪れるのだと確信するものです。振り返れば白鵬、稀勢の里の両横綱が中途休場となり、鶴竜が終盤に4連敗するなど誰一人として知る由も無いわけで、このような現象が即ち栃ノ心の不退転の努力から来る「引き」だと思います。また母国ジョージアの妻と出産間もない子供が大きな力になったと有りますから、このことも幸運を引き込む原動力となったのは十分に察するところです。モンゴル人力士が何かと揶揄される中での外国人力士・栃ノ心の優勝は、相撲ファン日本国民に多くの問題提起をしたとも言えます。栃ノ心から発せられるインタビューの言葉は、貴乃花親方が言う「日本古来の伝統的相撲道の神髄」を語っているように思えたものでした。今回は日本人力士もよく奮闘しており、色々な相撲界に於ける不祥事事件解決の糸口と方向性を示した大相撲初場所だったと思います。

須貝総代様の御自宅にて 御仏壇での諷経

さて、昨晩は寳勝寺総代・須貝外喜夫様ご夫妻の御招きにより御法要後の夕食を馳走になりましたが、ここでもサプライズ!で和尚の古稀祝いをしてくださいました。御母堂様七回忌法要を厳修後、ご自宅での諷経に引き続いての御斎(おとき)の席での古稀祝い、きっと和尚の亡き母も古稀誕生日を喜んでくれているものと静かに合掌しました。
 御斎の席にて
御斎の席にて


須貝総代様ご夫妻には心から感謝申し上げます。御母堂様の御霊の安らかならんことを慎んでお祈り申し上げます。友峰和尚より
ますます大相撲初場所が面白くなって来ました! 真剣勝負ほど見応えのあるものは有りませんね。現場で観戦するのが一番でしょうが、テレビ画面からも十分に力士の真剣な戦いぶりが伝わってきます。さて今日は法務に専心する一日となりました。午後からは寳勝寺総代・須貝家の年忌法要が本堂で営まれ、引き続き須貝家にお伺いしてお仏壇での御供養となりました。

須貝家 御先祖年忌供養修行 / 寳勝寺本堂にて


昨日もNHKのクローズアップ現代で「墓じまい」の特集が放映され、ここに来て先祖供養の形が急激に変化していくようです。少子高齢化社会が生む様々な問題は遂に死後の世界にまで及んでいます。いつの時代に有っても忘れてはならないのは父母の恩、先祖の恩であるとしみじみ思う今日この頃です。色々な分野で新たな価値観が生まれる現代社会、「慈恩」の心だけは保ち続けたいものです。友峰和尚より
 「心 清ければ 道 自ずから閑かなり」 友峰 書
「心 清ければ 道 自ずから閑かなり」 友峰 書