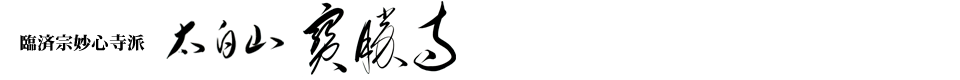和尚のちょっといい話
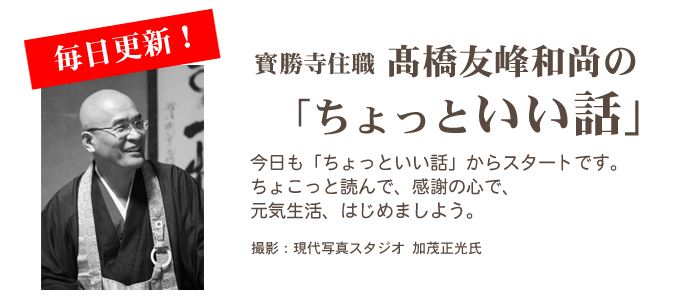 |

三重教区住職研修会 御寺院様が来寺されました
臨済宗妙心寺派・三重教区住職研修会が午前9時半より寳勝寺本堂を会場に開催されました。総茶礼をした後、最初に龍源寺三重教区宗務所長の開会の挨拶が有り、第一講として「寺院復興の工夫と実践」をテーマに約1時間に渡ってお話しさせて頂きました。昨晩は宗務所長よりお招きいただき、各御寺院皆様と夕食を共にしながら懇親の場を持つことが出来た事に感謝申し上げました。そのお蔭で本日は親しみを持ってお話しすることが出来ました。

喫茶室にて 到着茶礼のようす

三重教区役職のご住職様と

開会の前に 般若心経をお唱えしているところ

龍源寺三重教区宗務所長様の開会挨拶
 第一講として「寺院復興の工夫と実践」の講義
第一講として「寺院復興の工夫と実践」の講義


講義終了後は本堂前にて記念写真撮影をし、その後「ふれあいパーク霊苑」と野町・少林寺を会場に開催されている「東アジア2018文化都市展覧会」の視察をして頂きました。

講義に引き続き、ふれあいパーク霊苑を視察されました

合祀墓「 宙 (そら)」にて

奥の院 顕彰碑や檀信徒各家先祖代々の供養石板などを視察


皆様からの御質問などにお答えしているところ

記念撮影

寺町寺院群を見学しながら、少林寺まで徒歩で移動されました

少林寺にて




お参り後、「東アジア2018文化都市展覧会」 宋冬氏の作品を鑑賞されました

先般の滋賀北陸教区住職研修会に引き続いての2度目の視察研修会でしたが、和尚にとっては各御住職皆様に少しでも寺院復興の参考にして頂けたらと願っています。また西茶屋街まで足を延ばし金沢市内の歴史的建造物群を見て頂き、少々時間オーバー気味となりましたが、11時半には無事に研修を終えることが出来ました。

寺院運営の理想的有り方については日々思案していますが、徐々にその形が見え始めてきた感のある今日この頃です。為せば成る 為さねば成らぬ 何事も…、上杉鷹山の言葉を肝に命じて努力の日々が続いていきます。本当に遠くから御来寺頂き、三重教区御住職の皆様には深く感謝申し上げます。有り難うございました。友峰和尚より

御来寺賜り、厚く御礼申し上げます

今朝 石川県観光連盟 の 新井様と
気温が上がったり下がったりで高齢者の皆様には体調管理が難しいこの頃ですが、皆様如何お過ごしでしょうか? このところ、和尚の行程は福井-京都-金沢間を行ったり来たりでどうも落ち着きません。明日は臨済宗妙心寺派 三重教区住職研修会 が寳勝寺で開催されるためお迎えの準備をしましたが、今回の視察は滋賀北陸教区に続き、寳勝寺視察を兼ねた2回目の「住職研修会」となります。もはや待ったなしの「宗教に対する価値観の変化」に、各寺院がどのように布教活動を進めていくかが今後の重要な課題となっているようです。

ふれあいパーク霊苑奥の院 の お掃除をしました


今回の参加寺院は24カ寺ですが、その大半が住職ですから出来るだけ現実に添ったお話しをしようと思っています。されど大切な事はやはり寺院間の情報交換ですから、今回のような視察研修旅行を通して大いに住職同士が意見を交換することが一番だと思います。
 福邦銀行金沢支店 義元支店長 と 舟橋君とともに
福邦銀行金沢支店 義元支店長 と 舟橋君とともに
昨日の教区寺庭婦人会研修会の講義の中でも言われていましたが、「無常の世の中だからこそ、一瞬一瞬の御付き合いが重要なのです」と。三重教区の龍源寺宗務所長とは本山研修でよく意見を交わす仲間でも有ります。今回、遠い三重県から訪寺されることに深く感謝申し上げたいと思います。卑山代々墓始め参道脇の草引きとお掃除をして、住職皆様方を心からお迎えしたいと思います。三重教区住職研修会御寺院様!熱烈歓迎!!です。友峰和尚より
 「清風 萬里の秋」 渓仙書
「清風 萬里の秋」 渓仙書

「滋賀北陸教区寺庭婦人会総会並びに研修会」
実に爽快な京都の朝を迎えることが出来たものです。昨晩は妻と共に一泊し、「滋賀北陸教区寺庭婦人会総会並びに研修会」会場のハトヤ瑞鳳閣ホテルまで歩いて向かいました。午前11時より、教区教化主事 無量寺住職の開会挨拶の後、教区寺庭婦人会会長で大徳寺寺庭 藤田かおり様の日程報告があり、宗務所長挨拶後は本山派遣講師、傳宗寺(愛媛県)住職 多田曹渓師による講義が約一時間に渡って行われました。

本日の参加は13名の寺庭ご婦人でしたが、熱心にメモを取りながら拝聴されていました。講義のテーマは「信心の言葉」で、講師様の御子息お二人が野球部に属しておられ、その子育て過程を通してわかり易く信心のお話をされていました。普段より子育てをしながら住職を補佐し、寺院と檀信徒との間を取り持っておられる寺庭ご婦人方々には何かと苦労が多き事と察します。心から感謝申し上げる次第です。

午後からは総会が開かれ、終了後は臨済宗東福寺派、大本山東福寺を拝観され散会となりました。和尚は金沢での法務遂行のため途中で帰寺しましたが、本日の傳宗寺講師様のお話は大変聴き易く勉強になりました。また、寺庭ご婦人方々との交流も大切であると感じました。普段はなかなかお話しする機会も無いだけに、今後は寺庭間の交流の場を増やしていきたいと願ったものです。友峰和尚より
「形見とて 何か残さん 春は花 夏ホトトギス 秋はもみじ葉」とはあの有名な良寛和尚の辞世の和歌です。この歌は永平寺開山・道元禅師の和歌「春は花 夏ホトトギス 秋は月 冬雪冴えて 涼しかりけり」を参考にしたものと思われますが、この時期の京都嵯峨野の紅葉は見事です!明日の午前11時より京都市・ハトヤ瑞鳳閣を会場に、愛媛県・傳宗寺住職 多田曹溪師を講師にお迎えして「滋賀北陸教区寺庭婦人会総会並びに研修会」が開催されます。和尚は教区宗務所長として出席する為、本日午後より妻と共に京都に向かいました。

大本山 東福寺の紅葉 (画像は大本山東福寺様の頁よりお借りしました)
研修終了後は大本山 東福寺を拝観する予定になっていますが、紅葉の名所として近年大人気となっており、特に外国人観光客の京都観光目玉スポットとして人気を博しているそうです。京都は紅葉の時期としては少々早いとのことですが、京都盆地特有の冷え込みから清水寺を始めとする有名観光地の紅葉はまさに絶景かな!絶景かな!の風景を見せてくれます。学生時代は仁和寺裏山に登り紅葉を楽しんだものでした。形見など何も残さなくても、自然の有るがままの景色ほど素晴らしいものは有りません。紅葉の季節です、大いに観賞したいものですね。友峰和尚より

紅葉 秋風に舞う 渓仙 書

ふれあいパーク霊苑一周年香語
昨日は快晴のお天気のなか「ふれあいパーク霊苑一周年記念法要」を関係者御出席のもと無事に円成出来、感謝致しました。本日も引き続き晴れ渡った好天気となり、霊苑も一段と輝いているように思えたものでした。
 昨日の 一周年記念法要より
昨日の 一周年記念法要より

午後には卑山総代の北條英俊様、須貝外喜夫様ご夫妻が御来寺されしばし歓談しましたが、須貝様がお土産に持参下さった金沢漁港の新鮮なお魚をご夫妻で調理して下さり本当に有難うございました。10月もあっという間に終盤を迎え、そろそろこの一年を振り返りつつ来年の法務計画を立てる時期に来ています。来年は重要文化財・大安禅寺の諸堂修復工事が始まるため、年中行事の遂行を含め綿密な計画が求められています。全国の八百万の神様も現在出雲にお集まりになり、来年の神事計画を立てておられますが、まもなく地方へとお戻りになられます。神々の御加護のもとに、一年の無事を祈りたいと思います。友峰和尚より
 松井建設㈱ 様 が 御来寺下さいました
松井建設㈱ 様 が 御来寺下さいました

朝の気温が11℃と実に身震いするような寒さとなりましたが、スカッと晴れ渡った秋晴れの良いお天気となりました。本日は「ふれあいパーク霊苑開苑一周年記念法要」が午後一時半より卑山責任役員総代始め霊苑並びに工事関係者が出席されるなか厳修され、引き続き霊苑にて総供養祭が行われました。

 御加担下さった 江雲庵 様 (臨済宗国泰寺派 富山県高岡市)
御加担下さった 江雲庵 様 (臨済宗国泰寺派 富山県高岡市)

宝光寺 様 (臨済宗国泰寺派 富山県氷見市)

寳勝寺檀信徒 並びに ふれあいパーク霊苑縁者 各家先祖代々の御供養




今回は関係者のみでの法要でしたが、来年はもっと盛大に執り行いと思います。この一年間で本当に多くの方々と霊苑の御縁を頂きました。墓じまいや散骨、寺離れに直葬など、これまでに考えもしなかった現象が起きています。終戦後70有余年を経て、第二次世界大戦のあの恐ろしい戦争で亡くなられた戦没者英霊供養も高齢化社会が進むにつれ風化しつつあります。戦後社会の中で、常に英霊の供養を通して不戦を誓ってきた人々の精神が薄れつつあるようです。
 宝勝寺ふれあいパーク霊苑 奥の院 三界萬霊塔御真前での御供養
宝勝寺ふれあいパーク霊苑 奥の院 三界萬霊塔御真前での御供養


宝勝寺ふれあいパーク霊苑 合祀墓「 宙(そら)」 御真前での御供養

人間にとって最も大切なことは、先祖の恩・父母の恩を忘れない中に「生きる」という意義を見出すことが出来ます。人々の心は「かたち」に寄り添うだけに、祖先の御霊を形にして報恩の気持ちを捧げていきたいと思うものです。友峰和尚より


明日は卑山「ふれあいパーク霊苑」が開苑して一周年を迎えます。本日も午前中に墓碑開眼納骨供養が修業され、未来霊苑としての理解を深め市民の皆様に次第に浸透して来たように思います。何と言っても一年中色々なお花に囲まれるのは本当に嬉しい事だと思います。特に5月には幾種類もの薔薇の花が咲き乱れ、苑内が一辺に華やかさを増し極楽浄土そのものですね。薔薇だけでは有りませんよ、日本古来の草花も沢山咲きますからとても素敵な匂いに包まれ、心も和みます。黄泉(よみ)の世界は暗く冷たいものではなく、明るく美しく楽しい世界であって欲しいものです。
 お檀家様の 墳墓開眼納骨法要 / 奥の院にて
お檀家様の 墳墓開眼納骨法要 / 奥の院にて


新たに御縁を頂いた御家族様の 墳墓開眼納骨法要にて

御親族皆様お揃いで お参りくださいました


さて、明日は開苑一周年記念法要が関係者のみで厳修されますが、本日の午後はその準備に入りました。幕を張りながら昨年の落慶法要を思い出していました。季節外れの大型台風が接近するギリギリの状況で、大安禅寺御詠歌婦人部の方々が奉詠する中での稚児行列並びに落慶法要を無事に円成し安堵したものでした。あれから一年が過ぎました。明日は感謝の気持ちを込めて一周年記念法要に臨みたいと思っています。友峰和尚より


10月度 寳勝寺木曜坐禅会
昨晩は月例の木曜坐禅会が開催され、5名の居士大姉が参加されました。この時期の坐禅は実に気持ちが落ち着き、坐禅後の和合の茶礼も楽しいものでした。皆様もいちど坐禅体験してみませんか?きっと世界が変わりますよ!



茶礼にて 和合のひととき

桂岩寺様 と 法要の打ち合わせ

さて一夜明けて、今日は地元マドンナの皆様が御来寺下さり、「楽く楽く法話」を致しました。先般、管理部の小村様、中川様より依頼を受けたPFUテクノコンサル株式会社 社員皆様の「オフサイトミーティング」が寳勝寺を会場に開催されたわけですが、日頃はコンピュータに関わるデスクワークの仕事の為、本日は「人と人との結びつきを強める為の自己改革」というテーマでの開催だったようです。

とっても生き生きとした女性の皆様でしたので、ついついお話の時間を超過してしまいました! 女性の活躍が期待されている現代社会ですから、大いに頑張って頂きたいと願っています。「気力・体力・決断力」この三つの力を「魅力」と言う!との和尚の持論ながら、今日のお客様はまさに魅了を具えたマドンナの皆様でした。また是非ご来寺下さい。心よりお待ち申し上げております。友峰和尚より
 御来寺頂き、誠にありがとうございました
御来寺頂き、誠にありがとうございました

秋季定期宗務所長会を無事に終え、昨晩は自坊でゆっくり静養しました。夕食時には副住職が孫達を引き連れて会いに来てくれましたが、しばらく会わないうちにどんどん成長していく姿には驚きます。和尚の自室にはいまだに副住職の子供の頃の写真が飾ってあるのに、そこに孫達が合流すると実に隔世の感を覚えるものです。人生って本当に短いもんですね!

今日は寶勝寺で月例の木曜坐禅会が開かれるため午前中に金沢へ移動しました。その際、孫の永峰が見送りに来てくれたので写真を撮ろうとした所こっちを向いてくれず、別れの寂しさからか少々拗ね気味の行動がとても愛らしく何気ない素振りの中にも心の成長が伺えたものです。

さて、夕刻より坐禅会です。「心身一如」の静かなひと時でも有ります。人生には常にタイミングがあるようですね。動あり静ありの中で、心安らかに有りたいと願うばかりです。友峰和尚より

この時期としては汗ばむ気候となった京都ですが、盆地の影響からか早朝は爽やかそのもので、妙心寺開山堂拝塔諷経の際には堂内を冷んやりした秋風が吹き抜けて行きました。先般の台風では山内(さんない)のあちこちで建物被害を受けたそうで、開山堂も修復工事が行われていました。




拝塔後には小方丈で 小倉宗俊管長猊下 ご出席のもと総茶礼が行われ、引き続き微妙殿にて供養諷経があり、管長猊下のご垂訓のあと記念撮影となりました。

会議は午前9時半より宗務本所会議場で開催され 熱心な討議がなされたわけですが、長時間に渡る議事審議は和尚の持病 椎間板ヘルニアには最悪の状況です。日々の運動不足が歪めない最近の生活リズムに反省しきりでした。健康の秋!ですから、率先して体操運動を心掛けなければなりませんね。少しの運動でも随分と身体の筋肉がほぐれるものです。


各県では高齢者向けの健康体操を奨励して、寝たきりにならないよう実践指導されているそうですから、なんだか納得してしまいます。自分が高齢者で有るという自覚が足らないところにも問題が有るようです。さてさて、定期宗務所長会議も無事に終了し、ちょっと一服致しましょう! 友峰和尚より