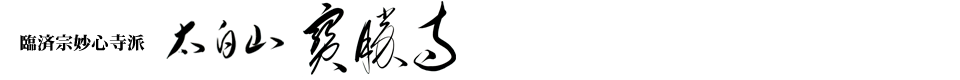和尚のちょっといい話
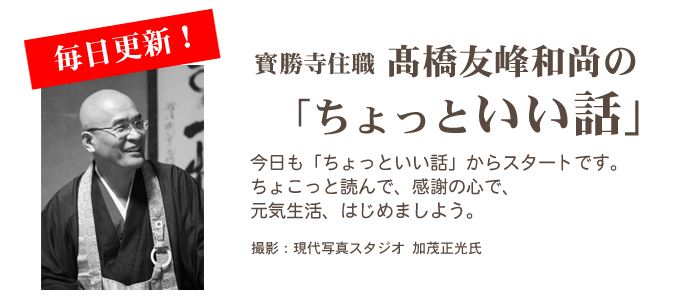 |
 式台復元工事視察 / 金沢市・歴史建造物整備課 新保さまとともに
式台復元工事視察 / 金沢市・歴史建造物整備課 新保さまとともに
昨年はこの時期、金沢市「しいのき迎賓館」で和尚の墨蹟禅画展が開催されていましたが、あれから一年を過ぎた今、新幹線開業を目前に控えて金沢市全体が盛り上がりを見せています。刻々と変化を見せて行く人間社会において、新幹線の開通は尚一層その度合いを早めて行くようです。寶勝寺も本堂の全面修復工事を終え、新幹線開通に歩調を合わせるかのように寺カフェ並びに法務の再出発の準備に入っています。この14日が開業日ですが、東京まで2時間半、北陸に住む人々にとっては日帰りも可能な乗車時間ということで実に魅力的な乗り物となりました。和尚もこれから法務の合間を見ては東京に行ってみたいと楽しみにしています。
復元された正面の引き戸を確認されているところ
土間の洗い出しのようす
今日は式台(玄関)の最後の仕上げの工事に立ち会いましたが、これで全ての工事が終了となりました。桜の季節を前に、寺カフェのお客様も日々増加しつつあります。間もなく和尚の法話も始まりますが、ブログをご覧の皆様も修復工事を終えた寶勝寺に是非ご来寺くださいますよう心よりお待ち申し上げております。
明日からは京都・大本山妙心寺での「全国宗務所長会」に出席致しますが、愈々来月新年度を迎えるにあたり、俄かに慌ただしさを見せ始めた宗教界のようです。「一期一会」の人生です、全力で法務に専心して参りたいと思います。友峰和尚より
床の間の掛軸が替わりました。サラローレンス大学個展開催記念の掛軸です
人間の頭の重さは相当なもので、和尚など長時間にわたって書を書く為に、前かがみ状態での動作となり、首にかかる負荷が大きくなります。生活習慣病の如く常に肩こりが発生するわけですが、人間の体重の12分の1を占めるこの約8キログラム程の頭こそが”自己の運命”を左右する本体であるとすると、いっそう不思議に思うこの頃です。和尚は身長が181センチメートルあるため、布団からはみ出した足の指を無造作に動かしてみる時、布団に隠れた胴体のさらに上の、脳からの指令を受けて動く足指に感動しています。自分の心の指令と連動して働く「脳」の働きこそ、「摩訶不思議」な神秘的世界に他なりませんね。
無心の状態では一切が不動の暗黒世界でありますから、「五感」と「脳」と「無心」とが連動して世界が創造されていくのだと思います。そうなりますと、「脳」の働きを普段から活性化させておく必要に迫られます。一番効果があるのは坐禅で、次が掃除です。「坐禅」と「掃除」、この「静」と「動」の行動が、「脳」を活性化させていくと和尚は思いますね。最近は「認知症患者」に対する色々な対応策が述べられていますが、要は如何に「脳」を退化させないかに懸っています。「人間は考える葦である」とはパスカルの言葉。やはり、人間は最後の最後まで「脳」を使っていくことが大切のようですね。さて皆様はどう思いますか?「イエス」それとも「ノウ!!」 友峰和尚より
朝、5時半起床で小雨模様の中を一路、自家用車で京都府宇治市・萬福寺に向かいました。滋賀北陸教区「花園会役員研修会」が黄檗宗大本山萬福寺で開催された為で、途中、役員3名も乗車して高速道路を走らせました。3時間ほどのドライブで萬福寺に到着。教区の多くの役員皆様とも合流し、早速に団参諷経が「大雄寳殿」にて行われ、山内拝観に引き続いて講話がなされました。
写真の如く、大本山萬福寺は流石に天下の名刹だけあって、多くの伽藍を備えた荘厳な佇まいでした。和尚も学生の頃にいちど訪ねたような記憶が有りましたが、その当時とは随分違った感覚でした。お昼には名物の普茶料理を頂きました。
午後からは塔頭寺院でもあります「宝蔵院」を尋ね、寺に収蔵されている一切経の版木を見学しましたが、三百年前の印刷技術を版木から垣間見た感が有りました。筆舌に尽くしがたい当時の禅僧の仏法伝授の辛苦の跡が偲ばれます。
役員研修会は、普段触れることの出来ない禅寺の奥深い部分を実地見聞する事を主眼としています。今回の研修では、一般参拝者が立ち入ることの出来ない建物の中を拝観することが出来ました。禅の修行を身近に感じる瞬間でもあります。また黄檗宗独特の、本場・中国スタイルでの読経聲明(どっきょうしょうみょう)も拝聴できました。本当に充実した研修の一日、「あなたの知らない世界」がまだまだこの世にある事を知った花園会役員研修会となりました。皆様も是非いちど、宇治市・黄檗山萬福寺をお尋ね頂きたいと思います。友峰和尚より
大安禅寺の境内いっぱいに春の新芽の匂いが立ち込める朝、総代様を伴って副住職が涅槃の托鉢に出発しました。大安寺地区四ヶ村を回って御浄米を頂くわけですが、そのお米で涅槃団子を作ります。幾代にも渡って続けられてきたこの涅槃托鉢。和尚の父親の代からも欠かすことなく毎年行われて来ました。
近年は共働きのお家が多くなり、留守がちの村々を回るわけですが、それでもご高齢の方が不自由な御体をおして勧進くださる姿には本当に感謝の念でいっぱいになります。この21日のお彼岸の日に、涅槃会と共に供養祭が行われ、その際に檀信徒役員の皆様で作られた「五色の涅槃団子」が釈迦涅槃像にお供えされます。連綿として伝えられて来た涅槃托鉢はこれ偏に報恩菩提の修行にほかなりません。
そんななか、岐阜県美濃加茂市・瑞林寺様がご挨拶に来寺くださいました。大安禅寺・隠寮「愈好亭」でのおもてなしでしたが、久しく歓談することが出来ました。「友 遠方より来る また楽しからずや」ですね。ゆったりと時の流れる早春の茶室から望む白山連峰もまた風流でした。いいですね!いいですね!心からのんびりさせて頂いた一日となりました。友峰和尚より
切干大根と法蓮草のおひたし、大根の煮物
昨日は中部7県のお寿司屋さんの集まりでの特別法話をいたしましたが、お寿司のみならず「和食」は実に繊細でかつダイナミックさをも加味備えた食べ物であると思います。繊細という意味では、なんといっても食材の持つ特性を最大限に生かす色々な加工方法と、その盛り付けも徹底的なこだわりを見せるものです。ダイナミックという事では、調理に於いての食材の大胆な使い方や、盛り付ける器の選定などにも目を見張るものが有ります。
さて、一宮市にお住まいの奥村行保様・美奈子様ご夫妻より先日頂きました手作りの切干大根と見事な大根そして法蓮草を使って、早速に料理してみました。大根の煮物と、切干大根のおひたしですが、同じ大根ながらその味は全くに異なります。
奥村様ご夫妻です。
ご主人の手作りの野菜はどれも美味しく、また、奥様が手塩に掛けて作った切干大根には絶妙な味わいが有ります。本当にいつもありがとうございます。最近は和尚も寶勝寺での自炊が多くなってきました。修行時代を思い出しながら、毎日の料理作りを楽しんでいます。
今日は内孫「芭月」の一歳の誕生日。息子嫁が手作りの料理を御馳走してくれるとか。今夜の夕食が待ち遠しいお祝い日でした。友峰和尚より

 |
 |
『「全国すし商生活衛生同業組合連合会」第44回中部ブロック代表者「福井県議会」大会』が、ユアーズホテル(福井市)で開催され、その記念講演として「遊戯三昧 すし三昧」と題し、午後4時より特別法話をいたしました。一昨年の平成25年、和食がユネスコ世界文化遺産に登録されましたが、寿司は今や世界的に有名で、海外の多くの国々でアレンジを加えてのお寿司が人気を博しています。日本はアイデアの国でもあり、最近では回転寿司がメジャーになりつつある現状の中、旧来よりの寿司職人としてのプライドを継続しながら頑張っておられるお寿司屋さんの組合の集まり中部7県から参加された、100名を超える盛大な寿司連合会大会です。
お寿司の歴史は古く奈良時代の文献にすでに登場しているそうですが、そもそも中国では「鮨」としてもっと古くからあったそうですから、日本に輸入されて一躍発展していった形跡が有ります。今の「寿司」という漢字になったのは江戸時代後期からだそうで、めでたい席に出される食品になって行ったところから「寿司」の当て字が使われるようになったそうです。兎に角、お寿司は古来より日本庶民にとっての好物ゆえに、色々な工夫を凝らしながら根強い人気を博しています。和尚もお寿司は大好きですが、高価な食品のイメージがある為、たまに行くしかできませんね。皆様もきっとお寿司は好物であると思います。「酢」飯から来たお寿司、やはり日本人にとって、健康には酢飯が欠かせないようですね。友峰和尚より

「桃の節句」の本日、寺町界隈は此れといったイベントもありませんでしたが、せっかくの雛祭りゆえに和尚の孫たちの健康を祈願し、朝一番に読経しました。「お雛様、数年たってお暇様」では有りませんが、子供達も今では自分の子供を持つ状況にて蔵にしまい込んだおひな飾りが心配されます。いつまでもお雛様を飾っておくと嫁に行けなくなるなんて昔の人は言いましたから、尚更のこと雛人形をしまい込む時間が長くなるという始末。たまには虫干しも兼ねてお飾りしたいと思ったものでした。いずれにせよ「節句」のお祝い日ですから何か楽しい事をしたいと思って居ましたら、有りがたいことに早速、寶勝寺の取材が入り、観光情報誌「金沢女子の旅」に掲載頂けるとのこと。地元のコピーライターで、アヴァンセ株式会社の代表取締役、沖崎松美さまが寺カフェ撮影に来られました。
とても素敵な女性の方で、多くの金沢観光ガイドブック作成に携わっておられるそうです。まさしく幸運の「おひなさま」が来られたと思いました。今後も寶勝寺の取材をお願いしましたところ、快く承諾くださいました。そこで今日、3月3日は「燦燦たる好日」となった次第です。忍者寺近くのなんじゃ寺「寶勝寺」を今後とも皆様、宜しく御ひいきに願いますね。「カチン カチン」 とさ。友峰和尚より
黄砂にPM2.5にスギ花粉にインフルエンザと、本当に息をするのも困難な最近の空気状況。マスクが離せない日々が続いています。お天気は良いのにどんよりと霞がかかったようなお空、本当に心配になりますね。寺カフェが再開されて3日目ですが,順調にお客様が利用されております。和尚のお客様も来られ、どなた様もゆっくりされて寶勝寺の法悦に浸っているようでした。そんななか、今日は、栃木県鹿沼市にお住まいの寳勝寺檀信徒・北條淳子様より、手作りのランチョンマットが送られて来ました。とても素敵なマットです。
北條淳子さまから頂きました、御手製のランチョンマット
有りがたいですね。寺カフェにて使用されている調度品はいずれも御寄進を頂いた物が多く、本当に有り難く感謝しております。基本的に、寺院は縁者のご寄進によって運営されて行きますから、理想的な展開となっています。多くの縁を頂きながらの寶勝寺・寺カフェです。早速に使用させていただきます。お客様の歓談する、楽しい笑い声が聞こえてきますと面目躍如の感が有ります。返すがえすもお寺は市民の憩いの場であって欲しいと願うばかりです。今日は寶勝寺総代の須貝様もお友達を連れて来て下さいました。3月22日にはお彼岸会法要が有りますが、檀信徒の皆様にも修復なったお寺をご披露したいと思っています。
須貝様、同窓生のご友人様とともに
西方寺ご住職様、妙法寺副住職様とともに
 大工師の岩内様が、ご家族と寺カフェへお越し下さいました。/ 3月1日撮影
大工師の岩内様が、ご家族と寺カフェへお越し下さいました。/ 3月1日撮影
妻も毎日、お庭の整備を続けています。まもなく式台(玄関)が完成しますと、春のお花道を通っての堂内入りとなります。どうぞお花の鑑賞も楽しみに御出で下さい。友峰和尚より

今日から三月!春がやって来るのは嬉しいですが、反面、足早に過ぎ去って行く月日には驚きを感じます。三月のことを昔の暦で「弥生」(やよい)と言いますが、その意味は新芽の吹き出るさまを言い「いやおい」から弥生になったとあります。まったくその通りで、この時期いっせいに枝木が新芽を吹いて行きます。時折、新芽の吹く様子を高速度カメラで撮影した映像が放映されますが、実に初々しく、なんとも愛らしく、また微笑ましくさえ感じるものです。
「春は花 夏ホトトギス 秋の紅葉葉(もみじば)」とは、あの有名な良寛和尚の辞世の歌ですが、「人生を振り返ってみれば、自然のありのままが最も心の安らぎを得るときであった」との悟りの境地でもあります。日曜日の寶勝寺、冷たい春雨の中を、金沢観光に訪れた若者達で寺カフェが賑わっていました。春の枝木のみならず若者もまた、新芽を吹くかのように溌剌とした春気を身体いっぱいに、満面の笑みを浮かべて楽しんでいるかのようでした。
 |
 |

「若者っていいですね!」和尚にだって若いときは有りましたよ。若者に負けじと気持ちだけは春風のように、生き生きとして参りたいものですね。さて、この時期の早朝の坐禅もまた格別ですよ。皆様、春の息吹を体全体で感じ取ってみませんか?本当に生きてるって感じです。命の有りがたさを身をもって知る季節のようです。友峰和尚より
底冷えのする好天気の朝を迎えました。いよいよ宝勝寺・寺カフェのスタートとなった土曜日、北條直敬様・仁美様ご夫妻から素晴らしい蘭の花鉢を頂き、堂内が一層華やいだ雰囲気となりました。この一週間は掃除掃除掃除の毎日でしたが、お陰様でどこもかしこもピカピカのお部屋。開業の無事を願って、朝一番にご祈祷致しましたが、晴れ晴れとした爽快な気分の中、お客様が見え始め、久し振りに賑わいを見せました。日頃からお世話になっております福邦銀行にお勤めの中山純一さんも、お休みの日にも関わらずお祝いに来てくださり、お茶席での楽しい歓談となりました。
明日からは本格的な活動に入りますが、本当に多くの方に利用して頂きたいですね。ブログをご覧頂いている皆様も是非ご来寺頂き、早春の古寺でのんびりとお寛ぎ頂きたく願っています。
式台玄関に、仮の扉が設置されました
式台に通じる踏み石
本日、新しい笏谷石が置かれました。
式台の中の踏み石
さて修復工事もひと段落しましたので、此れよりは和尚も法務に専念して行きたいと思います。先ずは3月4日に予定されている、中部7県の寿司組合特別法話から出発です。演題は「遊戯三昧寿司三昧」です。さてさてどんな話になるのやら、「花よりお寿司」で法話の前にお寿司を頂きたく思いますよ。なんたって酸っぱいは成功の元ですからね。すしません! 友峰和尚より