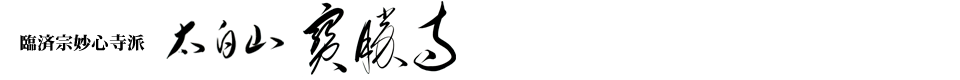和尚のちょっといい話
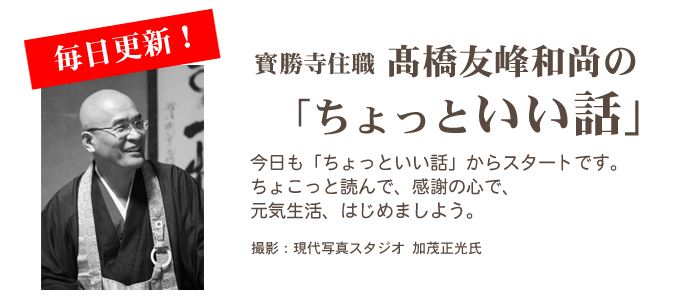 |

寳勝寺境内の雪割り

融雪作業が効いて 車が出入り出来るようになりました
今日もよく晴れ渡った一日となり、山のように積もっていた雪もどんどん融けていきます。ようやく時間的余裕も出来て午後からはピョンチャン冬季オリンピック・フィギュア男子シングルSPを観戦することが出来ました。羽生結弦、宇野昌磨両アスリートの素晴らしい圧巻の演技はここ数日間の除雪の疲れを癒してくれるに十分すぎるくらい感動的なものでした。スポーツ選手の活躍からは少なからず大きなパワーをもらえるものです。

寳勝寺式台玄関 夏椿の芽吹き
今になって身体のあちこちに痛みが走り、これまで除雪に支障なく頑張ってこれた事がウソのようです。「火事場の馬鹿力」という言葉が有りますがまさにそれで、集中力だけでは説明がつかないほど不思議な力を神仏が与えてくれたとか思えません。本当に有り難い事でした。オリンピック競技に於いても、アスリート達に幸運と不運が交錯するのを見るにつけ「心の綾(あや)の不可思議」を感じます。「艱難 汝を玉にす」とは「逆境は人を賢くする」の西洋の諺から来た言葉ですが、この度の北陸地方を襲った驚異的な豪雪に日々耐え抜こうとする国民性が、[大和魂]に通づるものだろうと思います。大安禅寺では福井県・福井市文化課の豪雪被害状況現場視察を受けたそうですが、今後は豪雪にも対応できる復興を目指して行きたいと念じています。友峰和尚より


昨日に引き続き、本日もこれまでがウソのような快晴の一日となり、身も心も放心状態となりました。長い長い除雪漬けの日々から解放され、見る見る融けていく雪を恨めしく感じたものです。昨日は金沢での法務遂行のため寳勝寺に入りましたが、バレンタインデーという事も有って妻が作ってくれたちらし寿司とチョコレートを食べながら本堂前の残雪排除作業をし、次にいつ来るか知れない雪に備えました。午後からは強制的に休息し、皆様から頂いたチョコレートやプレゼントに再び感激しながら温かい心を頂きました。

福井を出発するとき 妻が作ってくれたお寿司

バレンタインデーに頂きました
神様!その、あま~い心で山のように積みあがった雪を一挙に融かしてくださいな。本当に皆様に於かれましても日々の除雪にお疲れになった事と心からお見舞い申し上げます。大変ご苦労様でした! 人生、長く生きていると色んな難事に遭遇するものです。「どのような苦労も買ってでもせよ」とは故人の言葉です。まったくその通りで肝に銘じておかねばなりません。楽な人生など望むべくもなく、唯一困難な経験こそが人生を生き抜くための智恵として身に付いていくと信じます。この度の豪雪も和尚にとって「禍を転じて福と為す」と捉えています。「窮して変じ 変じて通ず」だと心得て、自坊の雪害復興に全力を尽くそうと覚悟を決めています。大休息の後は大前進あるのみなり! 友峰和尚より


清々しい快晴 の 寳勝寺境内

昨日の荒れたお天気から一変して青空の広がる好天気となりました。今日はバレンタインデーということで幸いにも和尚もチョコレートを頂く事が出来ましたよ。早速あま~い気分に浸りたかったのですがそれどころではなく、終日法務に専心した一日となりました。夕刻になってようやくチョコを頂くことが出来、お蔭様で一日の疲れがすっかり取れたようです。「チョコ力(ぢから)」を頂きました、本当に有り難うございました。

先日、和尚の古稀祝いをして頂いた折、加賀容子様より頂いた手作りのとっても素敵な「赤唐辛子魔除け飾り」を寳勝寺のお部屋に飾らせて頂きました。加賀様は日頃よりお人形も沢山制作されており、家にお伺いした折にはいつも楽しみに見せてもらっています。最近は寺カフェのお部屋も色々とディスプレイされ、おしゃれな雰囲気となってお客様もきっと楽しんでおられると事と思います。



さて、ここに来て連日の除雪疲れがどっと出て来たせいか、全身に痛みが走り、困ってしまいます。昨日は歯が痛み、今日は筋肉痛に悩まされる始末。何か「いい話」は無いものかと探ってみましたところ、この「痛み」こそ尽力した結果であり、よく耐えたものだと自分で自分を慰労してやりました。筋肉さん、ありがとう!よく頑張ったね! 古稀を迎えたこの力こぶに感謝!感謝!負けてたまるか! 友峰和尚より
 和尚のちからこぶ
和尚のちからこぶ
 雪に埋もれた 大安禅寺本堂を撮影 / 和尚のアトリエから
雪に埋もれた 大安禅寺本堂を撮影 / 和尚のアトリエから
明日はバレンタインデーだそうで、ひょっともするとチョコレートが頂けるかもしれません? そんな切ない期待を裏切らない為には予め自分で買っておいた方がいいと思います。先日のテレビ番組で「ココア」が健康と美容に大変良いという情報を聞き、チョコレート好きの和尚も早速スーパーマーケットに出向いて色々な種類のチョコをたくさん買って来ました。この度の豪雪では連日除雪に精を出しており、これが大変な重労働ですから当然栄養補給が欠かせないわけで、そんな時はチョコレートが一番栄養価が高く疲れがいっぺんに取れると聞いての対策です。あまりに美味しいのでついパクパクと食してしまいます。除雪しながら時々、ポケットに忍ばせたチョコを頬張るのも雪国ならではの味わいです。なかなか風流ですよ!


さて、大安禅寺の諸堂除雪に明け暮れた9日間でした。「刀折れ矢尽きる」心境でやるだけの事はやりました。甚大な被害が出ましたが、それとて最小限に食い止めた感がします。午後からはアトリエに篭ってしばし瞑想しましたが、自然の猛威の前では「人事を尽くす」ことが最も重要だと自覚します。本当に多くの方々の親切と真心を頂いた9日間でした。ブログでは書きつくせないほどの感動を覚えました。ようやく大雪の峠を越えたとの報道に安堵しています。お世話になった皆様には心底より厚く厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。友峰和尚よ

降り続く雪の中 融雪装置の復旧作業
雪を征するものは水なり!とは申せ、今回の豪雪で谷川の水すら凍りついてしまい折角の融雪装置も活かす事が出来ませんでした。おまけに谷間から引いていた取水用パイプが雪崩のせいで寸断され、午前中は副住職と山へ登りパイプ復旧作業に取り掛かり、午後になってようやく復旧することが出来ました。

融雪用山水を取水する 配管 の 修復


雪が融けるにつれ建造物の被害状況が明らかになりますが、無残にも雪の重みで軒先が損壊した箇所が多くあり、昭和56年の豪雪被害を思い出していました。ここ数年、全国的に地震、津波、台風、噴火、水害、豪雪と自然災害が頻発している感があります。昔から「備えあれば患いなし」という諺がありますが、「備えようにも備えようのない患い」ばかりで、吉幾三さんの歌では有りませんが、福井では「灯油も無い!ガソリンも無い!食料も無い!スコップも無い!」という状況が現在も続いていると言いますから驚きです。

雪囲いの点検 補強
さて、自分の大変さばかりを伝えたここ数日のブログでしたが、当然の事ながら北陸地方にお住まいの皆様は同じ心配苦労と重労働の毎日であった事と心から御慰労とお見舞いを申し上げる次第です。北陸の女性を称して「肝っ玉おっかさん!」と呼ばれているのは正に、どのような困難にもくじけない不屈の精神が「北陸魂」として地域に根付いているからかも知れません。頑張りましょう!頑張りましょう!なにくそ!負けてたまるか!友峰和尚より
時折青空の見えるお天気となり、心なしかホッとしました。一晩で1メートル以上の降雪ですから、夏場なれば大洪水に見舞われていたということなのでしょうか? 近年の異常な気象変動はあまりにも極端すぎて予測も出来ず対応策に困惑します。この度の想像を絶する豪雪には手の打ちようも無くお手上げ状態でした。

お檀家様除雪応援のおかげで 参道を確保
金沢から急遽自坊に戻って3日目を迎えましたが、副住職との懸命の各建物屋根除雪が功を奏し、今のところなんとか被害を最小限に食い止めています。境内の参拝路は、お檀家様自ら除雪機を運転して救援して下さり、本当に感謝申し上げます。


ほとんどの自治体ではいまだに幹線道路の除雪がなされている状況で、多くの町内の生活道路には山のような積雪がそのまま残されています。大安禅寺のような山中の寺院はひとたび豪雪に見舞われると孤立状態になってしまいますので、なんといってもお檀家様の援護は本当に有り難いものです。

各所で 下屋が折れ、瓦が落ちるなどの被害が出ました

県議会議員 畑孝幸氏による 豪雪被害状況の視察 / 大安禅寺 本堂にて

午後からは地元県会議員・畑孝幸氏が、重要文化財建造物雪害状況を視察して下さいました。近年では、少子高齢化の影響からか各寺院に於いて檀信徒を含めた「寺院護持会」が新たに結成されつつありますし、重要文化財建造物を多く保有する寺では特に必須の課題となって来ています。「重要文化財を守ろう」をスローガンに今後多くの方々との御法縁を頂きながら、寺院護持と愛山護法の精神を後世に伝えていきたいと強く願うものです。友峰和尚より

ピョンチャンオリンピックが開幕しましたがとても観戦する余裕すらなく、必死で除雪にあたっています。いったい今回の豪雪は何を意味するのだろうと一所懸命に思案しながらの作業です。今年度より卑山重要文化財建造物全面修復工事が始まろうとしている矢先の大雪で、建物のいたる所に甚大な被害が出ています。

 屋根雪が木扉を突き破り / 大安禅寺本堂正面向拝
屋根雪が木扉を突き破り / 大安禅寺本堂正面向拝


特に今後の豪雪を考えると、本堂屋根は瓦葺より銅板葺のほうが雪を管理をする上で優れていると感じましたし、融雪装置も必須の課題となりました。寺へ通じる交通インフラの全てが遮断されたのは今回が初めてで、防火の面でも色々考えさせられたものです。

瓦を引きずり、落ちてくる屋根雪 / 大安禅寺 書院

建物内では 雨漏りが始まっています
建物から救済悲鳴が聞こえてくる毎日ですが、重要文化財を守る上での「人」もまた重要で、本日は金曜坐禅会会員の大工師・小林永尚棟梁が職員を伴って本堂雪囲い養生の為に馳せ参じて下さり、また上田工務店社長自ら養生用の板を急遽運んでくださいました。心から感謝申し上げます。
 大工師・小林永尚氏が 救援に駆けつけてくれました
大工師・小林永尚氏が 救援に駆けつけてくれました


落雪から窓を守るため 板で補強しています
歴史有る重要文化財建造物を後世に残していく為には、あらゆる護持組織が不可欠の課題と言えるようです。毎日のブログが豪雪の話題に集中していますが、普通の状態に戻るのにはまだまだ時間がかかりそうです。友峰和尚より


野町・少林寺 中庭側の落雪
2月4日から降り続いた大雪のため、連日雪対策に追われたこの一週間でした。昭和56年の北陸豪雪の時、和尚は34歳でしたから、新命副住職が誕生するちょうど一年前の出来事です。あれから36年が経って再び豪雪に見舞われることとなったわけですが、新命和尚にとってはなにもかもが初めての経験できっと戸惑ったことと思います。

屋根雪が ガラス戸 を 突き破る 勢い
節分明けに金沢寺院の法務遂行の為に出向いたものの、豪雪報道がなされる度、自坊が心配で胸の痛む毎日でした。当然の事ながら金沢兼務寺院でも連日除雪に追われましたが、今日は午前9時より少林寺本堂除雪の段取りを済ませた後、JR北陸線がいまだ不通ということで急きょ車で自坊に戻りました。

少林寺にて 業者さんに境内除雪の指示をしているところ

図面と写真で 雪に隠れた石柱などの位置を説明し 壊さないようにお願いしました

先々代住職の奥様に 除雪状況をお伝えしているところ

夕方 福井に戻り 大安禅寺屋根の雪下ろし

瓦がずり落ち 雨漏りが始まっている箇所も

あまりの建物被害の大きさに愕然としたものでした。早速に新命副住職とともに屋根へ上がって、最も危険な場所の除雪にあたりました。今回は重要文化財でも有る多くの卑山建造物に甚大な被害が出ており、今後の降雪が更に心配されるところです。明日からは少しずつ雪害復旧に当たりたいと念じています。

古人曰く「刻苦光明必ず盛大なり」、只管精進努力するしか和尚に活路は無いようです。友峰和尚より

スタッフと共に 霊苑管理事務所 の除雪
強い寒気が抜けて、今日は晴れ間の出るお天気となりました。「台風一過」という言葉が有りますが、今回は「寒気一過」とでも言いましょうか? 節分明けからたった3日間で2メートルもの豪雪に見舞われた北陸地方は、日常生活が大混乱となってしまいました。大安禅寺のインフラ全面復旧にはまだまだ時間がかかりそうで、積もり積もった屋根雪の除雪が緊急課題となって来ています。明後日からは雨の予報で一気に屋根雪が重くなるため、建物の損壊が懸念されます。



昨日は野町・少林寺に出向き大型除雪機を導入したものの、山門を通過できず止む無くスコップ手作業での参拝通路確保となりました。今日も雪掻きからスタートした一日となりましたが、好天気の中での作業に安心感を覚えたものでした。週明けから再び寒波が襲来するとの予報で、出来る限り融雪作業に時間を割いて次の大雪に備えたいと思います。
 瑞光寺から少林寺へと来てくれた除雪車 高さ制限で 少林寺の山門を通過できず
瑞光寺から少林寺へと来てくれた除雪車 高さ制限で 少林寺の山門を通過できず

やむなく人力で通路を確保しました
 屋根からの落雪が 屋根に届いてしまいました
屋根からの落雪が 屋根に届いてしまいました

少林寺山門前の除雪だけでも 本当に助かりました

全国の多くの方々から豪雪見舞いのお電話を頂き本当に有り難うございました。先日は和尚の古稀祝いのお電話を頂き、今回は豪雪お見舞いの電話と、本当に世の中「一喜一憂」の「諸行無常」を感じ取っています。だからこその「日頃からのご愛顧とご厚誼」の大切さを思います。さて、一難去ってまた一難! 油断は禁物ですね。いかなる困難にもくじけず頑張って参りましょう!友峰和尚より

寺町通りの雪景色 / 六斗の広見から寳勝寺方面へ

大安禅寺の豪雪状況 2018年2月7日
自坊に戻りたくても全ての交通インフラが全面ストップ状態で、いかんともしがたいジレンマの中にいます。新命副住職より寳勝寺に送信されて来た大安禅寺の今の豪雪状況ですが、すっぽり雪に覆われていて未だに孤立状態とか! 2メートルほども積もった雪のため参道には除雪車も入れないそうで、昭和56年以来の豪雪となっています。

大安禅寺 正面玄関
屋根雪と 地上の積もった雪 が つながっています


車道も雪で遮断されています

なにもかも 雪の中

こちらは寳勝寺 屋根雪落下後

 なんとか 通路を確保
なんとか 通路を確保
金沢も例外ではなく、写真の如く本堂前は雪で埋め尽くされています。昨晩も深夜0時に除雪をし、朝は6時から開始して山門前の雪かきをしました。もはや身体全体が鉛のように重く感じられ、腰もふくらはぎも腕も肩も限界に来ています。このような時にはお風呂に入るのが一番とさっそくエコキュートのスイッチを入れたものの、落雪のため室外ヒートポンプが動かず、残念無念! 今日は急遽大工さんに来て頂き、給湯器周辺の養生をしてもらったところ漸く復活、やれやれでした。




その場で 材料を調整しているところ

緊急の防護壁が完成
ここに来てようやく大雪も峠を越えた感が有りますが、今年はまだまだ次の寒波が来そうな感じです。日頃の運動不足はもう十分すぎるくらい解消できたかと思います。大安禅寺の檀家皆様も毎日除雪に追われている事と思いますが、くれぐれも身体には気を付けて下さいね。

孫の元気な写真も送られて来ました
岩内大工師のおかげで今日は温かいお風呂に入れそうです!「いい湯だな、ははん~ いい湯だな、ははん~」って、疲れた時はお風呂が一番です。さあ皆さん!何事にもめげずに頑張って参りましょうぞ! 山のような大雪も解けて流れりゃ水ですよ! 気にしない気にしない。友峰和尚より