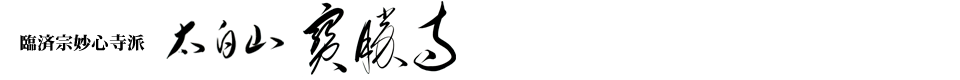和尚のちょっといい話
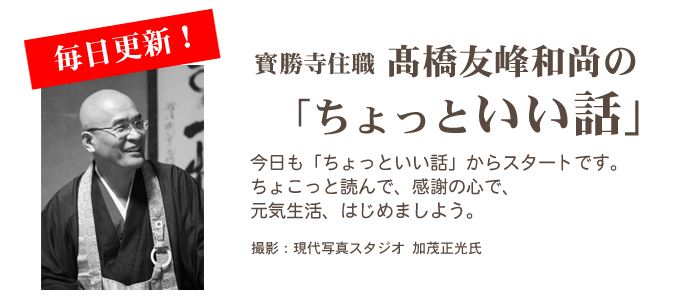 |

白蓮池の草取り / 大安禅寺 中庭にて
このところの猛暑日続きで熱中症の注意喚起が出ていますが、今日は和尚も危うく倒れるところでした。午前中は法務のため新命和尚と出掛け、帰寺後に気になっていた蓮池の草取りをしましたが、あまりの暑さに目眩(めまい)が生じ一瞬、目の前が暗くなる始末! すわ一大事と木陰で休憩していたところにタイミング良く、卑山お手伝いの島田さんがアイスクリームを持参して下さり、早速に頂きました。身体に熱を持っていたため、アイスクリームのおかげで難を逃れることが出来ました。有り難し!有り難し!

アイスクリームを頂きました 大安禅寺スタッフの島田さんと



また法務に出掛ける寸前には久しぶりに㈱日勝アドエージェンシーの小林卓雄会長が来られ、しばし歓談することが出来ました。こちらも有り難し! 金沢から自坊に戻ると境内は蝉しぐれで歓迎ムードいっぱい! 和尚感激でした。山中はいいですね。「閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声」そのまんまです。夕刻には日暮(ひぐらし)の鳴声でなんとも感傷的になるものです。両親の御霊に出会えるようでした。故郷に戻ることは自分の命に出会うことでもあるようです。元気を取り戻したところで、明日は再び金沢での法務に入ります。友峰和尚より

福井市足羽 臨済宗妙心寺派 華蔵寺様 です

傳燈寺にて お掃除ののち 盂蘭盆会諷経
金沢兼務寺院最後の盂蘭盆会修行の為、午前中は傳燈寺に出向き堂内のお掃除の後「盂蘭盆会諷経」をしました。傳燈寺にお参りするたびに感じるのは、なんと言っても空気が美味しいことでしょうか! 静まり返った堂内には霊気が漂い、歴史の重さを感じるものです。


金沢市内から車で約20分くらい走った山側に位置する傳燈寺は延慶元年(1308)に時の名僧・恭翁運良禅師が開山されたと言いますから、約700年の歴史を有する古刹でも有ります。現在の建物は大正時代に建てられたもので、創建当初は七堂伽藍を有していたそうです。帰り際に西川町内会長宅に立ち寄り、暑中のご挨拶をして寳勝寺に戻りました。今日で金沢兼務寺院4ヶ寺の盂蘭盆会法要を全て無事に円成することが出来ました。

火曜日は休寺日のため、夕刻には自坊に戻り明日の法要の準備に入りました。御年70歳と7カ月の身体には最近の法務遂行はかなりの負担となって来たようで、「老いては子に従え」と新命和尚に法務遂行を委ねています。さて、来月は大安禅寺の盂蘭盆会大施餓鬼会が15日に営まれますが、「報恩菩提」と「愛山護法」の真を捧げたいと念じています。友峰和尚より
ロシア・ワールドカップ決勝戦、フランス対クロアチア戦を観戦しようと午前0時まで起きていましたが、いざキックオフとなると両の瞼が重く塞がり、そのままま深い深い眠りに落ちてしまいました。ここ数日の激務の疲れからか、深夜の観戦はとても無理だったようです。眼が覚めればフランス優勝のニュースが流れ、繰り返しゴールのシーンが放映されていましたが、切り取りの映像からも素晴らしい試合で有った事が伺えました。一度ゆっくり録画を鑑賞したいと思っています。

紫陽花 隅田の花火 / 寳勝寺 玄関にて
皆様はこの三連休は如何お過ごしになられましたでしょうか? この度の西日本を襲った豪雨被害の状況が日々伝えられ、悲惨な被害現場が生中継されるたび心に強い痛みを覚えるものです。いまだ救助されていない被災者も多くおられ、ご家族皆様の心中を察するに余りあり、慎んで心よりお見舞い申し上げる次第です。この猛暑の中で、ボランティアの皆様が毎日頑張って災害復旧に当たっている姿には合掌するばかりです。和尚も被災者の皆様に少しでも支援できればと考えています。

天蓋百合のつぼみが 色づき始めました
養生のお蔭で腰痛も治まり、今日は三連休最終日の寺カフェのお客様を迎えるため早朝より準備に入り終日裏方に徹しました。観光客にとって避暑地にはお寺が一番で、今日は外国人観光客の姿が目立ったようです。一日を通して喜怒哀楽の感情が激しく交差する今日この頃、「無事」なる心境が如何に大切かをしみじみ思うものです。昨晩はNHK大河ドラマ「西郷どん」を鑑賞しつつ、人間模様に於ける人との縁の不思議を感じ取った次第です。友峰和尚より
 今年も 氷の季節がやってきました
今年も 氷の季節がやってきました

ぐんぐん大きくなっています 日中友好の朝顔
盂蘭盆の本日は、寺町の各寺院で施餓鬼会が行われていました。暦ではこの日を「中元」とも言いますが、古来、今年前半のお互いの無事を喜び贈り物をする日でも有ります。金沢兼務寺院の盂蘭盆会法要を終えて、午前中は野町・少林寺でお檀家様の法要が営まれその後墓参をしましたが、雲ひとつなく太陽が容赦なく照り注ぐ猛暑の中での墓諷経となりました。

ふれあいパーク霊苑管理事務所前にて


帰山後は台所方に入り寺カフェのお手伝いに専念したものの、連日の法務遂行の疲れからか夕刻には持病の椎間板ヘルニアが悪化して遂にダウン! 日曜日ということで掛かり付けの病院もお休みで、仕方なく安静を決め込んで休息しました。

朝顔開花のお便りが届きました
ここ数日、「日中友好の朝顔」が開花したとのお便りがあちこちから届き、大変嬉しく思っています。寳勝寺の日中友好の朝顔も大きな蕾を幾つもつけており、まもなく皆様にお披露目出来ることと思います。卑山ではこの時期の風物詩ともなって来ており、開花を楽しみにしています。

山門前にて つぼみがたくさん付いています

夏の夕焼けに照らされるつぼみたち

三連休も明日が最終日。猛暑にもめげず金沢市内は多くの観光客で賑わいを見せています。本日はせっかく和尚を訪ねて下さったにもかかわらず和尚の突然のダウンでご挨拶できなかったこと心よりお詫び申し上げます。明日には元気に復帰したいと思います。南無観世音菩薩 友峰和尚より

少林寺 盂蘭盆会開式を告げる 寺宝の梵鐘
最早、暑さを愚痴っても仕方が有りません! 全国的に気温が上昇し所によっては40度に近づいた地域も有ったとか。午前10時半より野町・少林寺で盂蘭盆会法要が営まれ、大勢のお檀家が参詣されました。予め気温上昇の情報が発令されていた為、堂内のあちこちに扇風機を設置してフル回転したものの、今日のような猛暑では如何ともしがたく只管精進一路でした。
 第十四代 宮崎寒雉様御寄進の半鐘を撞く 宝光寺様
第十四代 宮崎寒雉様御寄進の半鐘を撞く 宝光寺様
本日は自坊より新命副住職そして富山氷見市・宝光寺様もご出頭下さり、正午には法要を無事円成することが出来ました。昨年の9月に兼務住職として赴任しましたが、本日は法要終了後に今後の寺院活動についての説明とご協力をお願いし散会となりました。

少林寺 盂蘭盆会法要のようす

大安禅寺 新命副住職が維那を務められました


檀信徒の皆様が 御焼香をされているようす



法要終了後の法話と 今後の少林寺法務等説明会のようす

法要と法話は一体のもので、法要前にお檀家の桑島様から伺った「チョットいい話」を引用してさっそく法話で披露させて頂きました。その話とは、どのような良き言葉も「濁点」が付くとその意味が正反対になるというもので、例えば「意思(いし)」に濁点が撞くと「意地(いじ)」になり、「徳(とく)」に濁点が付くと「毒(どく)」になり、「口(くち)」に濁点が付くと「愚痴(ぐち)」になり、「本能(ほんのう)」に濁点が付くと「煩悩(ぼんのう)」になるというものでした。なるほど!なかなか説得力のある説明ですね。
 午後より ふれあいパーク霊苑での御供養を修業しました
午後より ふれあいパーク霊苑での御供養を修業しました
本日の盂蘭盆会法要も「心の掃除」が主眼で、「洗心」の心でご供養に臨めばご先祖の霊もさぞかしご満足いただけるものと思います。和尚のお盆の行事遂行はまだまだ続いていきます。頑張りましょう!頑張りましょ!友峰和尚より


金沢市本多町 瑞光寺にて 盂蘭盆会を修業しました

金沢市営野田山墓地に向かう道路が朝早くから混雑を見せるなか、本日は午前10時半より本多町・瑞光寺で盂蘭盆会が厳修されました。お盆とあって寳勝寺を取り囲む寺院のあちこちから読経の声が響き渡り、終日御供養日となったようです。


敷地内の墓地 檀信徒様の御家の 五輪塔にて 墓諷経

気温が上昇する中での墓諷経では背中を滝のように汗が流れ、夏本番を否が応でも体感したものでした。先般死去した落語家、桂歌丸さんの生前の活躍ぶりが特番で放映されていましたが、亡くなられる寸前まで落語家としてのプロの本分を全うされた映像には頭の下がる思いでした。暑いの寒いのなんて言っているようではとてもとても歌丸さんの足元にも及ばないようです。

先代住職のお墓所にて 奥様とともに
明日は野町・少林寺で盂蘭盆会が修業されるため、本日の午後からは法要の準備に入りました。親戚の方々も多く参列予定となっており入念な準備作業となりました。さて皆様はお盆はどのようにご先祖霊供養を予定されておられますでしょうか? 謹んで父母の恩祖先の恩に感謝しつつ御供養申し上げたいと思っています。友峰和尚より

ふれあいパーク霊苑 深緑の中での御供養
昨日は過密スケジュールの中での花菖蒲苗植えをし、不思議な事に今日は昨日の猛暑日とは打って変わって朝から小雨模様となり苗達にとっては過ごしやすいお天気となったようです。世話方さんには耳にタコができるほど水遣りをお願いしていただけにホッとしました。明日からは再び猛暑日となるそうですから、油断は出来ません。自坊の職員の皆様には毎日の水やりを欠かさないようお願しますね。
 奥の院 檀信徒各家墓前にてお盆の諷経をしました
奥の院 檀信徒各家墓前にてお盆の諷経をしました









ふれあいパーク霊苑「宙(そら)」での法要を終えた後には昨日のハードな畑作業のあおりからか足腰が痛み、午前中に川北整形外科病院を訪ね膝関節炎と腰痛の痛み止め注射を打ってもらいました。本当に情けないの一言です!

本堂にて ご依頼のご先祖供養を修業しているところ

午後からは職員とともに本多町・瑞光寺へ行き、明日10時より営まれる盂蘭盆会の準備とお掃除をしました。こじんまりとした禅寺ですが、歴史を感じさる仏像が数体お祀りされており、職員が丁寧にお掃除しました。





兼務寺院先を巡回しながら多くの仏像にお参り出来る事を幸せに感じています。仏像の持つ不可思議な霊力が和尚を元気にしてくれます。皆様も寺院にお参りした折には是非、本尊佛の前で静かに瞑想してみて下さい。心の安らぎの広がりを感じますよ! 現代社会はそのような不思議な御利益世界から次第に隔離されていくのでしょうか? 仏の御利益とは「ほどける」事であると思います。色々な苦悩から解放されるのも、仏の慈悲の力だと思うものです。友峰和尚より

気温が急上昇するなか、昨日に引き続き世話方さんと花菖蒲の苗植えをしました。花菖蒲はもともと乾田で育つものですが、この暑さでは流石に苗も悲鳴を上げているようで作業が急がれたものです。本来なら世話方さんにお任せして法務遂行のため金沢に戻らなければならなかったのですが、苗が心配で心配で作業続行となりました。お蔭様で無事にすべての苗を植えることが出来て安心したものです。あとは水やりをよくよくお願いして、午後に金沢に入りました。
 花菖蒲の株を分け 苗を植えつけていきます
花菖蒲の株を分け 苗を植えつけていきます

蒸し暑いなか 黙々と作業する世話方さん



根元を 足で踏み固めているところ
この14日、午前10時半より野町・少林寺で盂蘭盆会大施餓鬼法要を営む予定となっており、本日は職員によって大掃除と法要の準備が行われました。昨年9月に大本山妙心寺の辞令を受け、少林寺兼務住職に就任して以来今日まで法務を遂行してきましたが、未だ十分では無く現在は檀信徒皆様との交流が一番大切かと思っています。
 お盆行事をひかえ 金沢 少林寺の大掃除
お盆行事をひかえ 金沢 少林寺の大掃除
 窓ガラスや 桟 柱 畳など 隅々掃除しました
窓ガラスや 桟 柱 畳など 隅々掃除しました


少林寺 中庭の苔

寳勝寺と違って先代住職が在寺されていたことと、先代住職の奥様が日々お寺を丁寧に掃除されまた墓地も管理されて来た事も有って、禅寺としての風格が全体に感じられます。今後は自分の出来る範囲で寺院復興と法務遂行並びに後継者育成に尽力して参りたく思っています。さて、梅雨明けと同時に本格的な猛暑到来となっています。皆様方にはくれぐれも御身ご自愛ください。友峰和尚より


7月8日 吉田裕介君と真由さんが来寺されました
この7月14日(日)に金沢市内の式場で結婚式を挙げるというので、吉田裕介君がフィアンセ真由さんを伴って先般挨拶に来られました。本当に嬉しい事です。吉田君は福井の大学に在学中の4年間、大安禅寺へアルバイトに来られており、金沢の寺カフェをお手伝い下さったこともあります。大安禅寺でのアルバイトは彼が学生時代のことですからもうだいぶ昔の話となりましたが、その間、現在の彼女と今日まで仲良く御付き合いをされこの度目出度くゴールインとなったそうです。

勿論、和尚は吉田君のご両親とも懇意にしており、大安禅寺にも何度か来て下さった素晴らしい御両親です。ちなみにお二人の新婚旅行先はイタリアだそうで、羨ましいかぎりですね。皆様の新婚旅行は何処でしたか? さて本日は猛暑の中、花菖蒲の株分けと植え替え作業をしましたが、さすがに30度を超える暑さの中での作業には参りました。なんとしても来年は立派な花を咲かせたいという一念で頑張りました。

本日 大安禅寺花菖蒲園にて

苗を移植する場所の土を おこしているところ


大安禅寺世話方衆の堀江さんが 苗を植え付けているところ

大安禅寺世話方衆 の 宮田さん

苗を運ぶ 加藤職員


次々と 土をおこしていきます

花菖蒲とのお付き合いも約38年になります。毎年6月、その美しい姿を見せる時は、我が娘の艶姿を見るように思うものです。有り難し有り難し。友峰和尚より
 昨冬の雪害修復を担当された 渡辺社寺建築様と / 大安禅寺 受付所にて
昨冬の雪害修復を担当された 渡辺社寺建築様と / 大安禅寺 受付所にて
寳勝寺の盂蘭盆会大施餓鬼法要を無事に終え、本日は福井県小浜市の常高寺様へ花菖蒲の苗を頂きに行って来ました。当初は盂蘭盆会の前に伺う計画でしたが、梅雨前線停滞の影響でJRが3日間全面ストップしたため予定変更となり、本日は急遽、いつもお世話になっている日勝アドエイジェンシーの中西大(ゆたか)さんと、大安禅寺の加藤職員と共に一路小浜に車を走らせました。



立派な苗を分けていただきました
常高寺様は花菖蒲の寺として有名で、特に珍しい品種を育てられているため和尚が懇願して苗を分けて頂いた次第です。来年から卑山諸堂修復工事が始まり、拝観者方々は本堂や庫裡には入れなくなります。花菖蒲園ゲートのある枯木堂側入口が玄関となることを鑑み、来年6月には立派な花菖蒲を咲かせ皆様をお迎えしたいという思いから新しい品種を求めての行動でした。

常高寺様にて お茶のお稽古の席に参加させて頂きました
常高寺様に到着すると、まず最初にとっても美味しいお抹茶を頂きました。ちょうどお茶の稽古日で奥様が指導されており、グッドタイミングでした。本日は本当に有り難うございました。


そうそう、大安禅寺に帰寺したと同時に富山県砺波市から素敵な奥様方が拝観に来ておられ、お茶をご一緒しました。新命和尚の「生き生き法話」を聞きに来られたそうですが残念な事に今日はお休み、ならばせっかく遠くから来られたので和尚がご挨拶させて頂きました。本当にようこそ御来寺下さいました。またいつの日かおめもじしたいと思います。有り難うございました。友峰和尚より
 富山県からお越しの 参拝者の皆様とともに
富山県からお越しの 参拝者の皆様とともに

如月会の皆様 誠にありがとうございました