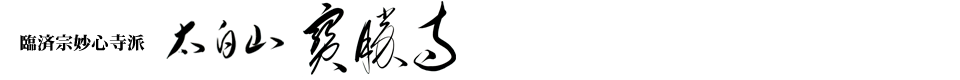寶勝寺日誌

10月も後半となりました。今日は晴天時々雨という珍しいお天気となり、太陽から降り注ぐような雨を思わず撮影した次第です。

ふれあいパーク霊苑でも日々、秋が深まり、色づく庭園墓地の風景に心が癒されます。秋の薔薇が次々と開花し、お参りに来られた方々が丁寧にお花を御供えされている後を拝見しますと、じんわりと温かい気持ちになります。





夏のあいだ、ぐったりとしていた杉苔が日に日に緑を増しています。植物の生命力には、本当に驚かされるばかりです。


生命力と言えば、こちらの「菊」の生長にも大変驚いているところです。昨年秋、寳勝寺中庭の日陰でひょろひょろと育っていた、か細い小菊(?)をたった1~2本移植した記憶があるのですが、気がつけば、頑丈な茎のもとに沢山のつぼみが育ちました。酔芙蓉もそろそろ名残花となり、次は小菊の開花が待ち遠しいところです。
野路菊 も もうすぐ咲きます

次々と咲き続ける ほととぎす 寺内を飾るお花にも 大活躍 です


糸すすきの穂 が 伸びて来ました
平成三十年度
≪ 寳勝寺盂蘭盆会 住職法話のご紹介 ≫
今般は未曾有の豪雨災害により全国各地に甚大な被害がもたらされ、多くの方々が犠牲になられたことに対し心よりお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。

… 和尚が寳勝寺を兼務してから早や7年が過ぎましたが、その間、多くの方々との御縁を頂いてこのお寺を復興して参りました。檀信徒皆様をはじめ㈱ココ・プランニング様、㈱豊蔵組様との御縁を得、そして今日は新たに同じ臨済宗妙心寺派として参列して下さったご家族もおられ、更にはふれあいパーク霊苑でも沢山の方々との御縁を頂いております。

…思えば、昨年は工事また工事で皆様には大変な御心労をおかけしたわけでございますが、代々墓区域である「奥の院」も立派に出来上がり、歴代住職をはじめ前田利常公からの檀信徒各家御先祖様もしっかりとお祀りする事が出来ました。今後は、本日御加担下さっている桂岩寺様、江雲庵(こううんあん)様、宝光寺様にもご協力頂き、盂蘭盆会法要に太鼓や鉢(はつ)を取り入れ、臨済宗本来の儀式の形を整えることに尽力したいと願っています。何かと簡素化されていく時代の風潮ではありますが、いまこそ丁寧な御先祖供養を行っていきたいと考えています。


… 仏教において「法(ほう)」といわれるものには、3つの要素があります。それは「真理」「形(かたち)」そして「規則」です。この3つの要素が守られますと、物事はおのずと前進して行きます。さきほど皆様とともに唱和した「白隠(はくいん)禅師坐禅和讃」の中に「因果一如(いんがいちにょ)の門(もん)ひらけ」とありますが、「真理」とは「因果一如」のことです。自分のしたことが、そのまま返ってくる。「棚からぼたもち」とはありえない話で、まず、ぼたもちを作り、そして棚に乗せる。そうすると、何かの拍子に落ちてくるかもしれないというほどのことです。何も行動を起こさないのに返ってくることは、まずありえません。そして「無二無三(むにむさん)の道直(みちなお)し」とは、二も無く三も無い。自も他もなく統べては自分と一体であるということです。人間は尊いものを外に求めがちですが、一番尊いのは自身と心得、自分が喜ぶのと同じように周りの人が喜ぶことを考えて無心に行動を起こすこと、それが「回向(えこう)」と言って廻り返ってくるのです。今回のような災害が起きた時にはお互いに助け合う、お見舞いをする、そういう一体の気持ちを持っていれば、お釈迦様の弟子として充分にその加護を受けることが出来、常に心が安らいでいるという「安心(あんじん)の法」を得ることができるのです。


… 来年度には庫裡と本堂裏外壁の修復工事が予定されていますが、それを以って寳勝寺の修復は完了です。今後は少林寺の修復、そして傳燈寺での法務活動などにも全力で取り組んでいきたいと思っています。

ふれあいパーク霊苑 合同慰霊祭
最近は、ふれあいパーク霊苑にも御家族や御親族が次々とお墓参りに来られています。供養寺としてこれほど嬉しいことは有りません。どうか御先祖の恩、父母の恩をいつも心に留め置いて頂きまして、無事で心安らかな毎日をお過ごし頂きたいと願っています。そしてお盆や御彼岸の法要は勿論、お近くへ来られる際には是非、寳勝寺へお参りに来て頂きたいと願っております。【事務局編集】
2019年 4月、フランス・サンリス市で開催される芸術祭「第1回 アート・サクレ芸術祭」に、髙橋友峰住職が招待禅僧として参加することになりました。こちらはその芸術祭をご紹介するページです。ぜひ御覧下さい!

サンリス市
「第一回 アート・サクレ」フェスティバル
開催期間:2019年 4月21日(日)~4月28日(日)
2019テーマ「大地から星への詩」
ノートルダム大聖堂 * 聖ピエール教会 * 聖フランブール礼拝堂
※動画の中で、住職のメッセージ映像が紹介されています。(2分52秒頃~)


 歴史あるサンリスの風景 芸術祭会場となる美しい教会
歴史あるサンリスの風景 芸術祭会場となる美しい教会
スピリチュアルな世界を表現するための舞台
このフェスティバルは、あらゆる文化・分野・時代を混ぜ合わせ、全ての宗教やスピリチュアルな活動から創造された美に門戸を開いています。コンサート、展覧会、会議など精神芸術の多様性や活発さを反映し、多彩なプログラムから構成されています。(公式サイトより)
芸術、最も普遍的な財産の芸術よりも重要なことは、人々が共に集うことでしょうか?
「芸術」…、文化と思想は欠くことの出来ない結び付きです。芸術は、生まれや言語、作者が誰であろうとも、様々な人々の象徴的・審美的・表現力豊かな世界に出会うことを可能にしてくれます。これが、この聖ピエール教会で8日間に渡って開催されるコンサート、展覧会、アトリエ、スタンド、会議などのイベントの骨子です。サンリス「アート・サクレ」フェスティバルは、スピリチュアルな生活や活動を行っているアーティストのみならず、感じたものを自由に表現しようとするアーティストにも門戸を広く開いています。
力の噴出
宗教の復活は、過去30年間に渡りフランスで観察された最も重要な事柄の一つです。が、この動きは、絵画や彫刻の下で、大部分が過小評価または無視されています。20世紀の初めから、芸術作品は魂を失った近代性を反映する傾向にあります。しかし、聖なるものは排除することが出来ません。それは灰の中から蘇り、私たちに力が湧き出る共通のビジョンを与えます。
存在をたたえる
このフェスティバルでは、集中力、繊細な感覚、感情、抽象、探究、バランス、混沌……表現するために歩み続け、自己を超える努力をしているアーティストが沢山いることを伝えたいと思っています。そう、世の中には、騒音から遠く離れて作業を続けるアーティストが存在しています。彼らの作品は、近代主義の基準にはそぐわないかもしれませんが、確かに近代社会の中に存在しています。そういった作品に光を与えることは私たちの誇りです。
神秘を解き放つ
サンリスには長い歴史と厳かな大聖堂が存在しています。「芸術」は、そのサンリスの懐でフェスティバルの一時を共に過ごすように導いてくれる糸です。宗教の枠を超え、サンリス「アート・サクレ」フェスティバルが出展者・来場者共に感嘆し、神秘を解き放ち、とりわけ敬意を共有できる機会になれば幸いです。御友人や御家族、そしてお一人でも是非ご来場下さい!
サンリス、「王家の街」…
中世の美しい街並みを残すパリ近郊の街サンリス(オー=ド=フランス地域圏、オワーズ県)。フランス・カペー王朝の始まりの地(987年)でもあるサンリスは、その後もシャルル10世(19世紀)の治世まで数世紀に渡り歴代フランス国王が訪問し、滞在地としてその地位を保ち続けてきたことから、現在に至るまで「王家の街」と呼ばれています。石造りの古い街並みが残るこの町は、「髪結いの亭主」や「王妃マルゴ」など、フランス映画の撮影舞台として数多くスクリーンにも登場し、映画人を惹き付けて止まない街としても知られています。
王宮の目の前に建つノートルダム大聖堂は、12世紀から16世紀にかけて建造されたサンリスのゴシック建築の象徴です。またユーグ・カペーの妻アデライード王妃(Adélaïde d’Aquitaine/945-952頃-1004)によって建てられた聖フランブール礼拝堂や13世紀にルイ9世(Louis Ⅸ/1214-1270)の命で建てられた聖モーリス小修道院など、街にはフランス王家ゆかりの歴史的建造物が数多く残されています。
その他にも、街の中心部にある3つの博物館が、サンリスの豊かな歴史と文化を今に伝えています。

平成30年6月19日、寺内と境内につづき、花菖蒲園と薔薇園を観賞させて頂きました。花菖蒲は満開を過ぎ名残花となっていましたが、緑葉の中に、浮かぶような大輪の花が本当に美しく咲いていました。

なぜか 紫の品種ばかり カメラが向いてしまいます


【 薔薇園にて 】


釣鐘状のクレマチス 圧巻の花房です
「大安禅寺 薔薇園」では、今年も奥様にご案内して頂きながらのとても贅沢なひとときを過ごさせて頂きました。山から吹き抜ける清風、野鳥のさえずりとともに、多種多様なバラやクレマチス、ラベンダーやミントなどのハーブと珍しい初夏の花々、グランドカバーといわれる地表の草花まで本当に見応えのある、美しい薔薇庭園となっています。
~ 薔薇の花々 ~

ピース (Peace)/ フランス

ベルサイユのばら「La Rose de Versailles」 / フランス

園内には品種名や産地の説明札が付けられているものもあり、どの花もとても優雅な名前です。お伺いした6月19日、バラの木々は一度目の満開を終え、再び次々と新しいつぼみを付け始めていました。花菖蒲祭千秋楽から7月にかけても、見頃が続いているのではないでしょうか。






つぼみ から 大輪へ 刻々と変化する花の姿


ときおり 遠い異国を旅しているような 気持ちになりました







 透き通るレモン色のバラ 木陰の青紫陽花が 黄色を一段と際立たせます
透き通るレモン色のバラ 木陰の青紫陽花が 黄色を一段と際立たせます


八つ橋のテラスの 屋根の上にまで伸びる枝葉に大きなつぼみ


【 クレマチス の花々】

園内にはいり、最初に迎えてくれる純白のクレマチス。真紅のバラとのコラボレーションが、花菖蒲祭の華やかさを引き立てるかのようです。

 バラのつぼみとクレマチスの調和
バラのつぼみとクレマチスの調和




鈴なりの満開クレマチス


クレマチス 鉄線 と アナベル(白紫陽花)



 珍しいクレマチスの花後 なぜこんな くるくる に なるのでしょう
珍しいクレマチスの花後 なぜこんな くるくる に なるのでしょう

金クルクル品種 と 銀クルクル品種のコラボレーション 花の色も 絶妙 です

お客様も不思議そうに眺めておられました

 こちらも 本当に珍しい クレマチス 「 サンダー 」というそうです
こちらも 本当に珍しい クレマチス 「 サンダー 」というそうです






風にそよぐ五色の吹流し、 清々しい大安禅寺薔薇園でのひとときとなりました。また来シーズンを心待ちに、お花の写真を眺めつつ寳勝寺での植栽に精力的に取り組んでいきたいと思っております。

 誠に ありがとうございました
誠に ありがとうございました

大安禅寺境内にて 本堂正面より本尊聖十一面観世音菩薩を参詣
平成30年6月19日火曜日、大安禅寺を拝観し花菖蒲園や薔薇園をゆっくりと観賞させて頂きました。当日撮影しました写真を中心にご紹介させて頂きます。
【 境内にて 】

大門の前に 沙羅双樹
 つぼみはもちろんのこと ふさふさとした大きな葉です
つぼみはもちろんのこと ふさふさとした大きな葉です


境内じゅう 朱や緑のもみじ眩しい景色
 庫裡玄関までの 壮大な参道の景色です
庫裡玄関までの 壮大な参道の景色です

大自然の中の のびのびとした花々
【 寺内にて 】

庫裡玄関にて 「萬松山」の扁額と 住職が描かれた達磨図衝立

文房流晴心会 野口支部様によるいけばな と 長田和也様の手漉越前和紙行燈

中庭にて 蒔絵のようなもみじのきらめきに感動しました


誕生佛 と 平出全价和尚禅画 「唯我独尊」のもとに
【 いけばな展 】

文房流晴心会野口支部様の華展「緑風に誘われて」


支部の皆様によって常にお花の入替えや生けこみが行われており、華展期間中は毎日、活き活きとした新作が展示されています。花や葉々の凜とした姿はいつまでも眺めていたい、離れがたいような美しさです。



同じ作品を どの角度から鑑賞しても 美しい姿です


 江戸時代は きっとこんな光のもと お花を鑑賞されていた事と 思いを巡らせました… / 開基堂にて
江戸時代は きっとこんな光のもと お花を鑑賞されていた事と 思いを巡らせました… / 開基堂にて


「行雲流水」 渓仙 書 / 松雲院にて
【 旧参道 や 駐車場 にて 】

どこまでも続くような 松林と紫陽花です

北陸の山の中の しっとりと潤った紫陽花

6月下旬から7月へ 本格的梅雨に入るとますます美しくなることと思います
【平成30年度 寳勝寺・盂蘭盆会のご案内 】
本年の盂蘭盆会法要は、7月8日 午前十時より厳修致します。
寳勝寺檀信徒の皆様には丁重なるご返信を賜り厚く御礼申し上げます。(返信の締切は7月1日です)
本年も皆様方の御来寺を心よりお待ち申し上げております。



丈夫で 元気な苗が 育っています
今年も「日中友好の朝顔」の季節がやって来ました。例年にも増して元気で丈夫な苗が育っています。六月の清風吹き抜ける寳勝寺境内にて、今日は苗床からプランターへの植替え作業をしました。


暑くなく寒くもなく、絶好の植替え日和です。山門に、境内に、霊苑にとますます沢山のお花を咲かせることになっており、今から本当に楽しみに準備しています。

植替え作業に引き続き、中庭の大掃除をしました。2月の大雪の影響からか(?)今年は異常なほど旺盛に植物が育ち、実生が生え、森のようになっていました。惜しみつつ草とともに実生を抜き取り、枝を剪定するなどして形を整えました。梅雨時期となり、苔もいっそう生き生きしています。

庭の中央に 大安禅寺から株分けされた花菖蒲です
 柏葉紫陽花もいきいきと
柏葉紫陽花もいきいきと
 雨の前 の 蒸し暑さです
雨の前 の 蒸し暑さです
遠くで雷鳴が聞こえ始めました、寳勝寺玄関前です。6月下旬のような蒸し暑さで、今夜にかけて暴風雨になるとのこと。朱傘や毛氈の床机を片付けようか否かと迷っているところです。
沙羅双樹の樹
ふれあいパーク霊苑の薔薇に引き続き、本日は寳勝寺境内の庭をご紹介させて頂きます。式台玄関の前に新しく植えられた沙羅双樹、いつのまにか大きな葉を広げ、たくさんのつぼみがついています。大安禅寺の沙羅双樹とずいぶん樹形が違うので、冬の間は「本当に沙羅双樹?」と疑いの眼でしたが、細い枝先にも大きなつぼみがつきました! 開花が本当に楽しみです。


沙羅の木の根元には、細竹、白萩、ツワブキとともに、涼やかなアシや小菊を植えています。細竹は一年に一度、七夕の折に短冊などを飾りつけています。

ホタルブクロ つぼみが出て来ました

玄関横 の 定家かずらが咲き始めました


やぶらん

突貫忍冬
 京かのこ
京かのこ

天蓋百合 野地菊
かつてのお庭から移植した草花も、それぞれの新しい場所で根を伸ばし始めています。
 高田様から頂いた 茉莉花の苗
高田様から頂いた 茉莉花の苗

山門に咲く睡蓮は ご近所のアイドル

ふじばかま
寳勝寺の中庭では、2月大雪の影響で植物の成長にも変化がありました。屋根雪落下で紫陽花が四方に折れてしまったのですが、かわりに根元のふじばかまが旺盛に育っています。

なんと珍しいカメムシを発見 背中の絵柄が昆虫のようです

「カフェ」
苗を購入して3年目のバラ、その名も「カフェ」です。3年を経てようやくたくさんの花を咲かせてくれるようになりました。寳勝寺の庭もふれあいパーク霊苑も改葬修繕後、初めての春を迎えています。来年、再来年へと本当に楽しみなお庭になっています。

いよいよ薔薇の花が咲き始めました、宝勝寺ふれあいパーク霊苑です。晴天と雨、五月のお天気に添って毎日次々と開花しています。この度は、霊苑に咲く薔薇のようすを特集してご紹介させて頂きます。

絹のような花びらです
 スタンダード薔薇 花束のように
スタンダード薔薇 花束のように




合祀墓「 宙 ~そら~ 」の 美しい花園

壁面の薔薇

故人のお名前を刻むガラスプレートにつたう ツルバラと葡萄


まぶしいほど 鮮やかな濃い桃色



代々墓「奥の院」にて


石柱を伝うツルバラ 開苑から一年で こんなに旺盛に成長しました

色鮮やか美しい姿かたちの花々が、苑内の御墓を優しく包み込むように咲いています。この地で眠られる御霊とともに、お参りの方々の心も真に癒される庭園霊苑となりました。毎日訪ねたい、いつまでもお参りしていたい、気持ちになります。




これからますます美しく開花していくことと思います。

皆様 薔薇の季節に 是非ご参拝ください

いよいよ五月となりました。今日も無事、寺カフェのお仕事を終え、静けさの戻った玄関前です。霊苑改葬と境内改修後、初めての春の大型連休を迎えていますが、美しく整った寺の景色には沢山の感謝とともに、不思議なずっと以前からそうだったかのような懐かしさを感じています。

こでまり
かつて式台玄関の右脇に植えられていた、こでまりです。やや小さく剪定されていますが、新しい場所で大きな花を咲かせています。

ニシキギ
四年ほど前、奥様が本堂前に植えられたニシキギです。当時の何倍も大きくなりました。新緑から紅葉まで、一年じゅう美しい樹木です。
 ニシキギ たくさんの小さな花を咲かせています
ニシキギ たくさんの小さな花を咲かせています

移植された木々の根にくっついて 蔓日々草が出てきました

式台玄関のおだまき 健在です

式台玄関のオダマキが、今年も元気に開花しました。昨年、鉢植えにしたオダマキは今年まったく芽が出ず、無念ではありますが、種が残っていますのでまた新たに育ててみたいと思っています。
 新しく 玄関に植えました 都忘れ
新しく 玄関に植えました 都忘れ
 中庭の白すみれ 庫裡玄関前に少し移植しました
中庭の白すみれ 庫裡玄関前に少し移植しました

連休中、寺カフェのお客様をおもてなしするため寺内のあちこちに生花を飾っています。昨年に引き続き今年も傳燈寺のお山から山野草を頂いて来ました。

ちごゆり
 ひめしゃが
ひめしゃが

鈴蘭 ビオラ 風知草 は 寳勝寺の庭からです
また、ふれあいパーク霊苑でも、「和エリア」の花々を始め「洋エリア」のバラがたくさんのつぼみをつけ始め、開花が待ち遠しい近頃です。
 湧水のせせらぎとともに
湧水のせせらぎとともに
 代々墓「奥の院」 石柱の薔薇
代々墓「奥の院」 石柱の薔薇

 歴史深いこの地に 美しい開花を 待ち遠しく思います
歴史深いこの地に 美しい開花を 待ち遠しく思います
まだまだ続く大型連休、お客様には寺内でゆっくりされた後、また境内の床几に座ってゆっくり語らう姿がなんとも嬉しい日々です。御来寺下さいました皆様に心より厚く御礼申し上げます。寺カフェは5月6日まで休まず開業しています。ぜひお立ち寄りください。
 新芽が次々と / 擬宝珠 アジュガ
新芽が次々と / 擬宝珠 アジュガ