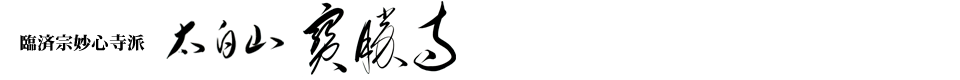寶勝寺日誌
今日はお昼も水が凍るような寒い日となりました。この10日間ほど御手洗所が使えない日々でしたが、本日、ようやく新しい便座などの設置が始まりました。電気屋さんによる配線工事が行われ、夕刻までには使用できるようになるとのお話しです。

壁の塗装のようす
壁の木板が塗装されました。天井と柱は元来の色です。
本日の工事では、霊園側の御手洗所の塗装や、廊下の壁の修復作業が行われました。細かなところまで丁寧に修復されています。
霊園側御手洗所に渡る廊下の壁の一部が修復されました。
また本日は夕方、旅行業者の方と関係者の皆様が来山され、春からの寺町観光プランについての打ち合わせが行われました。旅行コースとして寳勝寺を組み入れ企画して下さるとのことで、本当にありがたいことです。ますます春が待ち遠しく、頑張って参りたいと思います。
今日は祝日ですが、2月中の完成を目指して、大工師さんとクロス屋さんが作業をされています。片方の御手洗所では壁や床・天井が完成し、お寺らしい雰囲気の、居心地の良い空間が出来上がって参りました。
 午後、墓地改葬計画の打ち合わせのため来山された、㈱トムソーヤの高田さまと新しい御手洗所の視察をされているところです。
午後、墓地改葬計画の打ち合わせのため来山された、㈱トムソーヤの高田さまと新しい御手洗所の視察をされているところです。
墓地側の御手洗所も、ここまで出来上がりました。
昨晩のうちに、寺も街もまた冬景色に戻ってしまいましたが、午後からは水気の多いぼた雪が降り、着実に春が来ているのを感じます。今日は、金沢市歴史文化部・歴史建造物整備課の皆様が来山され、松浦建設㈱の吉田専務さま、東野さま、大工師さんとともに式台玄関復興工事の打ち合わせが行われました。
土間から階段、板の間までの長さを検討されているところ

これまで、寺の倉庫で保存されていた旧来の木戸。式台玄関が復元されるにあたり、再利用されることになりました。レトロガラスの施された重厚な引き戸です。
夕方には、寳勝寺檀信徒の稲場俊達さまがお越し下さり、住職と久しく歓談されておられました。御来山、誠にありがとうございました。
急ピッチで進む御手洗所工事 / 大工師の本さまです。(住職撮影)
2月に入り本格的に始まった御手洗所工事ですが、この1週間で、いっきに完成が見えて参りました。
1月下旬は、この様子でしたが・・・
2月7日に、こうなりました。大工さんの技術に感嘆です!
いっぽう寺の外では本日、雨どいの資材が運び込まれ、取り付け工事が行われています。これまでの塩化ビニール製雨どいにかわり、すべて銅製の雨どいで大変風格があります。
新しい雨どい資材到着 / 大工師の岩内さまです。(住職撮影)
輝く銅製の雨どい
式台玄関も、トイレの跡がすべて撤去され益々玄関の風格を戻しつつあります。これまで目に留まらなかった玄関のひさしの彫刻なども、際立って見えて来るようです。
梁に絵様が施されています
日々着々と進んでいる御手洗所移設工事ですが、新しい壁や床板が張られ、木の香り漂う清々しいトイレの全景が見え始めています。
一方、旧お手洗い所の解体工事も始まりました。メリメリバキバキという音と共にあっという間に解体されましたが、何も無くなってみますと、なるほどかつて玄関だったという風格が戻ってくるように思います。
約1か月後には、ここが式台(玄関)になっているということで、工事の過程が本当に楽しみです。
屋根瓦の葺き替えが無事完了しました。来週頃には足場の解体が始まるとのことで、整然と佇む屋根がまもなくお目見えです。旧お手洗い所は、電気や水道が止まり、いよいよ式台玄関復興工事が始まります。それに先駆け、式台玄関の屋根に銅板が葺かれました。
復元された懸魚(げぎょ) / 撮影 平成27年2月3日
本堂屋根の妻飾り「懸魚(げぎょ)」が、大工師の岩内さまによって復元されました。屋根の頂に取り付けられる飾りです。水を思わせる魚を模り、火除けのおまじないの意味があるそうです。足場が外れ本堂全景を拝見できる日が本当に楽しみになって参りました。
屋根の修復が大凡終了し、続いて、お手洗所移設工事が本格的に進んでいます。
本堂・上の間、柱の補修が進み、新しい材木が継ぎ足されています。古い柱にぴったりと組み合わさっています。
外側の柱にも、新しい材木が継ぎ足されました
柱の足元には、鉛の板が敷かれています。大工師の方に触らせて頂きましたところ、柔らかく大層重い板でした。この板を敷くことによって、柱と束石がゆっくりしっくりと馴染み、尚頑丈になるとのお話でした。