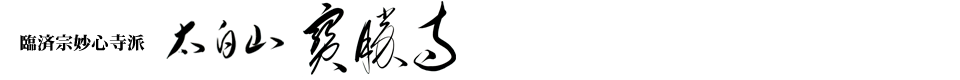和尚のちょっといい話
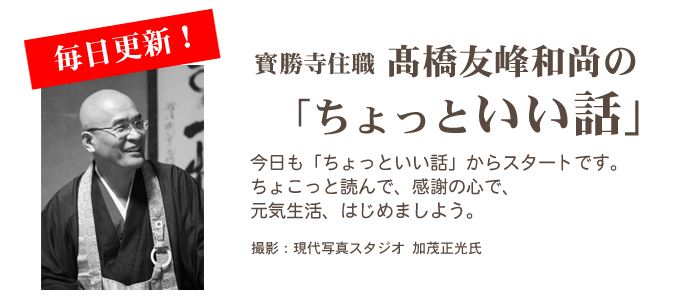 |
世にも不思議な湯のみ茶碗です。よくよく見ると茶碗の周りにぶつぶつの突起が有り、器を持った時に手の平を程良く指圧してくれるという優れものです。誰が作ったのかは知りませんが、たまたまお食事をしたお店で使用されていた物が売店にも並べられていたものですから思わず買い求めて、それ以後、日々愛用しています。そもそもこのような物を買い求めるのは、当然のことながら高齢者の方でしかありませんね。若い人なら湯呑み茶わんの周りにぶつぶつの突起が出ていても、デザインぐらいにしか思わないと思います。
最近は和尚も色々な場所で「年寄用グッズ」を目ざとく見つけ、買い求めています。所謂、簡単に健康管理が出来る代物といったものでしょうか。他にも、「健康運動用マット」とか「健康まくら」とか、「健康」と名の付くものに何でも目が行くようになったのは、「年寄」になった証拠でもあります。昨日発表されましたが、日本全国で百歳になられた方がついに6万人を超えたそうです。その数、61568人です。また、その中での女性の比率は87パーセントですから、やはり女性の皆さんが日本の長寿界をリードしているようです。65歳以上の方が約3千万人を超える日本社会に於いて、今後も益々「老人向けグッズ」が人気を博すると思います。次に何が登場してくるのか? 楽しみな日々を過ごしています。友峰和尚より
茨城県鬼怒川堤防決壊の現場中継がなされましたが、福井豪雨の際の足羽川堤防決壊の事を思い出しました。多くの方が次々と救助されていましたが、一瞬のうちに家屋が濁流に吞まれていく様には目を覆うばかりでした。近年の風雨災害は想像をはるかに超えたものですから、緊急避難情報が出た場合には速やかに指示に従って行動しなければなりませんね。最近では災害状況がテレビや携帯電話を通して生中継で映し出されますので、常に災害の現場情報を知る事が自分の命を守る事にもつながるかと思います。今日では日本の何処に住んでいても「安全」という言葉は無いようですから尚更、各地域での防災訓練がより一層大切になって来ているようです。地元では台風18号の無事通過を喜んでいた矢先の大水害のニュース、一刻も早い復興を願いたいと思います。「天災は 忘れたころに やって来る」などという諺は、現代社会には通用しないようです。「天災はいつでもやって来る」と承知して、日々の心構えが求められているようです。自坊の大安禅寺も今日まで多くの天地災害に見舞われて来ましたが、いずれの場合も地域の檀信徒皆様や自治体の俊敏な救援活動のおかげで今日を無事に迎えています。なんと言いましても「人海戦術」こそが災害復興の大きな原動力であることは、昔も今も変わらない事実であると思います。日頃から近隣皆様との交流を大切にしていきたいものですね。友峰和尚より
承証寺様にて 寶勝寺霊園改葬工事説明のようす
台風18号の本州縦断のニュースに翻弄されながらの一日でしたが、今日は「寶勝寺霊園改葬工事」の説明のため、工事関係者と共に霊園と隣接している承証寺様そして極楽寺様を訪ねました。いずれの御住職様にも霊園改葬工事へ御理解を頂き、また大変丁寧に応対して下さり、深く感謝した次第です。
極楽寺様にて
心配された台風の影響も無く、夕方にはお日様も指す穏やかな光景に心より安堵いたしましたが、「一難去ってまた一難」では有りませんが、工事車両の出入り口確保の件で夕方には再び松浦建設㈱の東野様が来寺され、現場立ち合いとなりました。「三人寄れば文殊の知恵」とはよく言ったもので、工事関係者皆様のそれぞれ得意分野での意見が出され、良い知恵が生まれて来る事に感心したものでした。やはり持つべきものは良きスタッフですね。これからも難しい局面が発生することと思いますが、知恵を出し合って進めて行きたいと思いました。「艱難汝を玉とす!」故事に倣っての毎日です。
会議終了後、寳勝寺にて打ち合わせのようす
それにしましても、東京から会議に出席された ㈱トムソーヤ・高田様から頂きましたお土産のクッキーの味には驚きました。一日が終わって早速にお土産を頂きましたが、さすが!世界の大都市・東京の味覚でした。皆様にお届けできないのが残念です。お口の中いっぱいに広がる絶妙な甘さに、一日の疲れも吹き飛んだものでした。さて明日からも元気で頑張って参りましょう! 友峰和尚より
「地震 雷 火事 親父!」とは古来、恐ろしい物の例えの順番ですが、台風18号が今夜から明日にかけて本州を縦断するとか。金沢でも、兼六園の松の木が折れないようにと庭師さんが補強対策をしているニュースが流れました。もちろん福井県も例外でなく直撃の恐れがあるそうですから油断はできません。最近は風雨による被害が続出していますが、その被害がこれまでとは違って想定外の状況となっています。恐ろしい物の中に「台風」という言葉が見当たらないのはどうしてだろうかと? 疑問を感じて早速に調べてみましたら、この「親父」が台風のことを指すのだそうです。古来の例えですから、もちろん今どきの「親父」の姿ではありません。昔の親父で特に明治時代頃の親父の姿を想像するに、いかめしい面の口元にそれはそれは立派な口ひげが反り繰り返っている風貌は流石に恐ろしい感じが伝わって来るものです。一度言葉を発すれば威厳に満ちた貫禄十分な風格から、「親父」となったそうです。それはいいのですが、最近の突風は半端なものではなく所謂「竜巻」ですから、最早「親父」をはるかに超えた「暴れん坊」ゆえに「地震 竜巻 火事 雷」と詠み方を替えなければ今の時代にそぐわなくなってきているようですね。明日の3時ごろに福井県を通過する予定とか、本当に無事に過ぎ去ってくれることを祈るばかりです。嵐の前の静けさなんでしょうか、今日は穏やかな一日でした。どのような状況下にあっても心だけは安んじていたいものですね。クワバラクワバラ、なぜ「クワバラ」か? 菅原道真公のお住まいになった桑原という地名の所だけは、なぜか雷が落ちなかったそうです。そこから「クワバラクワバラ」と言うようになったそうです。ふ~ん 友峰和尚より
本日の「楽く楽く法話」のようす
最近、指先がしびれる感覚があるため、さっそくに地元の病院を訪ね首の検査をして頂きました。その折には体調もいまひとつで、問診をして頂き血液検査をすることになりましたが、本日、その検査結果が出ました。誰もが経験する結果報告の際の不安ですが、和尚の場合は腰の持病もあって随分と長い間、整形外科に通院し、長期間に渡って痛み止めのお薬を服用して来た為、不安というよりも諦めに近い心境で先生の言葉を待ちました。その結果は、「異状なし」でした。
本来なれば大いに喜びたいところですが、兎も角も身体が不調であることには変わりない為、自分なりに診断すればやはり「老化現象」だと確信した次第です。実に情けなくも「老い」には勝てないようです。この、「どうにも避けられない老化現象」を遅らせるための健康管理が必要であることを自覚した一日となりました。病院には大勢のご高齢の方々が来られていましたが、皆それぞれに、老いと戦っているようです。とりあえず血液検査は無事にクリアしましたので、今後は現在の健康をキープしながら、法務に取り組んでいきたいと思います。
午後からは、富山県から来られた御婦人方々へ「楽く楽く法話」をしましたが、各御寺院の奥様の集まりと聞き、いつもの法話とは少々リズムを変えてお話しいたしました。「タラソ、テラピー」ならぬ「話そう!寺ピー」という調子で語り掛けました。楽しいお話の時間の後は寺カフェを利用して下さり、感謝!感謝!でした。健康であるからこその「楽く楽く法話」ですね。皆様の御多幸を祈念しております。友峰和尚より

夕方、須貝さんと看板の打ち合わせをしました。
本当に久しぶりに「NHKのど自慢大会」の番組を見ましたが、最近の年少者の歌唱力アップのすごさを感じたひとときでも有りました。U-18野球ワールドカップでは清宮選手を始め若い精鋭が活躍しており、今やあらゆるジャンルに於いて世界を相手に日本人若者世代の活躍が目立つ毎日です。和尚の子供の頃などは、中学生ぐらいの世代の子供達が世界で活躍したなどというニュースを聞いた事も有りません。堂々として物怖じひとつしない態度には敬意を表したくなる程です。
話は戻りますが、今日の「NHKのど自慢大会」に出場された北海道在住の高校1年生男子の方は、クラブ活動で放送部に所属されているとか。声といい、度胸といい、トークといい、抜群でした。この番組はNHKの長寿人気番組でも有りますが、出場の素人さん達が全力で歌う姿はいつ見ても新鮮で微笑ましいものです。合格してもしなくても心から拍手を送りたくなりますね。「最近のテレビ番組は面白くない」と言う会話をよく耳にしますが、この番組だけは例外のようです。誰もが参加でき、聞けて、笑えて、応援できる、そんな番組をもっと作ってほしいものですね。

さて、終日20℃を下回る肌寒い一日となりましたが、この時期は健康管理が難しい季節でも有ります。くれぐれもお風邪など召さないように、皆様お元気にお過ごしください。友峰和尚より
お寺には、多くの檀信徒皆様から寄進された仏具を始めとした色々な調度品が有りますが、中には、創建当初から約三百年間に渡って年中行事などで使われて来た物もあります。このたび、北嶋千代子様が施餓鬼台前机用戸帳を寄進して下さることになり、㈱キタジマ会長の北嶋幹補様と共に卑山に来られました。お話によれば、千代子様が今年70歳の古稀を迎えられる記念に寄進を思い立たれたそうで、今日までの健康に感謝しての御心からだそうです。
施餓鬼台前机の採寸
戸帳を採寸されているようす
改めて今まで使われて来た施餓鬼台前机の戸帳を見ましたら、江戸時代中期頃のもので痛みが激しく何度も修理した跡がありました。千代子様は卑山の年中行事に参詣する度にこの戸帳のほころびが気に掛かっていて今回のご寄進を思い立ったとの事で、住職として本当に有り難く感謝申し上げました。まもなく秋季彼岸会・放生会を迎えますが、間に合えばその時までに寄進したいとの事でした。お寺をぐるりと見渡せば、それはそれは多くの方々から寄進されたものがお寺の荘厳を引き立たせています。仏語に「荘厳の浄土」という言葉が有りますように、やはり美しく飾られた堂内でのお参りは自然と心が落ち着くものですね。
生地を選んでいるところ
それにしましても一番感心させられたのは、戸帳生地をいろいろ持参されての現場での色合わせでした。流石に㈱キタジマ様って和尚は思いました。和尚感激!! 冠婚葬祭のあらゆる備品を取り扱っている会社ゆえの計らいでした。北嶋様ご夫妻とは30年以上の御厚誼を頂いてきましたが、心より感謝申し上げました。まもなく彼岸会がやってきます。「秋なれや 月を追う雲 逃げる雲」 足早に時が過ぎて行く昨今です。友峰和尚より
今、きゃりーぱみゅぱみゅの人気が絶好調で、まるで平成時代の寵児のような存在となっています。人気が出れば出るほど彼女の名前にも耳馴れせねばなりませんが、どうも名前の発音が難しく、和尚などはいまだに上手く言えないでいます。そこで早口言葉を作ってみました。「きゃりーぱみゅぱみゅ ハムかむかむ」です。皆さん、一緒に言ってみてください。「はいどうぞ!」 これがクリアできれば「きゃりーぱみゅぱみゅ」も噛むことなく言えるようになると思います。それにしても、彼女のキャラクターとしてのイメージを実にうまく兼ね備えた良いネーミングだと感心してしまいます。スターになる条件には色々有ると思いますが、やはり名前は重要でインパクトが要求されますから、その意味合いでは彼女の名前は抜群のインパクトが有ります。サイケデリックな服装、フィギュア的ファッションもまさに時代をリードする最先端のコスチュームですね。日本のアニメが世界的に流行を見せる中での彼女の活躍を心から称賛したいと思います。そんなことを思う時、今年の流行語大賞はどういった言葉になるのか、ふと考えました。和尚が思いますのに、やはり「白紙撤回」と「そうせい!」が今のところリードしているかと思いますよ。ニュースでは、インドネシアでの新幹線計画が「白紙撤回」となったそうです。早速に使われたような感じでした!。和尚も何か作ってみたいですね。「そうせい!」友峰和尚より
四季の景色の美しい日本! 特に、山並みの杉木立群の美しさには圧倒されるものです。今日のように小雨が降るなかでの靄(もや)のかかった山間を走り抜ける高速道路沿いの山々の景色は、日本特有でなんとも心癒されながらのドライブコースと言えるようです。また、金沢方面へ向かう高速道路から眺める日本海の景色も素晴らしいものが有ります。高速道路でのわき見運転は危険と承知で安全運転を心掛けながら、初秋の風情を堪能しながらのドライブでした。
午前10時半より開催された「滋賀北陸教区・御詠歌講習会」に本部長として参加したわけですが、100名近い御婦人方々の参加となり、堂内一杯に響き渡る御詠歌の奉詠は法悦に満ち満ちていました。毎年の講習乍ら、真剣に取り組む御詠歌部の皆様の姿勢に頭の下がる思いがしました。皆様にも是非いちど聞いて頂きたいものですね。
「いまどき御詠歌ですか?」なんて、時代遅れのように言われる方もおられますが、枯淡な響きの中にこそ心の安心を得ることが出来ますから、逆に申せば、いまだからこその御詠歌だと感じます。「クイック、ライフ」の現代社会、落ち着く間もなく次へと向かっていきます。たまには時間を止めて、古典のリズムに耳を傾けるのも風流というものですね。皆様の中で御詠歌にチャレンジされたい方は大安禅寺にお申し出ください!

さて、ブログを御読み頂いている皆様はいかがお過ごしでしょうか? 九月は「長月」とも言いますよ。秋の夜長を存分に、心の癒しの時間に使いたいものですね。実に気持ちの良い季節を迎えようとしています。坐禅の季節でもあるようです。友峰和尚より
2020年・東京五輪国際オリンピック・エンブレムが白紙撤回となりました。いわゆる一番の目玉であるシンボルマークの白紙撤回は、大きな波紋を広げています。この「エンブレム」という言葉も最近はよく使われるようになりましたが、以前は「シンボル」という言葉で表現されていました。その意味は、記章、標章、紋章のことで、それならばはっきり「大会紋章」と言ったほうが分かりやすいですね。とにかくこのような問題は、一連の関係者の誰が最終責任者なのかがはっきりしていない所に原因が有ると思います。どのようなイベントでも必ず、最高責任者がいて初めて成功の道が開けるというものです。国立競技場建設の問題のように、もし、総理大臣が常に最高責任者だとしますと今後大変なことになりますから、それぞれの組織の責任者が大いに頑張って良い方向に結果を出して行って頂きたいものですね。NHK大河ドラマの毛利敬親の口癖を借りるなら、「そーせい」って、きちんと命令と責任を持てる人が出てきてほしいものです。諺に「禍を転じて福となす」、もっと良いエンブレムが登場することを期待したいものです。
和尚は、しばしの休息も終了して再び仕事モードに入っています。「俺がやらねば誰がやる 今やらねばいつ出来る!」 やはり責任感を持ってやらねば何事も成就出来ないですね。「エンブレム」のニュースは和尚に大いなる勇気を与えてくれました。他人ごとでは有りません、常に自分の事と捉えて「オリジナリティー」の人生を歩んでいきたいものですね。和尚は和尚らしくあれ!!って感じ。友峰和尚より