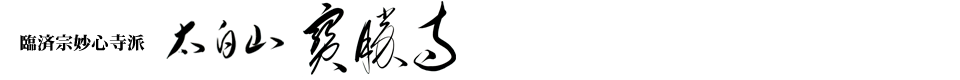和尚のちょっといい話
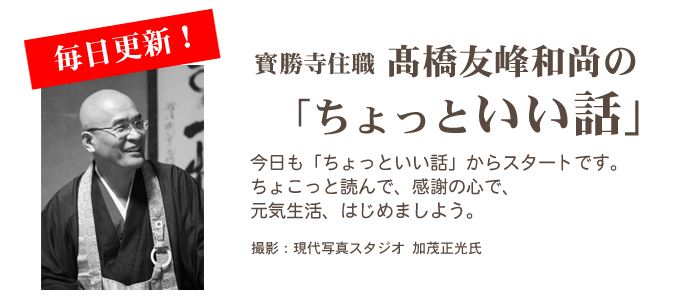 |
午前11時より金沢市芳斉町の髙巌寺様にて、先住職小祥忌(一周忌)法要の導師として出頭しましたが、福井より来られた御寺院方々と久しぶりに会うことが出来ました。髙巌寺は金沢駅に近い、街の中央に位置したところに有る臨済宗妙心寺派のお寺ですが、用水の流れる昔ながらの佇まいを残した閑静な場所に建てられています。金沢に来て5年が過ぎましたが、まだまだ知らない場所が沢山あり、至る所に歴史の重さを感じ取ることが出来ます。過去に戦災や地震などの被害に遭遇したことのない金沢市内だけに、昔のままの細い路地が縦横につながり、よりいっそう古へのロマンを掻き立ててくれます。いちど時間をかけて市内をウオッチングしたいと本当に思っています。また、古い町屋が数多く残っている事も金沢の魅力の一つだと思います。現在も途切れることなく観光客が訪れていますが、有名観光地のみならず市内のあちこちで旅行者の姿を見かけるのは、それだけ観光地が市内に集まっている事を意味しています。皆様も一度バックパッカーの一人となって、金沢市内散策を試みては如何でしょうか! きっと新しい自分を発見する事と思いますよ。そう言えば、今日のご法要後の珠洲市・吉祥寺住職の法話の中で「忌」の意味について、「心の上に己(おのれ)と書くのは、故人の恩徳や自分の心を振り返ってみる事だ」と言っていたように思います。己を見つめる事の大切さ、また歴史を振り返って見る事の大切さでも有るかと思いました。友峰和尚より
とうとうと言いますか、遂にと言いますか、風邪をひいてしまいました。最初は喉が少々ちくちくするぐらいでしたが、今日は物を飲み込むのも困難な状態で、さすがの和尚も病院に行き診察を受けました。熱は無く、喉だけが火傷の様な感じで、なんとも残念な一日となりました。午前中には檀家様の月参りも有りましたが、日頃の美声もままならず小さい声での読経となり、真にもって情けないとはこの事です。今、風邪が全国的に流行する気配とか。皆様もくれぐれも気をつけて頂きたいと思います。最初ちくちく中ひりひりの喉症状が現れましたら、これはもう間違いなく風邪です。
今年一年を振り返って見ても、風邪など一度もひいたことがなかっただけに「びっくりポンや!」でした。この「ビックリポン!」の言葉は、NHK朝ドラ「あさが来た」の主人公・白岡あさ役の波瑠の口癖ですが、どうやら今後の流行語になりそうな気配を見せています。「ビックリポン」って、なかなか面白い言葉ですから色々な場面で使えそうです。人間、身体のどこが悪くてもダメですね! 元気が半滅してしまいます。やはり常日頃からの健康管理が大切だと良く分かりますし、病魔はいつでも入り込むチャンスを伺っているようにも思いました。油断大敵!ビックリポンで済めばいいのですが・・・・。友峰和尚より
来年の干支は「申」という事で、今日初めてお猿さんの墨絵を描きました。今年の第一号の作品です! これから毎日干支の色紙を描き続けていくうちに次第に墨絵も進化していくと思いますが、歳を越えて来年の一月末頃になると、墨絵のお猿さんにも動きが感じられるようになると思っています。来年の法話の題目は「温故知新」ですが、お猿さんとの関わりはと申せば、昔から神様の使い、また知恵達者な動物として捉えられているところから、昔の良きところを学び、未来に生かすべく「温故知新」を画賛として書くこととしています。
昨晩から大荒れの天気となりましたが、その強風の中、先般東京で大変お世話になったCoco Planningの方波見様が事務局の方と来られ、しばしの時間でしたがふれあいパーク霊苑工事談議に花が咲きました。今後も多くの方々との出会いが増えて行くと思いますが、「温故知新」の言葉を心に於いて過ごして参りたいものです。さて、今日のお猿さんの墨絵ですが、「犬ですか?」って言われてしまいました。どうか皆様、お猿さんですので、お間違いのなきよう願います。「そうでござるか」友峰和尚より
昨日からのお客様と共に一路金沢に向かい、久しぶりにひがし茶屋街を案内しましたが、いつの間にか多くの新しいお店が開かれ、平日の今日も外国人の方や観光客で賑わいを見せていました。茶屋街入口に有るお店に休息しようと立ち寄ったところ、以前とはがらりと設えや雰囲気さえも変わり、おしゃれなお店に様変わりしていたのには驚きました。
少々お腹もすいていたので「焼きおにぎりお茶漬け」を注文したところ、写真の如く実に素敵な器を揃えての見事な物でした。もちろん味の方も抜群で、ミニあんみつがセットになっているところがなんとも女性に対しての気配りを感じさせてくれる絶品でした。

今や金沢市内は観光ブームに沸いているわけですが、どのお店も色々な工夫を凝らしてお客様に対応しているようです。また、観光客向けの貸衣装も大変人気で、和服を着た若い女性たちが観光客の求めに応じて記念撮影をしている風景はなんとも微笑ましさを感じさせてくれるものです。今年もあと一か月、金沢市はまだまだ北陸新幹線開業の恩恵を受け続けているようです。
この時期に有っては穏やかで暖かい一日となりました。午後より、社会福祉協議会団体様の依頼で地元の保養施設「すかっとランド九頭竜」を会場に法話をしましたが、ほとんどの方が65歳以上ながらその元気ぶりには驚きました。さすがに今、活気があるのは高齢者の皆様だと改めて認識したものです。これからの時代は、その地域地域で高齢者の健康管理のために色々なイベントを通して交流を図って行くのはベストの方法だと思いました。独居老人宅の増えつつある現状だけに、アイデアを出して孤立化を防いでいかねばなりません。
今日は広島県並びに愛知県から和尚のお客様が来られ、こちらも久しぶりの交友を深める時間となりました。自分が高齢になっても学ぶべきことは沢山ありますから、自分より経験の深い年輩者のお話を拝聴することは実に勉強になりますね。「あなたの知らない世界」ではなく「私の知らない世界」がまだまだ現実に有るという事です。勉強、勉強、また勉強、此れまでの怠慢が自己反省と共に蘇えってきます。皆様はどうでしょうか? なんだか今頃になってもう一度、学校に行って先生の講義を聞いてみたいと切に思うこの頃です。友峰和尚より
銀杏の落葉 / 大安禅寺 式台にて
今日から12月、師走に入りました。この字を見るだけで気ぜわしく感じてしまいますが、この「師走」の語源はあまりはっきりしないようで、一説には「師馳せ」から来ているとか。所謂この「師」とは僧侶のことを指し、12月は駆け込みの法事が増えてお坊さんが忙しく檀家さんの家を駆け巡る姿から師走となったそうです。いずれにしてもこの月は、習い事のお師匠さんや学校の先生はじめ色々な方々が年末に向けて多忙になり、毎日が駆け巡る状態になる事には違いないようです。
大安禅寺ではもう既に大掃除が始まっています。これからは急激に寒くなりますから、まだ暖かさの残る月初めから早めに大掃除をしてお正月を迎える準備をしようというわけですが、なにしろ広い広いお堂ですから、一か月をかけての徹底したお掃除です。来年の法話のテーマ「温故知新」に準じて、重要文化財のお堂を今後も大切にしていきたいものです。さて、皆様はこの一か月をどのように計画されていますでしょうか?「来年の話をすると鬼が笑う」そんな年齢を迎えつつある自分でも有りますから、この月は人生の締めくくり的感覚で、一日一日を一生と心得て大事に過ごして参りたいと念じています。どうか皆様、お元気にお過ごしください。友峰和尚より
11月最後の一日、愈々明日から師走を迎えます。天気予報とは違って今日は終日穏かな陽気となり、久しぶりにアトリエのお掃除をして、これからの厳寒に備え炬燵(こたつ)を設えました。幾度となく繰り返してきた光景ながら、流石に炬燵を見ると今年の終わりを感じるものです。お部屋を暖かくし足元もホッカホカの環境の中で色紙書きに専念しましたが、炬燵の暖かさは格別で心までも温まる感じで、日本古来よりの伝統的な暖房器具「炬燵」は実に優れものであると再認識しました。
色紙書きも今後は来年の干支である「申」の絵に替わりますが、12月いっぱいは日々「申」に成り切って、凡そ二百枚の宿題を全うして行きたいと念じています。昨日のNHK 大河ドラマ「花燃ゆる」を見ましたが、番組的には不評だったの事ですが和尚は幕末激動期の国内状況を知る上で大変勉強になり、毎回の放映が待ち遠しいものでした。明治維新から大正時代を迎える約20年間の国の有り様を少しではありますが垣間見た感が有ります。時として、歴史の事実を伝えようとするとドラマとしては面白味に掛けるものだと思います。間もなくドラマは終了しますが、もっともっと、歴史の奥を知りたいと思った今回の大河ドラマでした。友峰和尚より
11月29日は「いい福の日」というわけで、今日は一日幸せな気分で居たいと精進しました。午前中の「生き生き法話」後、年忌法要のお参りにおもむき、午後からも「生き生き法話」をしましたが、何とも爽やかな一日を過ごすことが出来ました。このこともやはり朝方、今日は「いい福の日」と心得て精進しようと誓ったからに違い有りません。
昔からよく言う言葉に「験担ぎ(ゲン担ぎ)」というのが有りますが、その日の数字語呂合わせでもなかなか面白いものです。人間、時として日々の出来事を悪い方に考えがちですが、常に「プラス思考」にもって行くことが大切であろうと思っています。この時期の旅行者の皆様は、ほとんどの方がその年の労を癒す為の観光となっていますから、一年の締めくくりとしての楽しい話を心掛けています。
そんなこと思っていましたら、ある方が「和尚さん今日はいい肉の日ですね、すき焼きなど食べてみたいですね!」だって。成る程、人それぞれに思いようも異なるものです。11月29日は「いい肉の日」でも有りますね。美味しいお肉を頂いて、元気いっぱい頑張りましょう!とはいってもお肉は有りません!憎々しいたらありゃしない。ギュウ。友峰和尚より
それにしましても素晴らしい門松です! もはや芸術作品と言っても過言では有りません。二十年余り以前より大安禅寺境内入り口に立てられて来た、卑山御用達「小森庭園」園主・末政幸憲氏の作品です。毎年お寺に御寄進下さっているわけですが、年々、テーマに沿ってその形を変化させてきました。
今年の門松のテーマは「温故知新」です。写真の如く、門松の後ろ側に「古きを温め新しきを知る」の如き意味合いのオブジェが設えて有り、実に見事な出来栄えです。昨日の地元新聞記事に大きく取り上げられていましたが、皆様も是非いちど、この門松を直に見て頂きたいと思います。
 今日の午前中には、小松に有ります会社職員方々の坐禅と写経研修会の指導に当たりました。今年もあと一か月余りとなったこの時期に合わせての社員修練会、日頃まったく馴染みのないカリキュラム内容ですからきっと戸惑われたに違い有りませんが皆さん真剣に写経と坐禅に取り組んでいた姿は大変立派でした。
今日の午前中には、小松に有ります会社職員方々の坐禅と写経研修会の指導に当たりました。今年もあと一か月余りとなったこの時期に合わせての社員修練会、日頃まったく馴染みのないカリキュラム内容ですからきっと戸惑われたに違い有りませんが皆さん真剣に写経と坐禅に取り組んでいた姿は大変立派でした。
納経の法要
今の時代には、人生のどこかで一度思い切って自分の心と向き合う時間が必要かと思います。その方法の一つとして、写経や坐禅にトライしてみては如何でしょうか。写経は自分の心を写し、坐禅は自分の心を投影します。さてどのような心が現れて来るのか?「ちちんぷいぷい」摩訶不思議!摩訶不思議! 心の安らぎは自分の心の奥底に潜んでいるようです。友峰和尚より
昨夜来からの雷轟と突風吹き荒れた金沢市は雪化粧の朝を迎えました。昨日は日本の政治の中枢地・霞が関での一日でしたが、本日は一変してスンスンとした何処までも清らかな冷気の匂いさえ感じさせてくれる北陸の朝。余りの環境の変化に戸惑いさえ感じますが、どちらもダイナミックな人々の生活エネルギーを感じさせてくれます。東京は躍動感のある素晴らしい町ですし、金沢は悠久の歴史とロマンを感じさせてくれるこれまた素敵な街です。これから本格的な冬を迎えるわけですが、和尚は雪国が大好きです。玄関入口の雪かきをしながら、気持ちも身体も引き締まる思いになりました。
今日も観光客の方が体を震わせながら寺カフェに来られましたが、関東方面からのお客様ですからきっと突然の雪に驚かれたことと思います。この時期の雪景色も北陸地方の風物詩の一つなのかも知れません。
さて、大安禅寺では門松が立てられました。まもなく師走です! えっ!もう師走? 人生待った無しですね。貴重な人生時間が過ぎ去って行きます。「うかうかと 暮らすようでも瓢箪の 真ん中あたりに締めくくりあり」って、誰かさんが言っていましたが、どうなんですか? 人生どのあたりが真ん中なんでしょうかね? さあ愚図愚図していてはいけません、寸暇を惜しんで頑張って参りましょう! 友峰和尚より