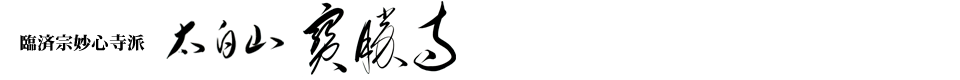寶勝寺日誌
昨日夕刻、寳勝寺にて開催されました”七夕夜カフェ”のご報告です。

まだ陽の落ちない午後5時半頃から次々とお客様が来山され、玄関はあっという間に大賑わいになりました。お昼過ぎまで降っていた雨が止み、涼しい風が吹きはじめ、「天気回復」の七夕祈願はすでに叶ったと感謝しながらのスタートです!
本堂入口の「受付」では、この度の”夜カフェ”企画発案者で、昨6月28日にキャンドル夜カフェを開催された桂岩寺さま(曹洞宗・寺町1丁目)と、前田尚毅様(㈱ビットストリーム代表)がお客様をお迎えして下さいました。ステキな浴衣姿で来山される女性もおられ、とても華やかです。受付の対面には、”テリマカシー・キャンドル”で美しく装飾して下さったアーティスト・浅野裕美様と、堀田洋菓子店(金沢市扇町)様の販売コーナーが設けられました。
撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏
本堂の中は、浅野裕美様によるキャンドルアートで荘厳な雰囲気に満ちていました。本尊・聖十一面観世音菩薩坐像と十六羅漢像にはライトが注がれ、鮮やかなキャンドルの灯明が美しく、来山された皆様もうっとりと拝観されていました。
撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏
”Terima Kasih candle”
午後6時、M4の皆様によるジャズの生演奏がスタート。少しずつ暗くなり”夜カフェ”が始まります。
思い思いに、七夕の夜を楽しまれる皆様。
 |
 |
堀田洋菓子店さまのケーキは、「笹のケーキ」と「マカロンケーキ」の2種類でした。パティシエ・堀田茂吉様が、この日のためだけに作った平成26年七夕限定のスイーツです。当初は3種類を試作して下さり、検討を重ねた結果、この2つのケーキが準備されることとなりました。お寺にふさわしい「和」風味の上品なケーキが大好評、堀田洋菓子店ファンの方々も多く来山されていました。
午後7時、住職の法話が始まりました。7月7日午後7時、寳勝寺で「七夕法話」を拝聴するという、不思議な一体感です。お客様はすでに100人近くがお集まり下さっていました。
七夕は、仏教では”お盆の入り”の準備をするという伝統行事でもあります。住職は、「棚に旗を立てて霊をお迎えする”棚旗”」のお話しや先祖供養の大切さについて楽しく法話をされました。
 撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏
撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏
法話に聞き入られる皆様。中央では、現代写真スタジオの加茂正光様が写真撮影をしてくださっています。
撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏
お昼間からは信じられないような月夜です。法話を拝聴される皆様の笑い声が響くなか、山門にも幻想的なキャンドルアートが登場していました。
撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏

御内陣にて、ご祈祷される住職
七夕法話に引き続き、「星祭り祈願」の御祈祷が行われました。御祈願をお申込み頂きました皆様、そして今夜御来山下さいました皆様の無事安寧を祈願し住職がお経をあげられました。
お参りされる皆様
星祭り祈願の後、ふたたびM4の皆様によるジャズの生演奏。手拍子をしながら音楽を楽しまれる皆様。
撮影/現代写真スタジオ 加茂正光氏
終了の夜9時近くになっても、たくさんの皆様が喫茶を楽しんでおられ、素晴らしい七夕の夜となりました。ご来山下さいました皆様、本当に本当にありがとうございました。無事円成後には、終了茶礼をいたしました。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。このたびは誠にありがとうございました。
7月7日午後、写真撮影の打ち合わせに来て下さった現代写真スタジオ・加茂正光様です。素敵な写真をありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。
「七夕の夜のキャンドル寺カフェ」、本日無事円成致しました。ご来場下さいました皆様、誠にありがとうございました。
平日にもかかわらず、100名近い皆様がお越し下さいました! / 住職の七夕法話のようす
夕方からはお天気にも恵まれ、たくさんの皆様にお越しいただき、
またご協力ご加担頂き深く感謝申し上げます。詳細は明日のホームページにてご報告いたします。
誠にありがとうございました。
いよいよ明日、「七夕夜カフェ」を迎えます。
今日は寺カフェ終了後の午後4時に、桂岩寺のご住職様とキャンドルアーティストのhiromiさん、「あるんけ金沢」の前田さんと森さんが来山され、本堂の設え準備をお手伝いして下さいました。内陣には美しいキャンドルアートがセッティングされ、リハーサルも行われました。その様子をご紹介したいのですが、今日はガマンです。明日は雨の予報ですが、寳勝寺で荘厳な天の川をご覧いただけることと思います。本番では写真を沢山撮影して御報告させていただきますので、七夕夜カフェにお越し頂けない皆様もどうぞお楽しみにお待ちください。七夕夜カフェが無事円成しますように・・・
 のかんぞうが咲き始めています。/本堂前庭、月桂樹の下に
のかんぞうが咲き始めています。/本堂前庭、月桂樹の下に
まもなく7日は七夕夜カフェ、そして、その後には大切なお盆の行事が控えており、準備に慌ただしく過ごしております。次々と咲く庭の花々や日々成長する朝顔をゆっくり観察できず残念に思っていたところ、今日は思いがけずうれしい出来事がありました。
先日、住職が御手植えされたピーマンの苗木。
特別な事も無く、いつしかお寺の景色に溶け込んでいましたが・・・
ふと気づくと、小さな苗木に大きなピーマンが実っていました!小さな植木鉢の中で、力の限りひとつの実を大きく育てたかのような姿に感動です。
さっそく住職が収穫されました。「ありがたく頂きます。」と住職。
収穫されたピーマンは、寳勝寺台所の韋駄天さまに御供えされました。七夕夜カフェまではあと二日ばかり、精いっぱいの準備をして皆様をお迎えしたいと思っております。今日はピーマンに励まされた日となりました。
寳勝寺中庭の下野(しもつけ)

寳勝寺・中庭のアガパンサス
数日、忙しくしておりました間に、夏の花が次々と開花していました。7月1日を待っていたかのような、一斉の開花です。アガパンサス、擬宝珠(ぎぼし)、底紅むくげ、ノウゼンカズラなどが咲き、真夏の到来を感じます。
そんななか、寳勝寺ではグリフィス博士のご子息・ジン氏による、住職の墨蹟撮影が行われました。来る10月22日より28日まで、ニューヨーク州ブロンクスビル、サラ・ローレンス大学で行われる個展の準備が進められています。
作品一点一点を丁寧に撮影されるジン氏 / 寳勝寺応接室にて
額や屏風・掛け軸など、撮影は終日続けられました。真夏の到来と共に、秋のNY個展準備も本格始動です!
擬宝珠、天蓋百合、紅色蛍袋など / 本堂前庭にて
爽やかな涼気の日となりました。今日は、まもなく宝勝寺に訪れる夏にふさわしい新しい風情のご紹介です。上の写真中央、下あたり・・・
昨日の「ちょっといい話」に登場しました大安寺観光協会さまの ”結び苔玉” が、県境を超えて宝勝寺へ届けられました!
住職が、寳勝寺カフェにと購入して下さった苔玉です。
葉の形を見ると、ミズキの種類でしょうか?
小樹と苔の見事なバランス、空間。
日本独特の美の世界が造り出されています。
”結び苔玉” は、縁側にも飾られました。
上の写真で中央上部に浮かぶのは・・・
青々とした苔玉から、アイビーが育っています。
日陰の緑がなんとも涼しげですね。
大事に育てて参りたいと思っています。
そして今日は、マレーシアから来日されたという若いお坊様が、寳勝寺を拝観されました。
”寺カフェ”、 ”自由拝観”の看板をご覧になり寺内へ入って来られたとの事でしたが、ぜひ住職にお会いしたいというご要望を頂き、応接間にてひととき歓談されることとなりました。
マレーシアで得度し、タイで修行されたとのこと。通訳の方を通じ住職にたくさんの質問をされました。・・・「福井の永平寺や横浜の総持寺へ行きましたが、多くの一般人の若者が修行に励んでいました。日本の若者はなぜ出家を選択し、修行するのですか?」、「日本の仏教の戒律とはどのようなものですか?」などなど、住職もひとつひとつに対し丁寧に答えられ、「日本の若者」の心の不安や、禅に”落ち着き”、”安らぎ”を求めていることを説明されていました。
 インド仏教のことやお釈迦様のお悟りのことなど、言語・民族を超えた宗教のつながり、以心伝心の雰囲気です。「思いがけない御縁で本当に良かった」と言われ、寺内やカフェが素敵になっていると何度も表現して下さいました。このあとの旅では、京都の禅宗寺院で短期の修行をされるとのこと。約1時間ほどの短いご滞在でしたが、深く心に残る出来事でした。旅のご無事をお祈りしたいと思います。
インド仏教のことやお釈迦様のお悟りのことなど、言語・民族を超えた宗教のつながり、以心伝心の雰囲気です。「思いがけない御縁で本当に良かった」と言われ、寺内やカフェが素敵になっていると何度も表現して下さいました。このあとの旅では、京都の禅宗寺院で短期の修行をされるとのこと。約1時間ほどの短いご滞在でしたが、深く心に残る出来事でした。旅のご無事をお祈りしたいと思います。
土曜日の寺カフェです。
最近では地元の方も来て下さるようになり、有難いことです。
観光客では、年齢層は若い学生さんや20代カップルが多いのですが、地元からは御年輩女性の方々にご好評頂き、リピーターも増えて参りました。カフェとしている室間には日頃ご紹介している季節の花々をたくさん生けていますが、それも女性陣の心を掴んでいるようです。
そんな折、お客様が「七段花(しちだんか)が生けてあるわね。」と花瓶を指さして言われるので、お聞きしたところ、
この、青い山紫陽花のことを ”七段花” と呼ぶそうです。江戸時代の文献にも残っているものが、一時代は失われて”幻の紫陽花”と言われていたと教えてくださいました。寳勝寺の中庭では、見事に満開になっています。
引用・・・江戸時代、シーボルトが著書『日本植物誌(フロラ・ヤポニカ)』で紹介しましたが、その後、日本人のだれもがその実物を見た人がなく、”幻のアジサイ”とよばれて長い間さがしつづけられていました。ところが、昭和34年(1959)に、たまたま六甲ケーブル西側で神戸市立六甲山小学校の職員が、発見し採取しました。それはシーボルトが紹介して以来約130年ぶりになります。「シチダンカ」は、ヤマアジサイの品種で装飾花が八重になったもので、質素な野生味のある花で江戸時代から栽培され、茶花などに使われていました。江戸時代に、星型に咲くヤマアジサイの八重のものを「七段花」と呼んでいたものが失われて幻の花となったそうです。
お花を学んだことと共に、お客様と近しく交流できた事もとても嬉しく、私も”七段花”の大ファンになりました。寳勝寺の木は大きく青々と茂り、これまでも大切に育てられて来たことが伺えます。真夏の季節も水やりを欠かさず、大切に継承していきたいと思っています。
寳勝寺に帰って参りました本日です。
山門の前庭では、大きな花菖蒲が開花していました。
金沢市内の多くの家々では、「和」の園芸植物がたくさん育てられています。
朝夕はさみを携えて熱心に庭に出ている愛好家の皆様をよく見かけますが、さすがに花菖蒲はありません。
現在、寺の山門から入口にかけては珍しい品種の鉢植えが並べられており、街の方々にも愛でて頂いています。
サッシ工事中の中庭にも・・・
先日から、サッシの取り替え工事が行われています。
寺町在住の大工さんが来られ、ただいま工事進行中です。
連日、草木花の開花をお伝えしていますが、庫裏側では住職お手植えの”茄子”の花が咲きはじめました。
花菖蒲・紫陽花とともに、茄子も梅雨の紫花だったのだと再認識です。
休寺日となりました本日は、休暇をいただき福井・大安禅寺の花菖蒲祭へお伺いしました。
曇り空で時折涼風が吹きこみ、絶好のお花見日和です。
平日にもかかわらず、観光バスと自家用車で駐車場は満杯でした。
いつお参りしても、清浄な空気に満ちた境内です・・・
ご挨拶させて頂きました後、さっそくに花菖蒲園へ。

たくさんの品種が咲き、ただいま見頃です!
八ッ橋の入口では、来園者をお迎えする真紫の花菖蒲が咲き誇っていました。
きれいです!
続いて、奥様が作庭され、今年から開園されたバラ園へ。
贅沢にも、オーナーである奥様がご案内してくださり、丁寧なお花の解説に聞き入りながら、ひとつひとつゆっくりと鑑賞させて頂きました。
真紅やピンク・薄黄色など。
写真以外にも、まだまだたくさんの品種が植えられています。日本はもちろんフランス・アメリカ・ドイツ原産とお国柄によって花形も違い、とても見ごたえがあります。バラのほかにも、クレマチスやハーブ、なつゆきかずらなど初夏の花がたくさん!
花菖蒲園や境内を巡るように育てられている紫陽花も、
見事に満開になっています。
山から降りてくる涼風と爽快な青色で、
梅雨の暑さを忘れるひとときでした・・・。
山と緑と花とお寺、
その後、帰宅してからも空中庭園を散歩しているような清々しい心地です。
本当にありがとうございました。
皆様もぜひ、大安禅寺花菖蒲祭へ御参拝ください。
花菖蒲もバラもたくさんのつぼみがついていましたので、まだまだ見頃が続くことと思います。