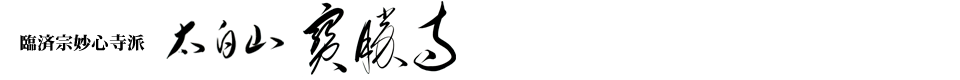和尚のちょっといい話
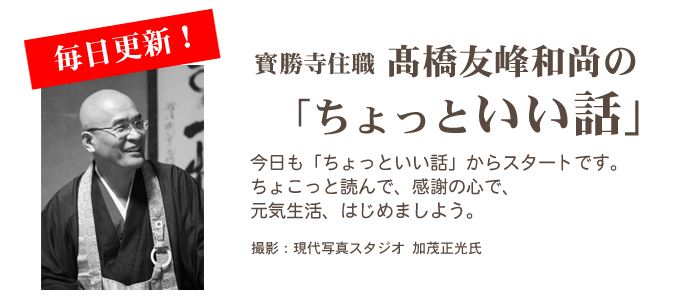 |

とうとう本日、千秋楽を迎えました。1か月間に渡った第32回「花菖蒲祭」、沢山の来園者で賑わった花菖蒲園も名残花が終わりを惜しむかのように可憐に咲いていました。今日も雨上がりの園内をゆっくりと参拝者の方が散策されていましたが、多くの方々の御支援を得ながらのお祭りも無事に幕を閉じようとしています。寺内では文房流晴心会・野口翠智社中の皆様による生け花展が好評を博していました。午前中に、野口社中の黒川様・渡辺様がお花直しに来山され、一緒に愈好亭でお茶を頂きながら今回のお礼を述べさせて頂きました。

この一か月間、多くの来訪者方々とたくさんお話し出来たことが、和尚にとって何よりの喜びの時間となりました。また、久しぶりに副住職に代わって「生き生き法話」を二回致しましたが、これ又のんびりゆったり、遊び心の如くにお客様との距離感を縮めての楽しいお話でした。嗚呼!和尚も随分と歳をとったものだと改めて感じました。
明日からは気分を一新して、7月お盆の行事に専心して参りたいと思います。この一か月間大変お世話に成りました、お茶お花の各流各派の御社中の皆様方には心より厚く御礼申し上げます。本当に有り難うございました。友峰和尚より
滋賀北陸教区花園会役員会が彦根で開催され、今年度の活動計画についての色々討議がなされましたが、午前中には会議を無事に終えて帰山致しました。梅雨時期を迎えての大安禅寺一帯は実に趣が有って、参道に植えられたアジサイ群が見事なまでに咲き競っています。一か月に渡った花菖蒲祭も愈々明日で千秋楽を迎え、新命副住職が法務で留守をする為、午前午後の法話は和尚がすることとなりました。お時間の許す方は是非ご参加ください。寶勝寺でも法話が始まっていますが、最近の話題を取り入れながらの「楽く楽く法話」となっています。
夕方には、大安禅寺責任役員総代・藤田様そしてペット愛葬社社長の中村様が訪ねて来られ、しばし世間話も交えての三者談話会となったものでした。そこへ新たに飛び入りで2名の「寺ガール」が加わり、お茶をしながらの懇談会となりましたが、やはりお寺は賑わいが一番ですね。
一日中降り続いた雨さえもまたお友達です。禅問答に、『鏡清禅師あって僧に問う。門外これ何の声ぞ? 僧答えて曰く「雨滴声」』と有りますが、雨だれの音もこれまた風流中の風流です。雨だれの音の中に心の安らぎを感じるのは和尚だけでしょうか? カエルの鳴き声もまた風流ですし、六月の清風に揺られ竹のこすれる音も風流です。真理と向き合うことの少ない現代社会、いちど思い切って一人っきりになる事も又、風流なのかも知れません。明日は千秋楽、全身全霊で法話に臨みたいと思っています。友峰和尚より
早朝、朝顔の植え替え
地元某テレビ局の取材がまもなく寶勝寺で有ります。これまで、各局の取材目的は「寶勝寺・寺カフェ」についての和尚のコメント要請でしたが、今回は対談方式で、実際に寺カフェを利用して頂きながらのお話となるそうです。
沢山のお水をやりながら
「禅寺とカフェ」一見ミスマッチのように思えがちですが、そもそも昔からの禅語に「喫茶去(きっさこ)」と有るように、その意味は「どうぞお茶を召し上がれ!」で、お寺とお茶は古来より切っても切れない縁を有しています。現在日本で流通しているお抹茶のルーツなどは、禅宗の高僧・栄西禅師が1191年に中国からお茶の木を持ち帰り、「抹茶」として日本全国に広めて有名になったというくらいですから、いわば禅寺でお茶を振舞ったのは栄西禅師が元祖ということでしょうか。
「日中友好の朝顔」独特の曲線を描く葉
少々お話が飛躍しそうになりましたが、「お寺」という意味そのものもインドでは「ビハーラ」と言って「休憩する、憩い安らぐ場所」という意味ですから、全くに寺本来の姿こそ多くの市民の心安らぐ唯一の場所となることだと思われます。寶勝寺も最近では、寺カフェのお客様とは別に、和尚を訪ねて来られる客人も増えてきました。その際もお茶を振舞いますが、どうやら「お茶を飲みながらの会話」は、より親しみを増していくようです。
一日休まず伸びる新芽
お茶が取りもつ仏縁です。若者の寺離れが加速する現代社会に有って、今、卑山・寺カフェには多くの老若男女が集っています。「笑う門には福来る!怒る門にはホスピタル!涙の門には縁来る!」多くの方々との仏縁を結んでいく寶勝寺、いよいよその真価が問われそうです。友峰和尚より
本日の「楽く楽く法話」のようす
午前中から早々と夏日となりました。流石に連日の暑さに和尚もダウン寸前、自室にはクーラーが有りませんから、これからが本番の暑さ対策を講じなければと思いつつの法務遂行でした。一昨日に引き続いての「楽く楽く法話」をしましたが、本堂は冷房装置もよく効いていて、参拝者皆様にとっては極楽浄土の世界を味わって頂いたかと思っています。寶勝寺は比較的こじんまりとしたお寺だけに、冷房機器が極めて有効で本当に助かっています。
6月も終盤に入っていますが、お寺への人の出入りもこのところ急に増えてきたような気がします。7月はお盆月でもありますので、和尚は現在、福井と金沢のお寺4ヶ寺の盆施餓鬼会の準備に入っています。御先祖の霊供養ほど大切なものは有りませんね。お坊さんの仕事は諸事沢山ありますが、なかでも霊供養は、自分の心も合わせて供養することとなり、本当に心からの安らぎを覚えるものです。
午後、寺町台まちづくり協議会ならびに官公庁関係者の皆様と懇談
7月7日の七夕が「お盆の入り」になります。昔は「棚旗」と書いたそうですね。特別に施餓鬼棚を縁側に造り、五色の旗を立てての御先祖の御精霊迎え。素晴らしい事だと思います。和尚もせめてもの7月7日には、五色の短冊に、今は亡き両親の御霊に感謝の言葉を送りたいと思っています。友峰和尚より
昨日に引き続き「日中友好の朝顔」の設えをしましたが、なにぶんこの暑さですから苗がぐったりとして、おまけに強い風が吹き込んで今にもちぎれそうなため、暑さと風対策としてのガードを立てました。
どのような花もお世話が肝心で、面倒を見ただけ苗もそれに応えてくれますから、我が子を育てるがごとく細かい注意を払っています。皆様もきっとそうしておられることと思いますが、和尚も作業をする時には「しっかり育ってね!」とか「元気ですか!」とか、苗に声を掛けながらやっています。思えば昔々、花菖蒲を田んぼに植えた当初の頃は、苗の茎を撫でてあげていたものです。三十年たった今でも大安禅寺の花菖蒲の花が立派に咲くのはきっと、それに関わる大勢の方々の思い入れが花達に伝わっているからだと思います。

さて、寶勝寺での朝顔の開花を心待ちしながらのお世話が続いていきます。皆様、楽しみにお待ちください。そんな作業中、和尚の傍を寺カフェのお客様が通り過ぎて行きました。まもなく「朝顔ロード」の誕生です!! 友峰和尚より
6月23日 午前11時の「楽く楽く法話」 / 寳勝寺 本堂にて
寶勝寺での「楽く楽く法話」が本格的に始まっていますが、今日は飛騨高山地区からの団体様が来山されゆっくりと和尚のお話を聞いて頂きました。法話終了後には寺カフェもご利用くださり、寺本来の姿であります「ビハーラ」すなわち心の安らぎ、憩いの場所としての面目躍如と言ったところでしょうか。地元からも数名の方が拝聴下さり、このことも大変嬉しく思いました。「坊主は説法!!」ですね。お寺が活気づくことを祈るばかりです。
今日の法話では、観音様のお経を上げました。
さて、愈々朝顔の季節を迎えています。昨年は卑山・寳勝寺の山門より本堂に至る塀に沿って「日中友好の朝顔」を咲かせましたが、今年も昨年と同様に塀に沿って設えをしました。この朝顔は大変珍しい品種で由緒の有る花だけに、大切に育てています。
朝顔のネットを張りました。
平成26年の写真です。
平成26年 8月20日頃の写真です
写真の如く実に美しく大輪で気品のある色合いで毎年、鑑賞者の眼を楽しませてくれています。今回は朝顔の種を段階的にずらしながら発芽させ、10月ごろまで咲かせていく工夫をしようと考えています。幕末の歌人・橘曙覧先生の「楽しみは 朝起き出でて昨日まで 無かりし花の咲ける見る時」の歌そのままに、今から和尚も開花を楽しみにしています。これからは、花菖蒲から朝顔のお世話に替わっていく毎日が続きます。友峰和尚より
文房流晴心会・野口翆智社中 華展 「遊戯三昧」
爽やかな朝を迎えました。今日は暦の上で「夏至」だそうですから、一日を優雅に過ごしたいと願ったものでした。野口社中の3名様が早朝よりお花のお水替えに来られ、お茶会のお礼を兼ねて応接間にてティータイムとなりました。

野口社中の浅野正美様・中出裕美子様・伊藤英子様とともに / 大安禅寺 応接室
昨日の疲れが有ろうかと思われますが、そのようなそぶりも見せず元気いっぱいのお姿に感心いたしました。皆様の生け花を紹介しますと次の如くですが、いづれのお花も生き生きとして見事な生け花です。
六月の清風が寺内を心地よく吹き抜け、各所に活けられた花木の枝葉を揺らす様には息をのむほどです。お寺のシチュエーションは、その伝統的建物の歴史が語り掛けて来るかの如く枯淡で清楚さを感じさせてくれるに十分です。
この日を待ち望んていたかのように、華たちは競ってその大胆な姿を参拝者の方々に見せつけるかのように大見得を切っているかのようです。生け花の「摩訶不思議」は、活け込まれた時よりも数日経った時の方が「形」が整うということです。花は生き物ですから、それぞれに自分の居場所を見つけていきます。人間も又、昨日よりも今日、自分の居場所をさらに整えて行きたいものですね。見事に生け込まれた文房流晴心会・野口翠智社中皆様の華展を、今日の日長と共に十分に楽しんだ一日となりました。友峰和尚より
天気予報では終日雨ということでしたが、朝方には雨も上がり木漏れ日の照らす境内は一段と輝いて見えたものです。今日は文房流晴心会・野口翠智社中皆様のお茶会と有って和尚も気合を入れて臨みましたが、予想通りの社中皆様の活躍ぶりで、多くのお客様をお迎えしての素晴らしいお茶席となりました。
和尚も今年は二度のご縁を得て、最初と最後のお茶席に入らせて頂きました。強く感じましたことは、始めから終了まで、社中皆様の疲れを見せない優雅な立ち居振る舞いでした。「素晴らしい!!」の一言に尽きます。「立派」です。約200名を超える来席者だったと思いますが、昨年にも増して盛大なお茶会でした。「天知る 地知る 我知る」という言葉が有るように、何事も主催者の集中力が良い結果を生んでいくようです。さて、「第32回花菖蒲祭」も、今日で山を越えた感が有ります。明日からは日々を楽しみながら、千秋楽を迎えて行きたいと思っています。あと一週間ですが、文房流晴心会の生け花を皆様どうか是非ともご覧頂きたいと思います。堂内のあちこちに活け込まれている花々は実に見事です。
御家元姉崎素山先生御一行様
 文房流晴心会・野口社中の皆様とともに / 大安禅寺 本堂にて
文房流晴心会・野口社中の皆様とともに / 大安禅寺 本堂にて
心のこもった生け花の一つ一つが、きっと皆様に語り掛けてくれることと思います。一か月に渡るお祭り、多くの方との出会いが和尚の生きがいとなって行くようです。友峰和尚より
この時期としては涼しく、穏やかで過ごしやすい土曜日の一日となりました。北陸地方も梅雨入り宣言がなされお天気が心配されましたが、予想に反してお花には最適の「花曇り」で、参道から続くアジサイが見事な開花を見せています。花菖蒲が名残花になっていますが、それに代わって薔薇が満開となりました。来年は「花菖蒲祭」から「参華(さんげ)祭り」とイベントタイトルを変えて開催したいと思っています。今日のご来山者方々は、実にゆっくりとお花を見ておられたように思います。そんななか、和尚のお客様が次々と来られ、賑やかさを増して行きました。片岡経営会計事務所社長の片岡正太郎様ご家族はじめ日本生命支社長の松平様御一行様、そして、娘夫婦が嫁ぎ先の御両親と共に、サプライズで訪問いたしました。明日が父の日という事もあって、孫たちを伴っての突然の帰省に感激しました。孫達と会えるのは本当に嬉しいものですね。
文房流晴心会・野口翆智先生、黒川翆江先生 と 片岡経営会計事務所・片岡正太郎様ご家族
布川様ご夫妻と娘夫婦
この時季、皆様はいかがお過ごしになられておられますか? 三十有余年に渡って続けられて来た「花菖蒲祭」ですが、和尚にとっては多くの方々と一年に一度の親交を深める大切な「出会い祭り」の季節となっています。明日は、文房流晴心会・野口翠智社中皆様によるお煎茶席と生け花展が開催されますが、今回のお祭りも愈々終盤を迎えようとしているようです。友峰和尚より
お誕生日おめでとうございます!
お誕生日のお祝いは幾つになっても嬉しいものですね。今朝一番の来訪者は卑山、大安禅寺の責任役員総代・藤田通麿様でしたが、本日6月19日が七十七歳喜寿の御誕生日だそうで、先日、家族総出の喜寿御祝い会が開催されたそうです。今日のご訪問は、御友人からの依頼で和尚に「やまがたのサクランボ」を届けて下さったわけですが、その際「喜寿御祝の言葉」を述べさせて頂きました。
今年も花菖蒲祭期間中、藤田様手作りの「苔玉」を販売していますが、これが大変人気を博しています。藤田様には現在、大安寺観光協会会長としてもお世話になっており、「手作り苔玉販売」は大安寺観光協会として実施しているイベントですが、今後は大安寺地区発展のための「あじさいロード」造成を提案されておりこれから大安寺地区全体にあじさい運動が広がって行くことを念願しています。
萬谷様ご夫妻とともに / 大安禅寺 応接室にて
「来る人も 又 来る人も 福の神!」なんて言葉が有りますように、続いて来られましたのは萬谷さまご夫妻。以前、卑山にご縁を頂いておりました職員の御両親ですが、久しぶりの楽しい会話となりました。この時期は多くの方々とお会いしますが、お元気な姿に接することは大変嬉しいですね。「出会いの寺・大安禅寺!」 四百年前から、人々との仏縁を大切にしてきた大安禅寺。これからもずっとそう願いたいと思っています。
未生流福井支部の皆様とともに / 大安禅寺 愈好亭にて
さて、この一週間、素晴らしい生け花を披露して下さった未生流・山口先生はじめ会員の皆様には本当にありがとうございました。友峰和尚より