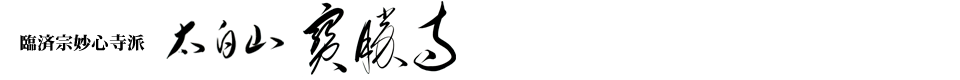和尚のちょっといい話
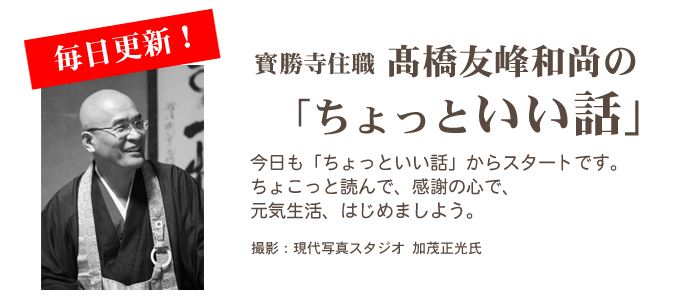 |

吉祥草 / 寳勝寺玄関にて
明後日12日(木)午後6時半より、月例の木曜坐禅会が開催されます。今年最後の坐禅会となりますが、大いにご参加頂き「無事」の心を味わい感謝の気持ちで坐って頂ければ幸いです。「艱難、汝を玉にす」の諺の如く、一年を振り返ると平坦な日など一日も無く、山あり谷ありの試練の日々を乗り越えて行くところに本当の安心(あんじん)が有ります。

また「楽あれば苦あり 苦あれば楽あり」ですが、苦も楽も無いに越した事は無く、究極「無事」の心が有り難いのです。坐禅を始めて約半世紀になりますが、坐禅ほど気持ちの落ち着く方法は他に無いように思います。皆様! 禅寺での坐禅のひと時を体験してみませんか!是非御来寺をお待ちしています。

さて、今日もふれあいパーク霊苑の第2期工事が進められていますが、今年はまだ雪もなく気温も穏やかで土木工事には全く幸いです。何もかもが有り難し!有り難し! 和尚も年を取りすぎましたか? 何物にも合掌するばかりの日々が続いています。友峰和尚より

ふれあいパーク霊苑 第2期工事が始まりました
秋晴れとなった好天気のもと、卑山「ふれあいパーク霊苑」第2期工事が㈱豊蔵組の施工で本日より始まりました。来年には開苑3周年を迎えるのですが、苑内に植栽された木々や草花もしっかり育ち、特に幾種類もの薔薇の花が参詣者の心を癒してくれているようです。

苑内に咲き続ける 幾種類もの薔薇





㈱豊蔵組 江川部長とともに
理想的霊苑の有り方を模索しながらの未来志向型霊苑を完成させたわけですが、地元の方々には未来の住処(すみか)としてのご理解と共に「墓じまい」を防ぐための「期限付き墓地」として、「永代墓システム」も少しずつ浸透しているようで安堵しています。和尚自身の年齢に同調しながら、これからの霊供養の方向性を更に工夫し、祖霊供養の重要性を布教して参りたいと願っています。

須貝総代様御夫妻とご親戚の方、御友人皆様とともに
さて、じりじりと師走に向かって待ったなしの状況ですが、霊苑には多くの参詣者が訪れています。本日も卑山総代・須貝様の御親戚はじめ御友人の方が墓参に来寺下さいましたが、一年を通して何度でも参詣して頂ける霊苑を目指して参りたいものです。友峰和尚より
 ご遠方より御参詣下さり 誠にありがとうございました
ご遠方より御参詣下さり 誠にありがとうございました

冬の薔薇 / 宝勝寺ふれあいパーク霊苑にて
ケーブルテレビの番組「銀河チャンネル」の放送で中国歴史ドラマが幾つか放映されており、毎回録画をして時間の余裕のある時に鑑賞しています。そもそも中国歴史ドラマを見るきっかけとなったのは偶然で、たまたまチャンネルを替えていたところ唐時代の素晴らしい王宮の模様が映し出され、それと同時に俳優の着ている民族衣装に大変興味を持ち、それ以来「歴史考察」を重点に観ています。

宝勝寺檀信徒様の年忌御法要が修業されました

霊苑にて 墳墓開眼並びに御納骨法要が修業されました
日本の御皇室祭礼の儀式なども中国皇帝の儀式を範として伝来したものと聞き及んでいますが、絢爛豪華な佇まいやその色彩また衣装や髪形等どの場面も素晴らしく感動的なシーンが多く、日本の飛鳥時代や平安時代の御皇室や貴族の衣装と照らし合わせて見ています。これまでに鑑賞したドラマは「少林問答」「独孤伽羅」「麗王別姫」などですが、現在放映されている「瓔珞(えいらく)」は1600年代の清王朝・太祖高皇帝時代のドラマで興味深く鑑賞しています。皆様も機会が有りましたら是非ご覧頂きたいと思います。

このたび新たにご縁を頂きました御夫妻と、御友人の方とともに

桂岩寺 ご住職と
さて、昨日に引き続き午前午後とも法要を修業しました。夕刻には寺町一丁目の桂岩寺住職と会合を持ちましたが、年の瀬を控えますます法務が忙しくなって来た今日この頃です。友峰和尚より


寳勝寺の紅葉

午前午後とも御法要の一日となりましたが、師走月(しわすつき)は一年最後の月でもあり、年忌法要はじめ御先祖ご供養がこれからも多く修業されます。そもそも「師走」の語源は年末の僧侶の忙しい姿からついた言葉とあり「成る程!」とうなずけますが、現在ではお茶お花など御稽古事の御師匠さんを言うのだそうです。いずれにしても年末は誰もが忙しく走り回る姿は同じで、益々気忙しさが増してきたように思います。

本堂にて 年忌法要が修業されました

近年、年忌法要や祖先の霊供養を修業されるお家が少なくなって来ました。ニュースでは日本における今年の子供の年間出生数が遂に90万人を割ったそうで、「団塊の世代」と言われた昭和22年~24年の年間出生数が約300万人だった頃から比べ、3分の1以下にまで減少した事を考えますと、今後仏事はますます簡素化傾向に進むと思われます。少子高齢化社会に対応するための寺院の布教活動にも色々な工夫が求められているようです。友峰和尚より

夕刻、古田様御夫妻とともに

京都駅にて
随分と冷え込んだ京都の朝でした。北陸地方は雪という予報を耳にしながら京都駅を後に金沢へ向かいましたが、加賀温泉あたりからは予報どおり雪模様となり、辺り一面薄っすらと雪化粧していて本格的な冬の到来を感じたものでした。車窓からは、急ピッチで進められている北陸新幹線の高架橋工事が延々と続いており、金沢駅は人・人・人で、年の瀬の観光を楽しむ旅行客で賑わいを見せていました。
北陸新幹線高架橋工事を眺めつつ 金沢へ

須貝総代様御夫妻です
午後には卑山責任役員総代の須貝様ご夫妻が年末のご挨拶に来寺され、奥様手作りの「小布施大栗スイーツ」を持参下さり思わずパクリ!! なんとも口の中いっぱいに大栗の深い甘みと渋みが溶け出し、ワイン漬けの香りが広がるとても美味しい味わいでした。そう言えば昨年も持参下さり感心したことを思い出しました。旬のスイーツしかも手作りで心の篭ったお土産に感謝申し上げます。 小布施の大栗をワイン漬けに 奥様の手作りスイーツ
小布施の大栗をワイン漬けに 奥様の手作りスイーツ


ほくほくとした 大きな栗です

貴重な甘みとともに 感激の味わい
今日は今年初めての雪模様となり、普段より暖かくした部屋の中での須貝総代様ご夫婦との楽しい歓談のひと時でした。また福井より日頃お世話になっている辻岡様も来寺下さり、愈々今年も終わりに近づいていることを感じたものです。どうか皆様にはくれぐれも御身ご自愛くださいますよう御祈念申し上げます。友峰和尚より

福井市より 辻岡様が来寺くださいました

京都の冷え込みは半端なく容赦なく身体に浸透してきます。本日は宗務本所での「妙心寺派僧侶育成審議会」に出席しました。本山の役職に就いて8年目となりますが、宗務所長会議を始め年間の各会議にはすべて出席させて頂きました。



「桃栗三年、柿八年」の諺の如く本山の役職にも馴染んで来たように思いますが、年を経るごとに諸問題解決の難しさをしみじみ感じます。そのような事が自覚できただけでも大きな成果だったのかも知れません。所謂「言うは易く行うは難し」という事だと思います。臨済宗妙心寺派の今後の発展を願えば願うほど、立ちはだかる壁が増していくようです。







さて、今年も残り少なくなって来ました。京都に到着して直ぐに、妙心寺塔頭・雑華院様へ年末のご挨拶にお伺いしましたが、学生時代、塔頭寺院・東海庵に下宿していた頃のことを思い出していました。志高く!禅宗僧侶としての本分を自分自身に問いかけていた若き学生でもありました。あれから50年!! 今もなお相変わらずの自分に驚きます。東海庵の本堂縁側で一昼夜一人坐禅していた学生時代が懐かしくまた誇らしくも思った京都での会議となりました。友峰和尚より

すっかり落葉した 錦木(にしきぎ)
12月最後の月例木曜坐禅会が12日午後6時半より寳勝寺本堂で行われますが、今年の締めくくりでも有るので大いにご参加頂きたいと願っています。今年のテーマは「亥」の年ということで「吾道一以って之を貫く」でしたが、来年は「子」で干支の最初でも有るので「無事」を一年のテーマとしました。「子」と「無事」とはいったいどんな関係があるかと言えば、「子」は種(たね)が新芽を吹きだす様を現し「無事」に成長する事を意味します。一日を振り返り、心が無心にして平穏である状態を「無事」と言います。

坐禅はこの無事なる心境を実地体得するところに有りますが、身体と呼吸と心を整えるだけでもずいぶんと気持ちの良いものです。座布団一枚で幸せな気分が味わえるのですからこんな有り難いものは他に見当たりませんね。さて、本日は雨霰(あめあられ)の寒さ厳しい一日となりました。風邪にはご用心!ご用心!どうか暖かくしてお過ごしください。友峰和尚より

クリスマスローズ

三角屋根が設置されました

朝方はずいぶんと冷え込む今日この頃、皆様お元気にお過ごしでしょうか? 本格的な冬の到来を目前にして、寳勝寺玄関にも屋根からの落雪を防ぐための三角屋根が設置されました。時折強い北風を伴って霙(みぞれ)模様のお天気となっていますが、明日からの気候は雨マークがずらりと並んでいて思わず身震いしてしまいます。

松浦建設㈱ 松浦 弥 社長とともに


㈱豊蔵組 幹部の皆様とともに
年末とあってご挨拶に来寺されるお客様が次第に増えてきました。本日は、現在進行中の大安禅寺諸堂修理保存工事施工者、松浦建設㈱の松浦社長が来寺されしばし歓談しましたが、年明けには本格的な本堂の修理工事にかかるそうです。また㈱豊蔵組の幹部の方々も、宝勝寺ふれあいパーク霊苑第2期工事の件で来寺され、茶礼を介しての和やかな歓談の席となりました。

さて、相変わらず来年の干支図色紙描きが日課となっており本日も来寺下さった方々にお渡ししましたが、描けども描けども直ぐに無くなっていく状況は本当に嬉しいものです。描けば描くほどに絵も上達し「ねずみ」にも動きが出てきます。絵に命を吹き込み、本当の無事の心境を味わっていきたいものです。友峰和尚より


ご依頼の 祥月命日忌供養を修業しました
「三度焚く 飯さえ硬し 軟らかし 思うままには ならぬ世の中」とは陶芸家・北大路魯山人の言葉とか? 本日も懸命に来年の干支「子」図を描いたのですが、なかなか思うように描けず悪戦苦闘の一日となりました。何事もそうなのかも知れませんが、上手く描こうと思えば思うほど手がこわばり良い線が描けません。コーヒーを飲んだりお茶を飲んだりして何度も休憩を取りながら描いたものの今ひとつ調子が上がらず、なにくそ!!頑張れ!!と自分に言い聞かせながらの作業となりました。思うように描けぬのは、明らかに加齢から来る老化現象のせいにして、明日から再びチャレンジしましょう。

 気持ちを入れ替え、教化主事より依頼されていた滋賀北陸教区機関紙「いもこぢ」の原稿書きをしましたが、こちらはスムーズに終了出来ましたので良し!良し!。毎日ブログを書き続けていることもありスラスラと書けました。継続は力なりですね。干支色紙描きは一年に一度ですから、上手く描けなくても仕方がないことです。やはり努力を続けるしか上手くなる方法など無いようです。ピコ!! 友峰和尚より
気持ちを入れ替え、教化主事より依頼されていた滋賀北陸教区機関紙「いもこぢ」の原稿書きをしましたが、こちらはスムーズに終了出来ましたので良し!良し!。毎日ブログを書き続けていることもありスラスラと書けました。継続は力なりですね。干支色紙描きは一年に一度ですから、上手く描けなくても仕方がないことです。やはり努力を続けるしか上手くなる方法など無いようです。ピコ!! 友峰和尚より


今日から12月「師走月」に入りました! 今年も残すところあと1ヶ月ということで、寳勝寺志納所の衣替えをしてみました。「PECORA MOCORA(ペコラモコラ)」のオリジナル作品コーナーを充実させると共に、最近の御朱印ブームに合わせ「御朱印グッズコーナー」も新たに設えました。





御浄財志納御礼品でも有る和尚の色紙も干支色紙が加わり、なんとも賑やかな雰囲気となったものです。12月最初の日曜日とあって、寺カフェ利用の観光客の方々も足を止め親子で志納所に見入っている風景が見受けられました。寳勝寺お堂の全面修復工事も最終段階に入り、本堂裏の外壁工事と庫裏外壁工事を残すのみとなっていますが、色紙コーナーは多くの方々と寳勝寺との御縁を結んでくれています。さて、まもなく年末大掃除です!金沢兼務寺院4ヶ寺の大掃除! 段取り良く進めて参りましょう!! 友峰和尚より