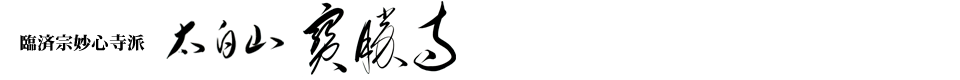寶勝寺日誌
昨日、住職のブログでもお話がありましたが、12月初旬、第二期修復工事が進められている本堂屋根裏から2枚の棟札が発見され、昨日関係者皆様の立ち合いの下、取り外す作業が行われました。本日はその詳細をご報告させて頂きます。
棟札の取り外しに際し、2社の地元テレビ局と3社の新聞社記者の方が取材にお越し下さいました。テレビでは昨日中に報道され、また今朝の新聞朝刊にも掲載して頂きました。丁寧な御取材と報道をして頂きましたこと厚く御礼申し上げます。
さて、棟札ですが、1枚は、本堂須弥壇の屋根裏部分(ご本尊観音様が安置されている壇の天井裏左側面の柱)に打ち付けられていました。住職、金沢市役所・歴史建造物整備課の皆様、松浦建設の方々、記者の方、テレビカメラマンや照明の方、などなど、総勢15名様が屋根裏に登り、垂木をかいくぐり、梁や柱をつたって現場まで向かいました。
こちら、屋根裏の様子です。地面は天井部分の為、降りることが出来ず、細い梁を伝って移動しました。
市役所の皆様や大工さん、テレビ局の方々も軽々と移動されていましたが、
私は前進後退を繰り返し慎重に移動しました…。
上の画像は、新しい垂木を設置する前(12月3日頃)の写真です。内部左側に見える四角い箱のようなもの(赤丸)が須弥壇天井裏に当たり、棟札は、緑矢印付近に、ご本尊様と同じ方向を向いて打ち付けられていました。
上段右から「皇風永扇 帝道遐昌 ”奉轉讀大般若経全部” 佛運紹隆 法輪常轉」二段右から「山門鎮静 衆僧無難 檀信歸崇」三段右から「火盗潜消 魔擾不起 諸縁吉利」下段右から「天保十四癸卯年 大悛道謹書 仲冬大甘露日」 ※天保十四年…1843年 表面・裏面とも、寳勝寺の繁栄と安寧、火災や盗難を防ぎ良い縁を得て発展するようにとの御祈祷の言葉が揮毫されています。
寺町の大工師・岩内様が丁寧に取り外して下さいました。直後に撮影
現場では、記者の方やテレビカメラによる撮影も行われました。
棟札はさらにもう一枚、内陣の天井上の柱に打ち付けられたものも発見され、確認のため取り外されました。こちらは、江戸時代末期から明治時代頃のものと思われ、現在詳細を調べているところです。
棟札が無事取り外され、階下へ降りる皆様。
屋根裏部分でも、柱の補強や筋交いとして、沢山の塔婆が使われている事がわかりました。
その後、本堂にて、2枚の棟札についての説明が行われました。
報道関係者の皆様からの質問に答える住職
記者の方からは主に棟札が発見されることの意義についての質問があり、住職は「寺の建築の歴史と文化財的評価を確かにすることは勿論、このお寺に住持した歴代住職や檀信徒の思いが伝わってくる大切な史料です…」とお話しされていました。
3時間近くに渡り行われた棟札の取り外し作業と記者会見。悪天候にもかかわらず現場の撮影から会見まで熱心に御取材頂き、誠に有難うございました。また金沢市歴史文化部・歴史建造物整備課の皆様にはいつも本当にお世話になり厚く御礼申し上げます。今後ともなにとぞよろしくお願い申し上げます。